―7―
「あらあら、何がどうなってるのかしら?」
輝夜さんと永琳さんがのんびりと姿を現し、幽霊と花にまみれた庭に目を丸くした。
「ねえ永琳、これはお花見と幽霊見のどっちをするべきだと思う?」
「輝夜の好きな方でいいわ」
「じゃあ、両方しましょう」
ぽんと手を叩き、輝夜さんは全く危機感のない顔で笑う。永琳さんも「そうね」と平然と頷きながら、「ウドンゲ」と鈴仙さんに手招きした。
「は、はい、師匠」
「何が起こっているのか、ちょっと調べてらっしゃい」
「わ、解りました!」
直立不動で応える鈴仙さん。「じゃあ、私はお花見幽霊見の支度でもしてくるわ」と永琳さんは屋敷の中へ引っ込んでいく。輝夜さんは縁側に腰を下ろして、幽霊に手を伸ばしていた。
「姫様、それじゃあ私はちょっとこの状況の調査に……」
「ああ、行ってらっしゃい。ところで、他のイナバはもう行っちゃったわよ?」
「え? あっ、てゐ、もういない! どこ行ったのよ、もう!」
頭を掻いて、それから鈴仙さんは私たちの方を振り向いた。
「……ところで、またついてくるとか言わないわよね?」
「同行してもいいのかしら?」
「お断りよ! じゃあね!」
調子のいい蓮子の言葉に、ふん、と鼻を鳴らして、鈴仙さんはひらりと塀を跳び越えて竹林へと消えていく。追いかける間も無いし、人間の私たちはあんな身軽に塀を越えられないから、追っても追いつけないだろう。
「あー、また逃げられちゃった」
「……どうするの、蓮子」
「さて、じゃあ私たちはてゐちゃんの方を探そうかしらね。そのへんで遊んでるでしょ。それじゃあ姫様、私たちもお邪魔しました」
「あら、行っちゃうの? こんなに花が綺麗なんだから、ゆっくりしていけばいいのに」
「せっかくですので、花めぐりでもして参りますわ。行くわよ、メリー」
「あ、う、うん。――お邪魔しました」
頭を下げて蓮子とともに永遠亭の玄関の方へ向かうと、輝夜さんは「行ってらっしゃい」とにこやかに手を振ってくれていた。
永遠亭の門をくぐると、改めて一面に咲き乱れた著莪の花たちが私たちを出迎えた。頭上は竹の花で埋まり、むっとするほどの花の匂いがたちこめている。六十年だかに一度の竹の花も、これだけ大量に咲いていると、いまいちありがたみを感じにくい。
「著莪の花って、春の日陰に咲くのよね。だから竹林にもよく咲くっていうけど――」
「……少なくとも、さっきまでこんな状態ではなかったわよね」
「竹の花もね。そもそも咲くこと自体激レアなわけで、植物学者や生物系カメラマンがここにいたら泣いて喜ぶでしょうけど」
「亜愛一郎とか?」
「まさしく。で、メリー、何かした?」
「何もしてないわよ」
何かの拍子に、一斉に花が咲き始めたということになる。著莪や竹の花だけでなく、永遠亭の庭には秋桜までも。まだ春だというのに――。
「著莪は春の花だし、竹の花は置いといて、問題は庭に咲いてた秋桜よね。あそこだけの狂い咲きなのか、それとも――他の場所でも季節外れの花が咲いているのか」
「向日葵とか?」
「そうよメリー。太陽の畑に行ってみれば確かめられるわ! あそこが夏のように向日葵畑と化していれば異変で確定ね。そうと決まれば急ぐわよ!」
確かに、この春先に向日葵が咲き乱れていたら、それは異変で間違いない。しかし――。
「ところで、どうやってこの竹林を抜け出すの?」
「……あ」
走り出そうとした相棒がぴたりと足を止める。この迷いの竹林には何度も来ているが、未だに案内なしで永遠亭に辿り着けた試しがない。帰りもまた同様、案内なしでは迷うこと必定だ。普段は鈴仙さんやてゐさん、あるいは迎えに来た妹紅さんや慧音さんに送ってもらうのだが。
「……まずは、てゐちゃんたちを探すわよ!」
「はいはい」
全く、せめてもう少し計画的に動けないものか。呆れながら蓮子に続いて歩き出す。
――と、そこへガサガサと物音をたてて、姿を現す影ひとつ。
「おん? なんだお前ら、永遠亭に来てたのか」
「あら、もこたん」
「もこたん言うな! 全く、輝夜に影響されやがって」
口を尖らせたのは、藤原妹紅さんである。もんぺのポケットに手を突っ込んで、妹紅さんは私たちと背後の永遠亭、それから足元や頭上に咲き乱れる花を見比べた。
「妹紅は、また姫様に喧嘩売りにきたの?」
「ああ――って違う。見ての通り、竹林中がこの状態だ。輝夜かあの藪医者か何かやらかしたに決まってるだろう。変な薬でも撒き散らしたか……」
「あら、残念だけど、たぶんそれは違うと思うわ」
「なに?」
「だって、永琳さんも姫様も驚いてたもの」
「だからって、あいつらの仕業でないとも言い切れないだろ」
「そうだと断定する根拠もないと思うけど」
「じゃあ蓮子、お前は何か犯人のアテでもあるのか?」
「そうねえ。とりあえず、太陽の畑にでも行ってみようかと」
「太陽の畑? ああ、あそこか……そういや、花好きの妖怪がいたな」
「ひょっとして、風見幽香さん?」
「名前は知らん。日傘を持った妖怪だよ。前にふらっと花畑を見つけて、慧音に摘んでってやろうかと思ったら、元気な花を無闇に摘むなって凄まれた。ありゃ相手にしたくないな」
妹紅さんは頭を掻く。風見幽香さんについては、去年の夏に阿求さんと太陽の畑を訪れたときにちらっと顔を合わせただけで、詳しいことは知らない。ただ、寺子屋に通っている花屋の娘の子によれば、たまに里の花屋に顔を出すらしいが――。
「彼女が花の妖怪なら、この状況について何か知っているかもね」
「というか蓮子、もしそうなら、ひょっとしてこの状況って」
「――風見幽香さんが犯人?」
ふむ、と蓮子は腕を組んで唸る。
「その可能性もあるけど、検討するには情報が足りないわね。やっぱり太陽の畑に行ってみないと。……というわけで、妹紅。悪いけど、竹林の外まで送ってもらえない?」
蓮子が片手を立てて拝むと、妹紅さんは肩を竦めて「解った」と頷いた。
「輝夜たちの仕業じゃないなら、私の炎で花を焼いちまうのも勿体ないしな」
「小火を出したら、また新聞ネタにされるしね」
「その話はもういいだろ! ったくあの鴉天狗……」
去年、永夜異変のあと、妹紅さんは輝夜さんとの喧嘩の結果、竹林に小火を出して、射命丸文さんの新聞の記事にされたのである。煙草の不始末とか何とか誤魔化していたっけ。
ともあれ、妹紅さんの先導で私たちは竹林の中を進む。どこもかしこも著莪の花だらけで、踏まずに歩くのは至難の業だった。ふわふわと幽霊もあちこちを漂っているし、妖精もどこからともなく現れてはしゃいでいる。妖精は花につられて来たのだろうけど――。
「しかし、この幽霊はどこから来たのかしらね。冥界の結界がまた緩んでるのかしら?」
蓮子が幽霊に手を伸ばしながら言う。幽霊はするりと蓮子の手を逃れて、ふわふわとどこかへ飛んでいった。
「まさか人間の里で大量虐殺が起きたわけでもないだろうし」
「怖いこと言わないでよ」
そんなことを言い合う私たちを、ちらりと振り返って妹紅さんは目を細めていた。
――ああ、と私は口をつぐむ。死ぬことのできない妹紅さんは、この大量の幽霊をどう思っているのだろう。羨んでいるのだろうか? それとも……。
「おっと、止まれ」
ぼんやりそんなことを考えていたら、急に妹紅さんが立ち止まって、私はその背中にぶつかってしまった。「ごめんなさい」と謝ると、「いいから、ちょっと伏せろ」と頭を押さえつけられる。言われるまま、茂みに身を隠すようにかがんで顔を上げると――。
「……弾幕ごっこ?」
「片方はてゐちゃんね。もう片方は……あれ、夜雀の屋台の女将じゃない?」
「ヤツメウナギの?」
言われてみれば、飛び回っている姿に見覚えがある。てゐさんとやりあっているのは、ヤツメウナギの屋台を引いている夜雀の子だ。妹紅さんと一緒に屋台に飲みに行ったこともある。確か、ミスティア・ローレライという名前だったっけ。
「喧嘩っていうより、浮かれてじゃれ合ってる感じね」
「そうね――あ、当たった」
ミスティアさんの放った光弾がてゐさんに当たって、著莪の花の中にてゐさんが墜落する。どうやらミスティアさんの勝ちらしい。
「どこまで飛んでも景色が変わらなーい。じゃあね~♪」
ミスティアさんはそう言って、どこかへ飛び去って行く。がばっと花の中から身を起こしたてゐさんは、こちらを振り向いて「なんだ、見てたの?」と笑った。
「大丈夫?」
「別に大したことないよ」
スカートを払って立ち上がり、それからてゐさんは妹紅さんの方を向く。
「姫様の宿敵じゃん。この花の異変は姫様やお師匠様の仕業じゃないよ~」
「じゃあ誰の仕業だってんだ?」
「さあて、ねえ。ま、何が原因でもいいって。こんなお祭り、騒がなきゃ損じゃん?」
タラッタラッタラッタ、うさぎのダンス~、と口ずさみながら、てゐさんもまたイナバたちを引き連れてどこかへ飛び跳ねていく。
「妖怪も浮かれてるな。そりゃあ久しぶりだから――」
妹紅さんが呆れ混じりに息を吐きながらそう言い、「ん?」と首を傾げた。蓮子が耳聡く、その言葉に反応する。
「久しぶり? 何が?」
「……いや、なんだったかな。前にもなんかこんなことがあったような……」
妹紅さんはこめかみを押さえて、ひとつ唸る。
「こんなことって、この花の異変?」
「うーん、思い出せん。前にもそういえば竹林が花だらけになったことがあったような気がするんだが、いつだったかな。……ダメだ、解らん」
私たちは顔を見合わせた。――過去にも、同じような異変があった?
―8―
竹林を出たところで妹紅さんと別れ、私たちは太陽の畑に向かった。竹林と太陽の畑は、同じ幻想郷の南部なのでさほど離れていない。妹紅さんは「ついて行こうか?」と言ったのだが、そこへ輝夜さんが永琳さんを伴って現れたのでうやむやになったのだ。
「あらあらもこたん、一緒にお花見と幽霊見しない?」
「何で私がお前らと――」
「いいじゃない。イナバたちが遊びに行っちゃって、永琳と二人だと寂しいのよ」
「知るか!」
仲良く(?)そんなことを言い合う妹紅さんたちを残して、私と蓮子は竹林を後にした。
竹林を出てから太陽の畑に向かう野道の周辺にも、やはり無数の花が咲き乱れている。タンポポや白詰草はわかるが、やはりよく見るとその中に菊や秋桜のような秋の花、芙蓉のような夏の花が一緒に咲いている。季節感がメチャクチャだ。
「これはもう完全に、局所的じゃなく幻想郷全体の現象のようね」
「幽霊も多いわね。冥界にいる気分」
「とすると、これは春雪異変と似たような異変なのかしら?」
相棒があごに手を当てて唸る。
「春雪異変のときは、お嬢様が冥界に春を集めたせいで他が冬になってしまったけれど……」
「じゃあ、今回は冬以外の季節を誰かが幻想郷に集めているの?」
「冥界とかが大寒波に見舞われてるのかもね」
「そういう概念を集めるというと……萃香さん?」
「萃香ちゃんなら宴会がセットじゃない? どこかで宴会が始まってないかしら」
そんな推理を巡らせながら歩いているうちに、ほどなく遠くに窪地が見えてくる。そこが太陽の畑だ。そして、見下ろしたその場所は――。
「……やっぱり」
「壮観ね」
案の定、真夏のように無数の向日葵で埋まっていた。今はまだ春だというのに、ここだけが完全に夏だ。本当に今は春だっただろうか、と自分の記憶を疑いたくなる光景である。
「さて、風見幽香さんを探しましょ」
窪地へ下りて、蓮子は私の手を引いて言う。
「それはいいけど、大丈夫なの?」
「何が?」
「私たち、あのひととは去年の夏に一瞬顔を合わせただけよ? 向こうが私たちのこと、覚えてるかどうかも解らないのに」
「……まあ、そのへんはなんとかなるでしょ。強い妖怪は紳士的だし」
「そんな適当な」
毎度ながら、この相棒の無鉄砲さはどうにかならないものか。
ともかく、まずは向日葵畑の周囲をぐるりと回ってみるが、風見幽香さんの姿も、あの薄紅色の日傘も見当たらない。目に付くのは咲き誇る向日葵と、その上を漂う妖精と幽霊ばかりだ。向日葵畑の中にいるのか、それともここにはいないのか――。
「留守じゃないの?」
「じゃあ、呼んでみる?」
「やめてよ」
そんなことを言い合っていた私は、不意に空を飛ぶ影に気づいた。見覚えのある人影が飛んでくる。あれは――魂魄妖夢さんではないか。
私が手を振ると、向こうも気づいて、私たちの傍に降り立った。蓮子が片手を挙げる。
「あら、妖夢さん。こんにちは」
「こんにちは。お二人はこんなところで何を?」
「季節外れの花を見物に。そちらは?」
「この世に来てみたらこの状況ですから、ちょっと調べてるんです。何か知りません?」
「さあ、私たちは何とも――冥界はどうなんです?」
「冥界ですか? 特に変わりはないですけど」
蓮子の問いに、妖夢さんはきょとんと目を見開く。
「結界が緩んだり、冥界の季節が奪われたりはしてないんですね?」
「……幽々子様のときとは違うと思いますが」
「季節外れの花が咲いてもいない?」
「少なくとも、私が出てきたときには、そういうことはありませんでした」
「冥界の幽霊が減ったりも?」
「そんなことも特には……結界は問題ないはずだし」
首を傾げる妖夢さんに、「なるほど」と蓮子は帽子を目深に被り直す。
「情報感謝しますわ。さすがに人間の足で冥界まで行くのは大変なので」
「はあ。……とりあえず私は、心当たりを回ってみます」
そう言って妖夢さんは、再びふわりと浮き上がる。
「あ、妖夢さん」
と、それを蓮子が呼び止めた。「なんです?」と妖夢さんは振り返る。
「以前、これと同じような異変が起きたという覚えはあります?」
蓮子の問いに、妖夢さんは「同じような?」と首を傾げた。
「いいえ……覚えがありません。それじゃあ」
それだけ言い残し、妖夢さんは迷いの竹林の方へ飛び去って行く。永遠亭に向かうのだろう。
それを見送って、相棒は「面白くなってきたわね」と猫のような笑みを浮かべた。
「冥界に変わりがないなら、あの幽霊たちは冥界から流れてきたわけじゃない。じゃあ、どこから流れてきたのかしら? 三途の川? 地獄? そして、なぜ季節外れの花が咲くのか。妹紅さんの言っていた、過去の同じような異変を妖夢さんは知らない。とすれば、それは妖夢さんが生まれる以前の出来事なのか――」
ぽん、と蓮子は手を叩いた。
「過去に同じ異変があったのかどうか、今回まず調べるべきは歴史だわ!」
―9―
そんなわけで、私たちは一路、人間の里へ引き返した。
里へ向かう野道も花だらけで、この調子なら里の中も花だらけだろう。花屋は商売あがったりに違いない。慧音さんら自警団は大騒ぎしているのだろうか。
「……っと、また誰かやりあってるわね」
蓮子が足を止めて視線を上げた。私もその視線の先を追う。里のほど近くで、ふたつの影がまた弾幕ごっこを繰り広げている。飛び交っているのは――音符とナイフだ。
「あれ、咲夜さんじゃない?」
「そうね。もう片方は――騒霊楽団のキーボードの子かしら?」
勝負は咲夜さんの方が優勢のようだった。キーボードの子は、降りそそぐナイフの雨の中を必死に逃げ惑っているが、完全に追いつめられている。このままでは後が無いと悟ったのか、破れかぶれのような突撃をしかけたが、咲夜さんにあっさりいなされ――私たちのいる方にはじき飛ばされてきた。
近くの草むらに、キーボードごと落ちてきた騒霊楽団の子は、「ぎゃふん」と呻く。咲夜さんはそれを一瞥するでもなく手を払い、どこかへ飛び去って行った。おそらく彼女も、この異変の原因を調べているのだろう。ということは、霊夢さんや魔理沙さんもどこかで誰かとやりあっているに違いない。これは大騒ぎだ。
「もしもーし?」
と、蓮子が花に埋もれたキーボードの子に呼びかける。キーボードの子は目をぱちくりさせて、「おおう」と呻いて起き上がった。
「あらら、オーディエンスがいたの? ごめんねー、いい演奏できなくて」
「いえいえ、たまたま通りかかっただけで。騒霊楽団の?」
「リリカよ。覚えてほしいし聴いてほしかったなあ」
「それはごめんなさい、是非今度ゆっくり。今日は三人一緒じゃないのね」
「今日はソロ活動。色んな音を集めてるの」
「音?」
「さっきのナイフの音も何かに使えないかなあ」
前衛音楽か何かか。そういえば宴会で騒霊楽団の演奏を聴いていても、バイオリンとトランペットが耳につくわりに、キーボードの音はあまり印象に残らない気がするが……。
「音じゃなくて、幽霊を集めてたんじゃないの?」
蓮子が不意にそう問うと、リリカさんは目をぱちくりさせる。
「幽霊? そういえば花景色というより妖精景色、幽霊景色だけど」
「冥界での宴会とかで、貴方たちの演奏によく幽霊が集まってたじゃない」
「あー、そりゃ主にメル姉のトランペットに陽気な幽霊が集まってるの。あとは陰気な霊がルナ姉の方に集まってるか、そのどっちか。私はふたりの調整役だからねー」
「調整役?」
「ルナ姉の音は鬱の音。メル姉の音は躁の音。どっちも単体だとテンションが下がりすぎたり上がりすぎたりしちゃうから、私の幻想の音がそれを取り持って、人間でも聞ける音にしてるのよ。つまり騒霊楽団で一番偉いのはこの私」
「ははあ。同じ幽霊どうしで引き合ってるとかそういうわけじゃないのね」
「幽霊と騒霊は違うよー。一緒にしないでほしいなあ」
リリカさんはそう頬を膨らませて、それから私たちを交互に見やった。
「あ、そうだ。貴方たちも何かいい音持ってない?」
「ええ? 急にそんなこと言われても」
「そりゃ残念、今度ライブ聴きにきてね~」
ふわりと浮き上がり、リリカさんはそう言って飛び去って行く。みんな忙しないことだ。
――と、そのリリカさんの後をつけるように飛んでいくふたつの影に、私は気づく。黒い影と白い影。あれは……騒霊楽団の残りのふたりではないか?
リリカさんと合流しようとしているのか、それともストーキングしているのか。よくわからないが、少なくともリリカさんは後ろにお姉さんたちがいるのは気づいてなさそうだ。
「騒霊楽団の仕業でもない、と」
蓮子は何か納得したように頷いている。
「彼女たちがハーメルンでもしてるのかと思ったんだけどね」
「あの子も言ってたけど、幽霊と騒霊は別のものでしょう?」
騒霊楽団は、騒霊というだけあってポルターガイストのはずだ。ポルターガイストは霊とは名付けられてはいるが、概念としては幽霊より生き霊の方に近いはずである。
「そう、そのはずだけどね……」
蓮子は帽子の庇を弄りながら、言葉を濁すように呟いた。
「幽霊が多すぎると思うのよ」
「……まあ、確かにたくさんいるけど」
「どうも、前提から再確認しないといけないわね」
「何が?」
「幽霊について、よ」
よく解らないことを言って、相棒は里に向かって歩き出す。
私は慌てて、その後を追いかけた。
――この時点では、我が相棒は真実を見誤っていた。
ルナサ・プリズムリバー、メルラン・プリズムリバー、リリカ・プリズムリバーの三姉妹からなる、プリズムリバー騒霊楽団。
バイオリンと、トランペットと、キーボードを奏でるポルターガイスト三姉妹。
鬱と躁と幻想の音を紡ぐ、騒がしい霊たち――。
彼女たちもまた、この異変の犯人である。
第5章 花映塚編 一覧
感想をツイートする
ツイート








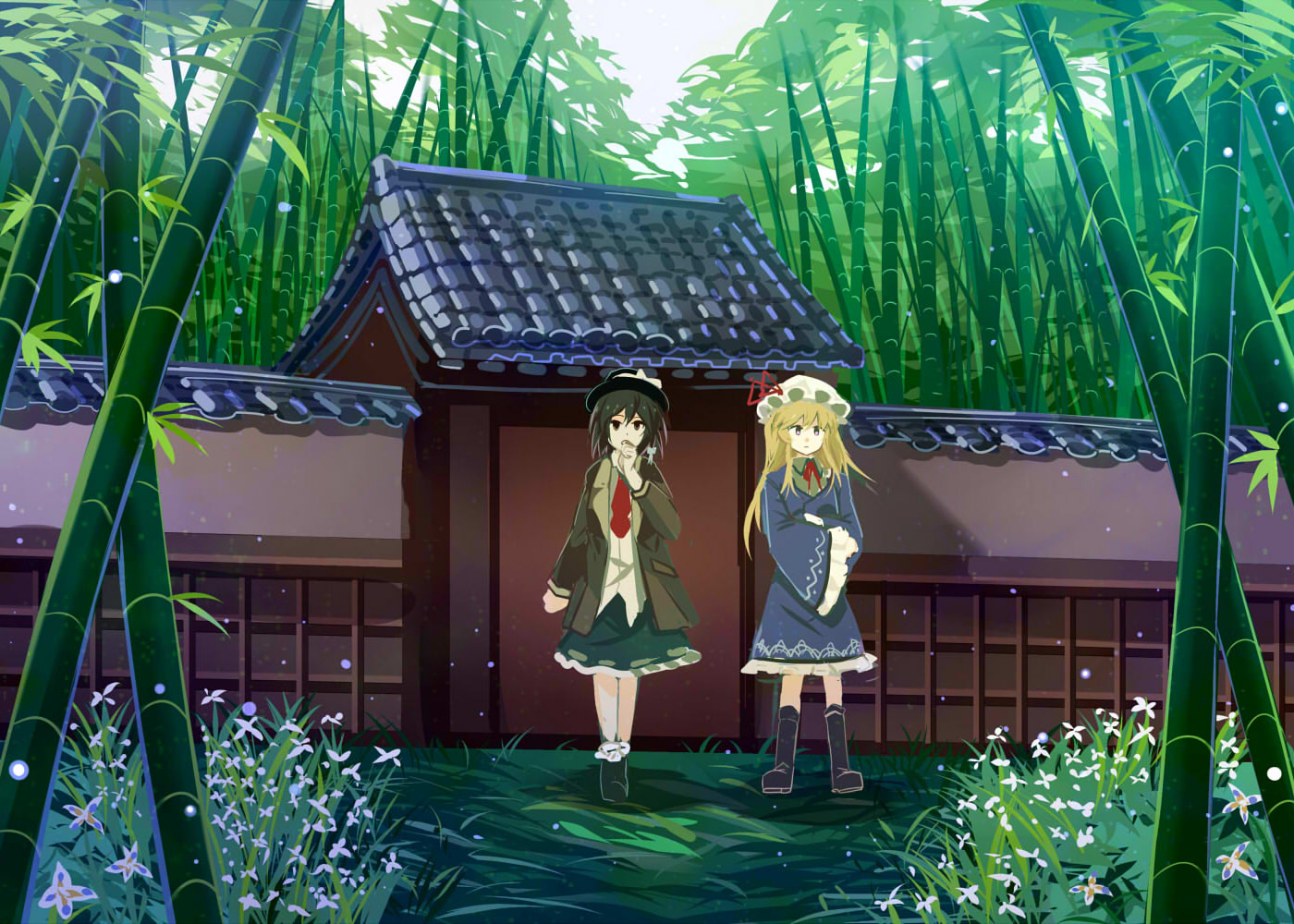



うーん、幽香だけでなく騒霊三姉妹まで絡むとなると、複数の人物が意図せずに起こしているということなのかな?わくわくしてきました。
次回も楽しみにしております。