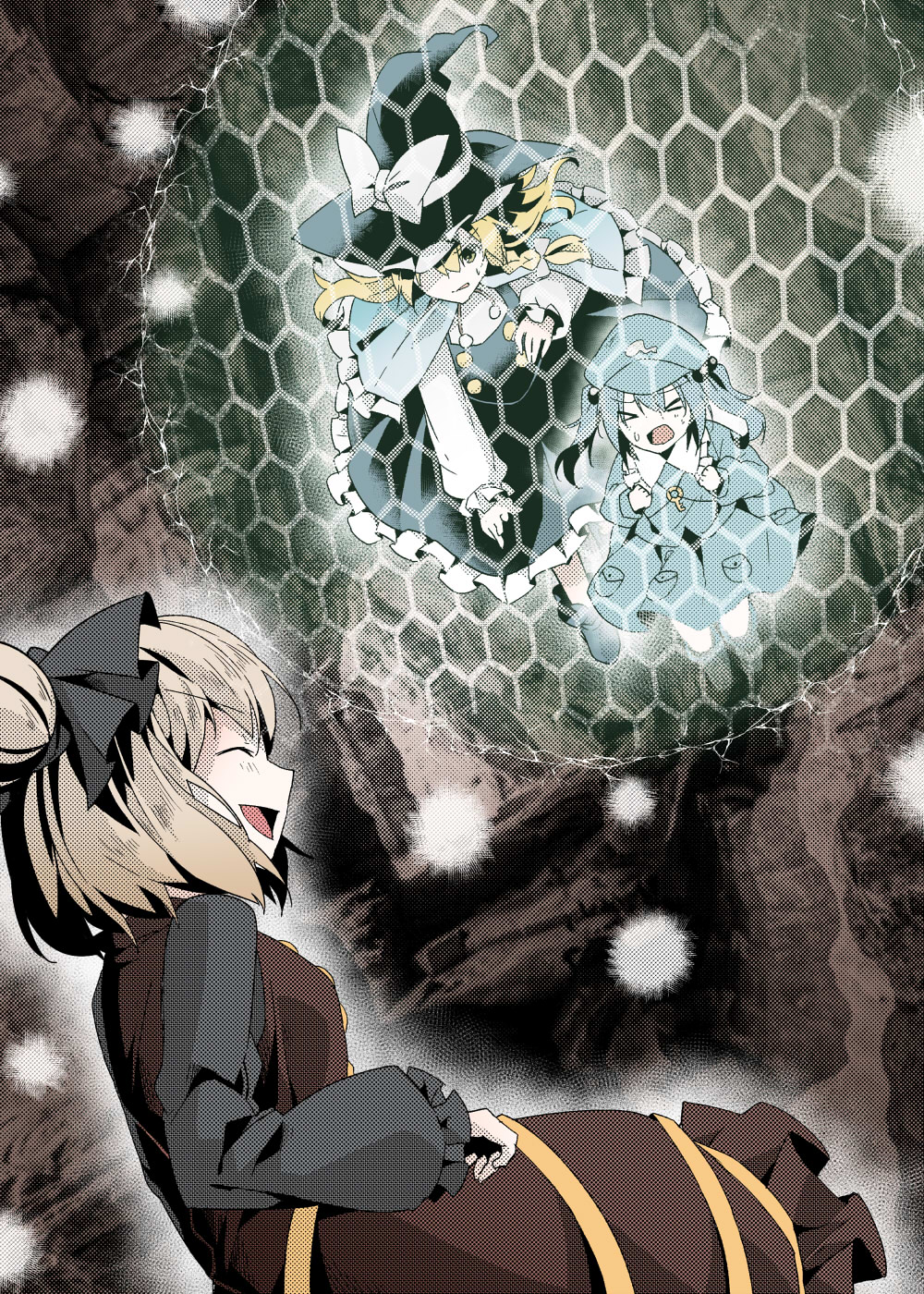楽園の確率~Paradiseshift.第1章 火の国のヤマノメ 火の国のヤマノメ 第10話
所属カテゴリー: 楽園の確率~Paradiseshift.第1章 火の国のヤマノメ
公開日:2017年01月30日 / 最終更新日:2017年01月30日
楽園の確率 ~ Paradise Shift. 第1章
火の国のヤマノメ 第10話
ヤマノメが為朝との決戦に合流するとの旨は、田道間を通じてその日の内にひょうず達に伝えられ、先に彼が言った通りに合意を得られた。
「オレは万寿のことを恩に着せる気は無いし、あいつにだってそんな考えは無かったろう。オレからすれば、オレや他の土蜘蛛には協力を仰がず、一人で勝手に事を進めたのはあいつだ。ひょうずを手勢に使おうと考えていたのかも知れないんだ」
これも傍から見たればこその考え。ヤマノメは万寿の思いを、彼女が如何なる考えで土蜘蛛ではなくひょうず達に協力を仰いだのかを知りながらも言った。
「万寿御前はそれを望んでいたか? お主らは?」
「流石は田道間様。それもお見通しだったか」
彼女も当初は、妖に、勿怪になったのを嘆いていたであろうが、最期には誇っていた。土蜘蛛である自身を。
ならば他の土蜘蛛も同じ。今のヤマノメの様に、己の由緒を知らぬ者ですらそうなのだ。天道や所謂“お上”への反骨や恨みの心は、今も土蜘蛛が共通して抱くもの。だが、人間の力を借りてまで世を覆そうなどとは考えない。
「かと言って、あいつが田道間様達を低く見ていた訳でもない」
「そう。あの方は、ワシらと義親公の思いを同時に汲もうとして下さっただけだ」
そして万寿自身の思い。敗残者たる恨みを晴らそうとしたのではなく、巫女王としての役割を果たそうとしたのだ。
「それにしても不安です。為朝の如き童に国を覆せますかな」
童。彼はまだ、ただの悪童にすぎない。祖父の大業を今こそ為さんとするのも、鎮西に己を追いやった父か、兄達を見返すためでしかないのだ。その未熟な心がいずれ、ずば抜けた武力と並んだ時こそ、万寿が期待した義親の嫡孫、鎮西総追捕使為朝となる。
「信じるしかあるまい。そのためにはまず、我らが勝たねばならぬ。たとえ今、為朝が鎮西を平定してもいずれは、来たる官軍に負ける」
今行く手を挫かねば、彼は祖父義親と同じ末路を迎えてしまう。
「それに龍蛇相手となれば、負けてもなんとか面目は立ちますか」
それもそうだと、田道間は意図の外であったヤマノメの言葉に同意し、横たわる龍蛇の背を何度か叩く。中はひょうずが入れるように作られているが、ただの空洞の様な反響は返さず、その分洞穴内で金属音が響く。
当初短かった胴は、今や龍と呼ぶにも相応しい十丈を上回る全長となり、特段の意匠も施されていなかった頭部も、恐ろしげな毒蛇の物になっている。
「始めは奴の手勢に、せいぜいが豊後の家遠の軍が加わるだけかと思っていたのでな。今国衙に在する兵ならば、それで十分間に合うはずだからな」
しかしそこに肥後の忠国や、併合した肥前諸氏の軍が合流する恐れが出てきたことから、この龍蛇を当初より強大にするに至ったのだと田道間は言った。
「しかし、これだけの『鎧』をよくもまあ」
彼は、人の面なら覆ってしまえるほどの鱗を持ち上げながら答える。
「言っただろう。燃石など扱えず、僅かな量に留まるが、ワシらも“これ”を用いると」
銅やスズ、鉄に水銀なども。金気を忌避する他の水界のモノ達と一線を画すのが、彼ら。
「そうだ燃石を使った精錬ですが、一つ問題があるんだ」
「瘴気を除く以外にまだ何かあるのか」
「またそれなのです。どんなに瘴気を除けても、これは完全に抜ける訳じゃないみたいでな。どうやってみても玉鋼が出来ないのです」
砂鉄や重く硬い木炭を用い、蹈鞴(たたら)によって僅かに取り出せるのが玉鋼。元は土蜘蛛も生産していたが、土蜘蛛にとっては使い道の無い物となって久しかった。
「それこそは、今もワシ等の領分だな。新しい業も便利なだけでは無いか」
もしかしたら万寿も、かつての技を用いて義親にこれを提供していたのかも知れない。
(やはりオレは、お前に成り得ないみたいだぞ)
だから彼女は託してくれたのだろう、今のヤマノメに。
そんな感慨に浸るヤマノメと、それを見守る田道間に、別のひょうず二人が足音を響かせながら駆け寄る。
「田道間様、一大事です!」
(為朝か? だとしたら随分早いな)
忠国の館での出来事からは、まだひと月ほどしか経っていない。いくら阿蘇の忠国が協力したとしても、敵対する土豪の制圧がせいぜい。太宰府に寄せられるほど、兵を掌握出来たとは考えにくい。
そのひょうずが耳打ちしようとするのを田道間が咎め、報告はヤマノメにももたらされる。それはやはり、為朝の来襲を告げるものであった。
「肥前の原田との戦も終わったばかりでまさかとお思いでしょうが、為朝は今、元からの手勢だけを動かしている模様でして」
ならば人心掌握の手間は無いし、大軍を動かす時の様な種々の準備も省略でき、小回りも利く。だがそれで太宰府を落とすなど叶うものか。
「奴の手勢はたかだか二十騎程度のはず、いや……」
豊後勢を後詰めとして配するか、もしかしたら海賊を用いて海路より寄せさせるのかも知れない。現在、陸路を北上しつつある為朝と率いる手勢こそ、後詰めとも考えられる。
「勝てますかな」
「尋常であれば、な」
阿蘇からの兵を想定しての十分な備えがあっても、彼相手では少しの油断も許されない。
だが、いずれにせよやるしかないのだと、ヤマノメは身を震わせながら、幾度めかの決意を己に確認した。
∴
背振の山脈の南端。基肄(きい)の山城と付随する水城を避け、武士の一団が筑後川支流の川沿いを北上する。
僅かに二十騎、徒武者を含めても五十人足らずの兵であればこそ、それらを避けて通るのも叶う。一団の将、鎮西八郎為朝の策の一つはそれであった。
「御曹司。霧が出て来ましたが、このまま進むので?」
「むしろ都合がいい、このまま進むぞ」
重代の重宝、源氏八領が一種である『八龍(はちりよう)(※1)』を模した白糸威(しろいとおどし)の大鎧を纏い、九尺もある重藤の弓を担いだ為朝が命じる。跨がる馬は先に平らげた菊池から召し上げた、大陸北方の血を色濃く残す巨体の駿馬。佩刀は、これも源氏重代の太刀、吠丸。
武家の惣領の御曹司に相応しい出で立ちの彼が堂々と号するのに、手勢らは粛々と従う。
その巨馬と大丈夫に並んで歩く一人の法師が、先の郎党の別の懸念を持って進言する。
「若大将、ここはヤバいかも知れません」
「ヤバい?」
「危うし事が待っているやもと。我が山には、義親公が太宰府に兵を寄せようとした際、それを阻んだ勿怪の記録が残っております」
「夜叉丸よ。よもやそれは、兵主部の事か?」
彼の進言を側で聞いていた、別の壮年の武者が問う。
「お、後藤の大将はご存じなのか」
「我らの本所の肥前にも伝わるモノだ。それが不安ならしかし、御曹司も安心なされよ。我には策があります」
「うむ。夜叉丸、高宗(たかむね)はこう言っているが、どうか?」
「ならば、よろしいでしょうが……」
そう言いながらも夜叉丸は、周囲に満ちる不穏な気配を察知している。霧はより濃密になり、二十間先も見通せぬ程。彼はその霧の先にある気配の大元を認めた。
「若大将。どうやら敵は、国衙やひょうすべだけではないようですぜ」
乳色の大気に、尋常でなく巨大な影が映し出されていた。
ひたりひたりと、濡れた静かな足音が、川沿いを行く為朝の一団を包囲しつつある。彼らは正面に現れた龍蛇の影に気を取られ、それに気づきもしていない。
「ヤマノメよ、他は我らが引き受ける。お主は為朝のみを狙え」
「承知しました」
だがまだ早い。周囲には為朝を守るように騎馬武者が展開し、龍蛇を迎え撃とうと後方に居た徒武者も前進を始めている。恐れる事無くあの大蛇に立ち向かおうというのだ、ただの侍なら蛮勇と評されるところ、為朝が誇る手勢ではそうとも言いがたい。
霧の向こうの龍蛇が重々しく鎌首をもたげる。
身の丈およそ三丈にも上るその姿に怯む事無く――
「放てぇ!」
馬上の武者が一斉に矢を放つと同時に、徒武者が薙刀を手に鬨の声を上げ、斬りかかる。
しかし如何に強弓を以てしても、青銅の鱗に鎧われた大蛇を貫く事あたわず、薙刀の刃も表面に疵を刻むだけ。
そこに大蛇の頭が鉄槌として振り下ろされ、また前進せんと蛇行すると、肉薄していた徒武者は潰されるか轢かれるか、あるいは弾き飛ばされた。
さしもの彼らも驚くが、為朝が再び鎌首をもたげた大蛇に向かって弓を引くのを見て、落ち着きを取り戻している。
そこから先は、ヤマノメ達が驚く番であった。
引き絞るのは八人張りの弓。引き分けるには相応の力と共に技量も必要とされるが、為朝は極めて滑らかにそれを為している。
短刀を交差させた様な巨大な雁股の矢が放たれると、風を巻き、霧を貫きながら飛翔する。それも最初から分かっていたかのように、機巧の大蛇の痛点に向けて。
ヤマノメも一瞬肝を冷やすが、そこを守るのは特に頑強な鉄の鱗。空前の剛弓から放たれたその矢すらも弾いて見せた。
為朝は表情も変えず、視線も乱さず、箙(えびら)から速やかに矢を抜き、番える。
一瞬だけ並んだ腕の異様さに、人外であるヤマノメや、田道間ですら驚きを露わにする。
「あの腕はなんだ!?」
弓手が馬手より明らかに長い。拳一つ分ほどであるが、その手は八人張りの強弓をやはり軽々と引き分け、達人の限界すらも超えて引き絞る。
番えるのは、鑿の如く分厚く広い平根の矢。
「いかん!」
田道間が潜むのを止め、手にした矛を投げつけようとした直前、矢は放たれた。
第一射よりも低い音が大気を揺らし、大蛇の喉元に食らいつく。鉄の鱗を貫かれ、背側の青銅の鱗も散らして大蛇は地に伏した。
「どうか!」
「し、死んでおるようです!」
残心を取りながら為朝が叫ぶと、前進していた徒武者が駆け寄り、検分して言った。
それを受けて為朝ら騎馬武者は大蛇の側に寄る。突如現れた怪物を倒したのには安堵した様子であるが、彼らの考える戦場はまだまだ先。少しの油断も見られない。
為朝は、自ら貫いた鉄の鱗を剥ぎ取ると、近くの騎馬武者に預ける。だが馬が重みに負け、膝をついてしまった。
「御曹司。これは、無理です」
「まあ、こんな物はどうでもいいか。しかし」
「若大将!」
「分かっている!」
剥がされた鱗の内側から、蓑を背負って矛を構えた男が躍り出る。彼はすぐに為朝に切り伏せられたが、それを皮切りに大蛇の中から、川や岸辺の森からも、蓑を纏い矛を携えた男達が現れ、包囲する。
数は為朝達の倍、一人一人の力も人間を上回る。やはり尋常であれば負ける理由は無い。
「これがひょうずですぞ!」
叫びながら夜叉丸が次々と礫を放つが、射撃は目に見える範囲に留まる。
「各々方! 辺りの敵を散らしつつ戦列を整えよ! 亥の方へ向かって進め!」
為朝の号令に従い、徒武者と騎馬が速やかに体勢を立て直す。同時に従わなかった者には、容赦なく矢が放たれる。そして射撃は、的を違えなかった。
「これが為朝の軍か」
寡兵ながら恐れを見せぬ整斉とした動き。だがそれも仇となる。相対的に後方に下がった為朝を兵達から切り離そうと、ひょうずも側面から戦列を組んで前衛を襲う。
前衛で矛と薙刀が火花を散らす後ろから、ついにヤマノメ達が躍りかかる。
「為朝ぉ!」
しかしそれを阻まんと一騎が跳ね飛び、立ち塞がる。
「面妖な賊共が!」
壮年の武者が鋭く太刀を振り払い、ヤマノメを切りつけた。弾かれると同時に衣が裂かれ、脇腹に傷を刻まれるが、皮より頑強な肉はその刃を通さない。
腰から落ちたヤマノメに続いて、また数人のひょうずが前に出る。それにも壮年の武者は怖じ気づかず、堂々と迎え撃ちながら、朗々と詠い上げる。
「兵主部よ、約束せしを忘るるな、かわたつをのこ、われもすがわら」
それを聞いたひょうず達は一斉に膝を着き、頭を垂れる。
「道真公が残した兵主部調伏の歌です。さあ、前衛を――」
ひれ伏したひょうず達や、起き上がろうとするヤマノメの側を、極めて静かな足音が抜けてゆく。彼は抜き身の太刀へと矛を交わせ、名乗りを上げる。
「ワシはひょうずの長、名は田道間諸杵(もろき)。お前、菅原氏の者では無いな、名乗れ」
「先の歌が利かぬとは。ならば聞け、我こそは肥前国有田郷の国人、名は後藤高宗!」
互いに尋常な立ち会いではない。それ以上の口上は無く、切り結んだままの刃を一旦放してから、また二人は火花を散らす。それを以て数人のひょうずが解き放たれるが、彼らは動けぬ同族を守るために防戦一方。
対する為朝の側には、夜叉丸だけが残っている。
「ヤマノメ、やはり来てしまったのか」
彼は両手の拳を向け、弾指の構えを取る。ヤマノメはそれにもかかずらわず、歩み寄る。
「どけ、オレが用があるのは為朝だけだ」
「俺とて退けん!」
至近で弾指の速射が始まり、その分だけ礫が飛ぶ。数町先の物を精密に射貫くそれはしかし、逆に近い物を撃つには向かなかった。腕をかざして目を守るヤマノメを数発かすっただけ。急速に迫るヤマノメに、備えるのすらままならない。
「避けろ夜叉丸!」
至近でも遠距離でもお構いなしの強弓が、ヤマノメに指向する。すぐさま放たれた矢は、かざしたヤマノメの右腕を貫き、耳を切り裂きながら飛び去る。
瘴気を用いるか。ヤマノメは一瞬そう考えて、すぐに止める。
(田道間様達も居る、ダメだ)
その思惟に夜叉丸の声が覆い被さる。
「ヤマノメ。今からでも遅くない、河童達と共に若大将に味方せよ」
「断る! お前こそ何故、為朝にそこまで肩入れする」
「俺ももう、後悔したくないのだ!」
かつて義親が事を起こした折の田道間と同じだ。自身ではいくら味方したくとも、それを叶えられずに今も負い目を抱き続ける彼と。
「後悔したくないのなら、今は為朝を退かせろ」
射貫かれた腕を庇わず、ヤマノメは拳を作って迫る。
「それこそ何故か?!」
「童に、日の本を覆すなど、出来るか……!」
義親にも万寿にも、それは為せなかったのだから。
その思いはしかし彼らに通じず、夜叉丸は為朝からの射線にあえて割り込む。
「若大将、ここは拙僧が頂きますぞ」
『大通連』
彼がそう号すると、いつの間にか現れていた二口の直剣が各個自在に回転し、飛翔する。
「西国(さいごく)の陰陽兵器より伝えられし、鈴鹿の魔鍛冶の方術よ。かの者も、義親公に呼応し檄を飛ばした一人であったがなぁ!」
朝廷や魔縁の者(※2)、その上に立つ天つ神々や天部。それに対峙しようとする者がここまで多いとは。だがヤマノメの心も、それ以上は揺らがない。
左右から同時に迫る刃を、両腕を立てて凌ぐ。直剣は中程で折れ、いずれも地に落ちた。代わりに、ヤマノメの両腕にまた新たな傷が刻まれる。それも肉を裂くには至ってないが。
自慢の術が看破されたのに驚愕し、動きを止める夜叉丸。ヤマノメは間髪入れずに追撃。彼の身体の真芯を打ち抜き、川向こうまで殴り飛ばした。
「やはり、万寿の眷属か」
「アイツからは聞かなかったのか?」
夜叉丸が飛んでいった方を、ヤマノメは指し示す。
「いや、奴はお前に惚れていたようだからな。だから俺には言わなかったのだろう」
冗談でも本当でもそれは御免被るとヤマノメは眉をひそめながら、為朝に言い渡す。
「ではオレからは、お前が惚れた奴からの言付けだ。兵を退き、尋常に京へ戻れ」
「それが万寿の望みだと言うのか」
「……ああ!」
それが全てでは無い。だが、今はそれだけ。
「断る。俺は鬼となってでも、義親公の、万寿の無念を晴らさねばならんのだ」
為朝の答えに、ヤマノメは未だかつて無い怒りを覚える。
「やはり、お前はただの童だ。好いた女や好いてくれる女の思いも分からぬ、ただのガキだ。何が鬼に成る、だ。それに目的のためならどんな嘘っぱちものたまう奴がなれるのなんて精々、ホラばかり吐き出す小鬼だけだ!」
駆け出し、腕の傷に構わず拳を振りかざす。為朝は十間も無い間合いを詰めようとするヤマノメに対し、騎乗のまま一瞬で二矢を放つ。弓勢は先に龍蛇を射たのにも劣らない。
殆ど時間差無く飛来する矢を、ヤマノメは続けざまに叩き落とした。
「こんな弓にあいつがやられたなんて、なぁ!」
もう矢を番える暇は無い。しかし為朝は手にした弓を叩き付けて退け、更に対岸からもそれを助けて光弾が飛来する。
「夜叉丸! 俺は構わん、兵主部と戦っている奴らを助けろ!」
動きに一分の無駄も生じさせず黒漆拵の鞘から太刀が抜かれ、切っ先がヤマノメに向く。
「今は吠丸、かつての蜘蛛切――」
以前、彼の郎党季遠が大蜘蛛に振るった際は、最期の刺突が通っただけであった。
「いかに勿怪でも、徒手空拳の女が相手では剣筋も鈍りそうだ。お前も万寿の様になれ」
彼の言葉の中には、さきのヤマノメの怒りへの対抗心もあろう。だが、
「それは出来ないな」
言葉通り、今以て己を大蜘蛛と化す方法を知らないのだ。だが為朝の解釈は異なる。
「それも万寿の遺言故か。見くびるな」
巨体の馬を自在に操り、太刀を振るう彼を前に、そんな余裕は一切無い。
せめて馬を。だが殴り倒すには余りに大きすぎる。
斬撃を一度二度とかわしてみるが、それ以上は近づくのもままならない。後ろに回れば馬の後ろ足に阻まれ、左右に入れば太刀が襲い来る。だが正面は――
(この位置なら、瘴気を)
潜り込み、刃か馬の頭が振り下ろされる直前に、妖気と共に瘴気を発露。さしもの巨馬も覿面(てきめん)にあおの影響を受けてよろめき、その場にどうと倒れ込む。
為朝も投げ出されたが、ヤマノメはその姿を見失ってしまった。いくら霧が濃いとは言え、そこは十分視界が開けているのに。
馬の陰から白刃が横薙ぎに迫る。ヤマノメの僅かな隙を、為朝は見逃さなかったのだ。
腰に迫る逆胴、彼の膂力なら人の身体など上下に分断してしまえる。間合いを見極め、飛び退るヤマノメ。だが馬手で振られた刃は想像よりも伸び、切っ先はヤマノメを捉えた。
衣が裂け、傷口から血が伝う。しかし傷は、それ以上の物ではなかった。
「どうした、それがその鈍刀(なまくら)の限界か」
その剣筋、人間相手には十分な深さであったろうが、土蜘蛛相手には全く足りなかった。そもこれが蜘蛛切なる霊剣であったなら、並の太刀以上の驚異となったはずであるのに。
「俺は清和帝の裔、源氏の男子だ。吠丸よ、俺の血に応え、唸れ!」
半歩踏み込み、逆袈裟に斬りかかる為朝。ヤマノメは矢傷を受けた右腕で真っ向から受け止める。
「鬼になると言ったり、天子様とやらの末裔であるのを誇ったり、本当に忙しい奴だな。だから万寿は、今のお前に失望したんだ!」
腕は太刀を絡め取り、弾き、左の拳が振り抜かれた。
数と地の利に勝るひょうずの包囲と、屈強な兵達の中心で、ひとつの決着がついた。
「どうだ、まだ兵を退かないつもりか」
「……俺は、この日の本を、変える。ここで、敗れるなど」
顎が砕けたのか、為朝は億劫そうに言葉を吐き出す。
殴り飛ばされても手から離さなかった太刀を頼りに立ち上がると、切っ先を向け直す。しかし大鎧の重量にすら負けたのか、また膝から崩れ落ちそうになる。その彼の肩を、川向こうから戻ってきた夜叉丸が支えた。
「若大将。ここは諦めましょうや」
「帰れるか、戻れる、ものか。ここに、朝廷を立て、天道を、得るのだ。このまま、おめおめと、みやこに帰ったら、俺の時は、未来は、そこで止まる」
為朝以上に顔を腫らした夜叉丸は、首を振りながら諫める。
「止まらせやしませんぜ。この夜叉丸もお供しますから」
これでいいのだろうと、夜叉丸の目がヤマノメの方へ向く。
「田道間様!」
「後藤の大将!」
双方の矛を下げさせ、ヤマノメは川上側に道を開ける。
「俺は、諦めん……」
「ああ。お前が真に事を為そうという時には、オレも鎮西で待っていよう」
彼が望むなら、敵にも味方にもなろう。ヤマノメに自覚は無かったが、これは万寿の後を継ぐという決意でもあった。
いつか来たる人間の英雄の為に、己の時もしばし止めようと。
「ヤマノメよ。若大将のついででよい、拙僧のことも待っていてくれぬか」
「さて、な」
親しく語らいたいと思った試しは一度も無い相手であるが、今は素っ気なくも、確かに肯定の意思を返す。
再び隊列を整え、退いてゆく為朝ら一団が霧の向こうへ消えるまで、ヤマノメとひょうず達は彼らの背を見守り続けた。
∴
襤褸に身を包み、その下に直垂を纏った一人の旅人が、鎮西より旅立つ。
人々の営みが広がり、地方で侍の力も増しつつある中、安住の地を探すため。
潮流に乗り北は蝦夷から、陸奥へ上り坂東へと。
彼女の目的地はまだ、無い。
* * *
平安末期、鎮西八郎為朝と称した豪傑が居た。
彼は鎮西での大立ち回りを後ろにして京へ帰洛。後に、父に子に、兄と弟にと分かれて相争う戦に参じ、奮戦するも破れ、伊豆大島へ配流となる。
そこでも彼は戦い続け、一説には伊豆七島に棲んだという鬼達を組み敷き、大島では悪徳を極めた代官すらも平らげるなど、その勇壮さは京に在した時以上であった。
だがやがて、国衙の命を受けた伊豆国の豪族、狩野茂光(かのうもちみつ)に攻め寄せられると、その強弓を以て数百人を海の藻屑としながらも、自ら腹を裂いて果てたという。
そこから少し時を下り、肥後の土蜘蛛達の間には「日向国で為朝を見た」という噂話が流れ始めた。その裏付けの様に、彼と白縫姫の交流は尽きなかったと伝えられている。
また為朝には、鎮西よりもはるか南の琉球で王朝を築いたとの伝説もある。
彼は人として死んだのか、鬼になったのか。万寿の願いはどこまで叶ったのか。
ヤマノメのそれらの記憶は、一族丸ごと新たな地に身を寄せた新天地で暮らすうち、多くの思いと共に朧な認識の中に沈んでいった。
* * *
ヤマメは奈落への落下を止め、噴き上がる怨霊達の生暖かい息吹を背に受け、風穴の先を目指していた。
自分が待ち続けた人間の英雄は、とうの昔に死んだのだろう。今の怨霊達の中には、彼がいたのかも知れない。
噴き上がった怨霊に隠れて瞬いた燐光は、徐々に大きく、明るくなっている。
そこに天道は無い、ここからは天蓋にも届かない。
その見通せぬ空から、星が降って来た。
楽園からも半ば切り離されたこの地の時が、黒谷ヤマメの今に、刻まれ始めた。
第10話注釈
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1 八龍:源氏八領は源氏に伝わる八領の鎧。。為朝は身体が大きすぎたため、模造品を使った。
※2 魔縁:仏教用語。魔界に堕ちた者、天狗を指す言葉である場合もある。
※※本章『火の国のヤマノメ』は、一部『椿説弓張月』(作:滝沢馬琴)を元ネタにしました。
※※※その他、細々としたネタは以下の通り。
・万寿:肥前国黒髪山で、為朝により大蛇から救われた女性の名から。
・ヤマノメ:土蜘蛛としては大山田女・狭山田女、耶蘇女、あるいは邪馬台国から連想。または、為朝が大蛇退治の際、誤って首をはねてしまった勇敢な犬『山雄(やまお)』からも。
・ひょうず:ひょうすべ、兵主部とも。由緒については『兵主神』と共に『アメノヒボコ』に連なっているかもと妄想してます。
・夜叉丸:為朝の手下であった八丁礫の喜平治と、伊豆七島の伝説に登場し、為朝を琉球に導いたとされる鬼夜叉なる人物とのニコイチ。(いずれも英彦山とは関係ありません、多分)
・吠丸:これを為朝が所持していたという史実はありません。為朝の妹である鳥居禅尼の婚儀の際、熊野別当家に納められたとされ、後に『薄緑(うすみどり)』と改名して義経の佩刀となっています。
・白縫姫:為朝の初の妻。彼女が飼っていた老猿が侍女を殺し、攫われた彼女を為朝が取り返したという、弓張月のエピソードから色々と。(元は矢ではなく鶴を放ったとか書いてありますが)
・燃石での精錬:尺と知識とテンポの関係で作中の表現は相当に適当ですが、瀝青炭を原料にコークスを作り、リモナイト(褐鉄鉱)を用いた高炉精錬を想定しました。そんな物が平安時代にあったらオーパーツです。作中にもねじ込みましたが、これだと含有物の関係で玉鋼は出来ないらしいです。
・淵の大蜘蛛:南阿蘇の恐ヶ淵の伝説から。『浄蓮の滝の女郎蜘蛛』に似た伝説ですが、浄蓮の滝の蜘蛛が美女なのに対して、こちらは婆蜘蛛ということだそうで。
・巫女ヤマメさん:下さい。
火の国のヤマノメ 第10話
ヤマノメが為朝との決戦に合流するとの旨は、田道間を通じてその日の内にひょうず達に伝えられ、先に彼が言った通りに合意を得られた。
「オレは万寿のことを恩に着せる気は無いし、あいつにだってそんな考えは無かったろう。オレからすれば、オレや他の土蜘蛛には協力を仰がず、一人で勝手に事を進めたのはあいつだ。ひょうずを手勢に使おうと考えていたのかも知れないんだ」
これも傍から見たればこその考え。ヤマノメは万寿の思いを、彼女が如何なる考えで土蜘蛛ではなくひょうず達に協力を仰いだのかを知りながらも言った。
「万寿御前はそれを望んでいたか? お主らは?」
「流石は田道間様。それもお見通しだったか」
彼女も当初は、妖に、勿怪になったのを嘆いていたであろうが、最期には誇っていた。土蜘蛛である自身を。
ならば他の土蜘蛛も同じ。今のヤマノメの様に、己の由緒を知らぬ者ですらそうなのだ。天道や所謂“お上”への反骨や恨みの心は、今も土蜘蛛が共通して抱くもの。だが、人間の力を借りてまで世を覆そうなどとは考えない。
「かと言って、あいつが田道間様達を低く見ていた訳でもない」
「そう。あの方は、ワシらと義親公の思いを同時に汲もうとして下さっただけだ」
そして万寿自身の思い。敗残者たる恨みを晴らそうとしたのではなく、巫女王としての役割を果たそうとしたのだ。
「それにしても不安です。為朝の如き童に国を覆せますかな」
童。彼はまだ、ただの悪童にすぎない。祖父の大業を今こそ為さんとするのも、鎮西に己を追いやった父か、兄達を見返すためでしかないのだ。その未熟な心がいずれ、ずば抜けた武力と並んだ時こそ、万寿が期待した義親の嫡孫、鎮西総追捕使為朝となる。
「信じるしかあるまい。そのためにはまず、我らが勝たねばならぬ。たとえ今、為朝が鎮西を平定してもいずれは、来たる官軍に負ける」
今行く手を挫かねば、彼は祖父義親と同じ末路を迎えてしまう。
「それに龍蛇相手となれば、負けてもなんとか面目は立ちますか」
それもそうだと、田道間は意図の外であったヤマノメの言葉に同意し、横たわる龍蛇の背を何度か叩く。中はひょうずが入れるように作られているが、ただの空洞の様な反響は返さず、その分洞穴内で金属音が響く。
当初短かった胴は、今や龍と呼ぶにも相応しい十丈を上回る全長となり、特段の意匠も施されていなかった頭部も、恐ろしげな毒蛇の物になっている。
「始めは奴の手勢に、せいぜいが豊後の家遠の軍が加わるだけかと思っていたのでな。今国衙に在する兵ならば、それで十分間に合うはずだからな」
しかしそこに肥後の忠国や、併合した肥前諸氏の軍が合流する恐れが出てきたことから、この龍蛇を当初より強大にするに至ったのだと田道間は言った。
「しかし、これだけの『鎧』をよくもまあ」
彼は、人の面なら覆ってしまえるほどの鱗を持ち上げながら答える。
「言っただろう。燃石など扱えず、僅かな量に留まるが、ワシらも“これ”を用いると」
銅やスズ、鉄に水銀なども。金気を忌避する他の水界のモノ達と一線を画すのが、彼ら。
「そうだ燃石を使った精錬ですが、一つ問題があるんだ」
「瘴気を除く以外にまだ何かあるのか」
「またそれなのです。どんなに瘴気を除けても、これは完全に抜ける訳じゃないみたいでな。どうやってみても玉鋼が出来ないのです」
砂鉄や重く硬い木炭を用い、蹈鞴(たたら)によって僅かに取り出せるのが玉鋼。元は土蜘蛛も生産していたが、土蜘蛛にとっては使い道の無い物となって久しかった。
「それこそは、今もワシ等の領分だな。新しい業も便利なだけでは無いか」
もしかしたら万寿も、かつての技を用いて義親にこれを提供していたのかも知れない。
(やはりオレは、お前に成り得ないみたいだぞ)
だから彼女は託してくれたのだろう、今のヤマノメに。
そんな感慨に浸るヤマノメと、それを見守る田道間に、別のひょうず二人が足音を響かせながら駆け寄る。
「田道間様、一大事です!」
(為朝か? だとしたら随分早いな)
忠国の館での出来事からは、まだひと月ほどしか経っていない。いくら阿蘇の忠国が協力したとしても、敵対する土豪の制圧がせいぜい。太宰府に寄せられるほど、兵を掌握出来たとは考えにくい。
そのひょうずが耳打ちしようとするのを田道間が咎め、報告はヤマノメにももたらされる。それはやはり、為朝の来襲を告げるものであった。
「肥前の原田との戦も終わったばかりでまさかとお思いでしょうが、為朝は今、元からの手勢だけを動かしている模様でして」
ならば人心掌握の手間は無いし、大軍を動かす時の様な種々の準備も省略でき、小回りも利く。だがそれで太宰府を落とすなど叶うものか。
「奴の手勢はたかだか二十騎程度のはず、いや……」
豊後勢を後詰めとして配するか、もしかしたら海賊を用いて海路より寄せさせるのかも知れない。現在、陸路を北上しつつある為朝と率いる手勢こそ、後詰めとも考えられる。
「勝てますかな」
「尋常であれば、な」
阿蘇からの兵を想定しての十分な備えがあっても、彼相手では少しの油断も許されない。
だが、いずれにせよやるしかないのだと、ヤマノメは身を震わせながら、幾度めかの決意を己に確認した。
∴
背振の山脈の南端。基肄(きい)の山城と付随する水城を避け、武士の一団が筑後川支流の川沿いを北上する。
僅かに二十騎、徒武者を含めても五十人足らずの兵であればこそ、それらを避けて通るのも叶う。一団の将、鎮西八郎為朝の策の一つはそれであった。
「御曹司。霧が出て来ましたが、このまま進むので?」
「むしろ都合がいい、このまま進むぞ」
重代の重宝、源氏八領が一種である『八龍(はちりよう)(※1)』を模した白糸威(しろいとおどし)の大鎧を纏い、九尺もある重藤の弓を担いだ為朝が命じる。跨がる馬は先に平らげた菊池から召し上げた、大陸北方の血を色濃く残す巨体の駿馬。佩刀は、これも源氏重代の太刀、吠丸。
武家の惣領の御曹司に相応しい出で立ちの彼が堂々と号するのに、手勢らは粛々と従う。
その巨馬と大丈夫に並んで歩く一人の法師が、先の郎党の別の懸念を持って進言する。
「若大将、ここはヤバいかも知れません」
「ヤバい?」
「危うし事が待っているやもと。我が山には、義親公が太宰府に兵を寄せようとした際、それを阻んだ勿怪の記録が残っております」
「夜叉丸よ。よもやそれは、兵主部の事か?」
彼の進言を側で聞いていた、別の壮年の武者が問う。
「お、後藤の大将はご存じなのか」
「我らの本所の肥前にも伝わるモノだ。それが不安ならしかし、御曹司も安心なされよ。我には策があります」
「うむ。夜叉丸、高宗(たかむね)はこう言っているが、どうか?」
「ならば、よろしいでしょうが……」
そう言いながらも夜叉丸は、周囲に満ちる不穏な気配を察知している。霧はより濃密になり、二十間先も見通せぬ程。彼はその霧の先にある気配の大元を認めた。
「若大将。どうやら敵は、国衙やひょうすべだけではないようですぜ」
乳色の大気に、尋常でなく巨大な影が映し出されていた。
ひたりひたりと、濡れた静かな足音が、川沿いを行く為朝の一団を包囲しつつある。彼らは正面に現れた龍蛇の影に気を取られ、それに気づきもしていない。
「ヤマノメよ、他は我らが引き受ける。お主は為朝のみを狙え」
「承知しました」
だがまだ早い。周囲には為朝を守るように騎馬武者が展開し、龍蛇を迎え撃とうと後方に居た徒武者も前進を始めている。恐れる事無くあの大蛇に立ち向かおうというのだ、ただの侍なら蛮勇と評されるところ、為朝が誇る手勢ではそうとも言いがたい。
霧の向こうの龍蛇が重々しく鎌首をもたげる。
身の丈およそ三丈にも上るその姿に怯む事無く――
「放てぇ!」
馬上の武者が一斉に矢を放つと同時に、徒武者が薙刀を手に鬨の声を上げ、斬りかかる。
しかし如何に強弓を以てしても、青銅の鱗に鎧われた大蛇を貫く事あたわず、薙刀の刃も表面に疵を刻むだけ。
そこに大蛇の頭が鉄槌として振り下ろされ、また前進せんと蛇行すると、肉薄していた徒武者は潰されるか轢かれるか、あるいは弾き飛ばされた。
さしもの彼らも驚くが、為朝が再び鎌首をもたげた大蛇に向かって弓を引くのを見て、落ち着きを取り戻している。
そこから先は、ヤマノメ達が驚く番であった。
引き絞るのは八人張りの弓。引き分けるには相応の力と共に技量も必要とされるが、為朝は極めて滑らかにそれを為している。
短刀を交差させた様な巨大な雁股の矢が放たれると、風を巻き、霧を貫きながら飛翔する。それも最初から分かっていたかのように、機巧の大蛇の痛点に向けて。
ヤマノメも一瞬肝を冷やすが、そこを守るのは特に頑強な鉄の鱗。空前の剛弓から放たれたその矢すらも弾いて見せた。
為朝は表情も変えず、視線も乱さず、箙(えびら)から速やかに矢を抜き、番える。
一瞬だけ並んだ腕の異様さに、人外であるヤマノメや、田道間ですら驚きを露わにする。
「あの腕はなんだ!?」
弓手が馬手より明らかに長い。拳一つ分ほどであるが、その手は八人張りの強弓をやはり軽々と引き分け、達人の限界すらも超えて引き絞る。
番えるのは、鑿の如く分厚く広い平根の矢。
「いかん!」
田道間が潜むのを止め、手にした矛を投げつけようとした直前、矢は放たれた。
第一射よりも低い音が大気を揺らし、大蛇の喉元に食らいつく。鉄の鱗を貫かれ、背側の青銅の鱗も散らして大蛇は地に伏した。
「どうか!」
「し、死んでおるようです!」
残心を取りながら為朝が叫ぶと、前進していた徒武者が駆け寄り、検分して言った。
それを受けて為朝ら騎馬武者は大蛇の側に寄る。突如現れた怪物を倒したのには安堵した様子であるが、彼らの考える戦場はまだまだ先。少しの油断も見られない。
為朝は、自ら貫いた鉄の鱗を剥ぎ取ると、近くの騎馬武者に預ける。だが馬が重みに負け、膝をついてしまった。
「御曹司。これは、無理です」
「まあ、こんな物はどうでもいいか。しかし」
「若大将!」
「分かっている!」
剥がされた鱗の内側から、蓑を背負って矛を構えた男が躍り出る。彼はすぐに為朝に切り伏せられたが、それを皮切りに大蛇の中から、川や岸辺の森からも、蓑を纏い矛を携えた男達が現れ、包囲する。
数は為朝達の倍、一人一人の力も人間を上回る。やはり尋常であれば負ける理由は無い。
「これがひょうずですぞ!」
叫びながら夜叉丸が次々と礫を放つが、射撃は目に見える範囲に留まる。
「各々方! 辺りの敵を散らしつつ戦列を整えよ! 亥の方へ向かって進め!」
為朝の号令に従い、徒武者と騎馬が速やかに体勢を立て直す。同時に従わなかった者には、容赦なく矢が放たれる。そして射撃は、的を違えなかった。
「これが為朝の軍か」
寡兵ながら恐れを見せぬ整斉とした動き。だがそれも仇となる。相対的に後方に下がった為朝を兵達から切り離そうと、ひょうずも側面から戦列を組んで前衛を襲う。
前衛で矛と薙刀が火花を散らす後ろから、ついにヤマノメ達が躍りかかる。
「為朝ぉ!」
しかしそれを阻まんと一騎が跳ね飛び、立ち塞がる。
「面妖な賊共が!」
壮年の武者が鋭く太刀を振り払い、ヤマノメを切りつけた。弾かれると同時に衣が裂かれ、脇腹に傷を刻まれるが、皮より頑強な肉はその刃を通さない。
腰から落ちたヤマノメに続いて、また数人のひょうずが前に出る。それにも壮年の武者は怖じ気づかず、堂々と迎え撃ちながら、朗々と詠い上げる。
「兵主部よ、約束せしを忘るるな、かわたつをのこ、われもすがわら」
それを聞いたひょうず達は一斉に膝を着き、頭を垂れる。
「道真公が残した兵主部調伏の歌です。さあ、前衛を――」
ひれ伏したひょうず達や、起き上がろうとするヤマノメの側を、極めて静かな足音が抜けてゆく。彼は抜き身の太刀へと矛を交わせ、名乗りを上げる。
「ワシはひょうずの長、名は田道間諸杵(もろき)。お前、菅原氏の者では無いな、名乗れ」
「先の歌が利かぬとは。ならば聞け、我こそは肥前国有田郷の国人、名は後藤高宗!」
互いに尋常な立ち会いではない。それ以上の口上は無く、切り結んだままの刃を一旦放してから、また二人は火花を散らす。それを以て数人のひょうずが解き放たれるが、彼らは動けぬ同族を守るために防戦一方。
対する為朝の側には、夜叉丸だけが残っている。
「ヤマノメ、やはり来てしまったのか」
彼は両手の拳を向け、弾指の構えを取る。ヤマノメはそれにもかかずらわず、歩み寄る。
「どけ、オレが用があるのは為朝だけだ」
「俺とて退けん!」
至近で弾指の速射が始まり、その分だけ礫が飛ぶ。数町先の物を精密に射貫くそれはしかし、逆に近い物を撃つには向かなかった。腕をかざして目を守るヤマノメを数発かすっただけ。急速に迫るヤマノメに、備えるのすらままならない。
「避けろ夜叉丸!」
至近でも遠距離でもお構いなしの強弓が、ヤマノメに指向する。すぐさま放たれた矢は、かざしたヤマノメの右腕を貫き、耳を切り裂きながら飛び去る。
瘴気を用いるか。ヤマノメは一瞬そう考えて、すぐに止める。
(田道間様達も居る、ダメだ)
その思惟に夜叉丸の声が覆い被さる。
「ヤマノメ。今からでも遅くない、河童達と共に若大将に味方せよ」
「断る! お前こそ何故、為朝にそこまで肩入れする」
「俺ももう、後悔したくないのだ!」
かつて義親が事を起こした折の田道間と同じだ。自身ではいくら味方したくとも、それを叶えられずに今も負い目を抱き続ける彼と。
「後悔したくないのなら、今は為朝を退かせろ」
射貫かれた腕を庇わず、ヤマノメは拳を作って迫る。
「それこそ何故か?!」
「童に、日の本を覆すなど、出来るか……!」
義親にも万寿にも、それは為せなかったのだから。
その思いはしかし彼らに通じず、夜叉丸は為朝からの射線にあえて割り込む。
「若大将、ここは拙僧が頂きますぞ」
『大通連』
彼がそう号すると、いつの間にか現れていた二口の直剣が各個自在に回転し、飛翔する。
「西国(さいごく)の陰陽兵器より伝えられし、鈴鹿の魔鍛冶の方術よ。かの者も、義親公に呼応し檄を飛ばした一人であったがなぁ!」
朝廷や魔縁の者(※2)、その上に立つ天つ神々や天部。それに対峙しようとする者がここまで多いとは。だがヤマノメの心も、それ以上は揺らがない。
左右から同時に迫る刃を、両腕を立てて凌ぐ。直剣は中程で折れ、いずれも地に落ちた。代わりに、ヤマノメの両腕にまた新たな傷が刻まれる。それも肉を裂くには至ってないが。
自慢の術が看破されたのに驚愕し、動きを止める夜叉丸。ヤマノメは間髪入れずに追撃。彼の身体の真芯を打ち抜き、川向こうまで殴り飛ばした。
「やはり、万寿の眷属か」
「アイツからは聞かなかったのか?」
夜叉丸が飛んでいった方を、ヤマノメは指し示す。
「いや、奴はお前に惚れていたようだからな。だから俺には言わなかったのだろう」
冗談でも本当でもそれは御免被るとヤマノメは眉をひそめながら、為朝に言い渡す。
「ではオレからは、お前が惚れた奴からの言付けだ。兵を退き、尋常に京へ戻れ」
「それが万寿の望みだと言うのか」
「……ああ!」
それが全てでは無い。だが、今はそれだけ。
「断る。俺は鬼となってでも、義親公の、万寿の無念を晴らさねばならんのだ」
為朝の答えに、ヤマノメは未だかつて無い怒りを覚える。
「やはり、お前はただの童だ。好いた女や好いてくれる女の思いも分からぬ、ただのガキだ。何が鬼に成る、だ。それに目的のためならどんな嘘っぱちものたまう奴がなれるのなんて精々、ホラばかり吐き出す小鬼だけだ!」
駆け出し、腕の傷に構わず拳を振りかざす。為朝は十間も無い間合いを詰めようとするヤマノメに対し、騎乗のまま一瞬で二矢を放つ。弓勢は先に龍蛇を射たのにも劣らない。
殆ど時間差無く飛来する矢を、ヤマノメは続けざまに叩き落とした。
「こんな弓にあいつがやられたなんて、なぁ!」
もう矢を番える暇は無い。しかし為朝は手にした弓を叩き付けて退け、更に対岸からもそれを助けて光弾が飛来する。
「夜叉丸! 俺は構わん、兵主部と戦っている奴らを助けろ!」
動きに一分の無駄も生じさせず黒漆拵の鞘から太刀が抜かれ、切っ先がヤマノメに向く。
「今は吠丸、かつての蜘蛛切――」
以前、彼の郎党季遠が大蜘蛛に振るった際は、最期の刺突が通っただけであった。
「いかに勿怪でも、徒手空拳の女が相手では剣筋も鈍りそうだ。お前も万寿の様になれ」
彼の言葉の中には、さきのヤマノメの怒りへの対抗心もあろう。だが、
「それは出来ないな」
言葉通り、今以て己を大蜘蛛と化す方法を知らないのだ。だが為朝の解釈は異なる。
「それも万寿の遺言故か。見くびるな」
巨体の馬を自在に操り、太刀を振るう彼を前に、そんな余裕は一切無い。
せめて馬を。だが殴り倒すには余りに大きすぎる。
斬撃を一度二度とかわしてみるが、それ以上は近づくのもままならない。後ろに回れば馬の後ろ足に阻まれ、左右に入れば太刀が襲い来る。だが正面は――
(この位置なら、瘴気を)
潜り込み、刃か馬の頭が振り下ろされる直前に、妖気と共に瘴気を発露。さしもの巨馬も覿面(てきめん)にあおの影響を受けてよろめき、その場にどうと倒れ込む。
為朝も投げ出されたが、ヤマノメはその姿を見失ってしまった。いくら霧が濃いとは言え、そこは十分視界が開けているのに。
馬の陰から白刃が横薙ぎに迫る。ヤマノメの僅かな隙を、為朝は見逃さなかったのだ。
腰に迫る逆胴、彼の膂力なら人の身体など上下に分断してしまえる。間合いを見極め、飛び退るヤマノメ。だが馬手で振られた刃は想像よりも伸び、切っ先はヤマノメを捉えた。
衣が裂け、傷口から血が伝う。しかし傷は、それ以上の物ではなかった。
「どうした、それがその鈍刀(なまくら)の限界か」
その剣筋、人間相手には十分な深さであったろうが、土蜘蛛相手には全く足りなかった。そもこれが蜘蛛切なる霊剣であったなら、並の太刀以上の驚異となったはずであるのに。
「俺は清和帝の裔、源氏の男子だ。吠丸よ、俺の血に応え、唸れ!」
半歩踏み込み、逆袈裟に斬りかかる為朝。ヤマノメは矢傷を受けた右腕で真っ向から受け止める。
「鬼になると言ったり、天子様とやらの末裔であるのを誇ったり、本当に忙しい奴だな。だから万寿は、今のお前に失望したんだ!」
腕は太刀を絡め取り、弾き、左の拳が振り抜かれた。
数と地の利に勝るひょうずの包囲と、屈強な兵達の中心で、ひとつの決着がついた。
「どうだ、まだ兵を退かないつもりか」
「……俺は、この日の本を、変える。ここで、敗れるなど」
顎が砕けたのか、為朝は億劫そうに言葉を吐き出す。
殴り飛ばされても手から離さなかった太刀を頼りに立ち上がると、切っ先を向け直す。しかし大鎧の重量にすら負けたのか、また膝から崩れ落ちそうになる。その彼の肩を、川向こうから戻ってきた夜叉丸が支えた。
「若大将。ここは諦めましょうや」
「帰れるか、戻れる、ものか。ここに、朝廷を立て、天道を、得るのだ。このまま、おめおめと、みやこに帰ったら、俺の時は、未来は、そこで止まる」
為朝以上に顔を腫らした夜叉丸は、首を振りながら諫める。
「止まらせやしませんぜ。この夜叉丸もお供しますから」
これでいいのだろうと、夜叉丸の目がヤマノメの方へ向く。
「田道間様!」
「後藤の大将!」
双方の矛を下げさせ、ヤマノメは川上側に道を開ける。
「俺は、諦めん……」
「ああ。お前が真に事を為そうという時には、オレも鎮西で待っていよう」
彼が望むなら、敵にも味方にもなろう。ヤマノメに自覚は無かったが、これは万寿の後を継ぐという決意でもあった。
いつか来たる人間の英雄の為に、己の時もしばし止めようと。
「ヤマノメよ。若大将のついででよい、拙僧のことも待っていてくれぬか」
「さて、な」
親しく語らいたいと思った試しは一度も無い相手であるが、今は素っ気なくも、確かに肯定の意思を返す。
再び隊列を整え、退いてゆく為朝ら一団が霧の向こうへ消えるまで、ヤマノメとひょうず達は彼らの背を見守り続けた。
∴
襤褸に身を包み、その下に直垂を纏った一人の旅人が、鎮西より旅立つ。
人々の営みが広がり、地方で侍の力も増しつつある中、安住の地を探すため。
潮流に乗り北は蝦夷から、陸奥へ上り坂東へと。
彼女の目的地はまだ、無い。
* * *
平安末期、鎮西八郎為朝と称した豪傑が居た。
彼は鎮西での大立ち回りを後ろにして京へ帰洛。後に、父に子に、兄と弟にと分かれて相争う戦に参じ、奮戦するも破れ、伊豆大島へ配流となる。
そこでも彼は戦い続け、一説には伊豆七島に棲んだという鬼達を組み敷き、大島では悪徳を極めた代官すらも平らげるなど、その勇壮さは京に在した時以上であった。
だがやがて、国衙の命を受けた伊豆国の豪族、狩野茂光(かのうもちみつ)に攻め寄せられると、その強弓を以て数百人を海の藻屑としながらも、自ら腹を裂いて果てたという。
そこから少し時を下り、肥後の土蜘蛛達の間には「日向国で為朝を見た」という噂話が流れ始めた。その裏付けの様に、彼と白縫姫の交流は尽きなかったと伝えられている。
また為朝には、鎮西よりもはるか南の琉球で王朝を築いたとの伝説もある。
彼は人として死んだのか、鬼になったのか。万寿の願いはどこまで叶ったのか。
ヤマノメのそれらの記憶は、一族丸ごと新たな地に身を寄せた新天地で暮らすうち、多くの思いと共に朧な認識の中に沈んでいった。
* * *
ヤマメは奈落への落下を止め、噴き上がる怨霊達の生暖かい息吹を背に受け、風穴の先を目指していた。
自分が待ち続けた人間の英雄は、とうの昔に死んだのだろう。今の怨霊達の中には、彼がいたのかも知れない。
噴き上がった怨霊に隠れて瞬いた燐光は、徐々に大きく、明るくなっている。
そこに天道は無い、ここからは天蓋にも届かない。
その見通せぬ空から、星が降って来た。
楽園からも半ば切り離されたこの地の時が、黒谷ヤマメの今に、刻まれ始めた。
第10話注釈
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1 八龍:源氏八領は源氏に伝わる八領の鎧。。為朝は身体が大きすぎたため、模造品を使った。
※2 魔縁:仏教用語。魔界に堕ちた者、天狗を指す言葉である場合もある。
※※本章『火の国のヤマノメ』は、一部『椿説弓張月』(作:滝沢馬琴)を元ネタにしました。
※※※その他、細々としたネタは以下の通り。
・万寿:肥前国黒髪山で、為朝により大蛇から救われた女性の名から。
・ヤマノメ:土蜘蛛としては大山田女・狭山田女、耶蘇女、あるいは邪馬台国から連想。または、為朝が大蛇退治の際、誤って首をはねてしまった勇敢な犬『山雄(やまお)』からも。
・ひょうず:ひょうすべ、兵主部とも。由緒については『兵主神』と共に『アメノヒボコ』に連なっているかもと妄想してます。
・夜叉丸:為朝の手下であった八丁礫の喜平治と、伊豆七島の伝説に登場し、為朝を琉球に導いたとされる鬼夜叉なる人物とのニコイチ。(いずれも英彦山とは関係ありません、多分)
・吠丸:これを為朝が所持していたという史実はありません。為朝の妹である鳥居禅尼の婚儀の際、熊野別当家に納められたとされ、後に『薄緑(うすみどり)』と改名して義経の佩刀となっています。
・白縫姫:為朝の初の妻。彼女が飼っていた老猿が侍女を殺し、攫われた彼女を為朝が取り返したという、弓張月のエピソードから色々と。(元は矢ではなく鶴を放ったとか書いてありますが)
・燃石での精錬:尺と知識とテンポの関係で作中の表現は相当に適当ですが、瀝青炭を原料にコークスを作り、リモナイト(褐鉄鉱)を用いた高炉精錬を想定しました。そんな物が平安時代にあったらオーパーツです。作中にもねじ込みましたが、これだと含有物の関係で玉鋼は出来ないらしいです。
・淵の大蜘蛛:南阿蘇の恐ヶ淵の伝説から。『浄蓮の滝の女郎蜘蛛』に似た伝説ですが、浄蓮の滝の蜘蛛が美女なのに対して、こちらは婆蜘蛛ということだそうで。
・巫女ヤマメさん:下さい。
第1章 火の国のヤマノメ 一覧
感想をツイートする
ツイート