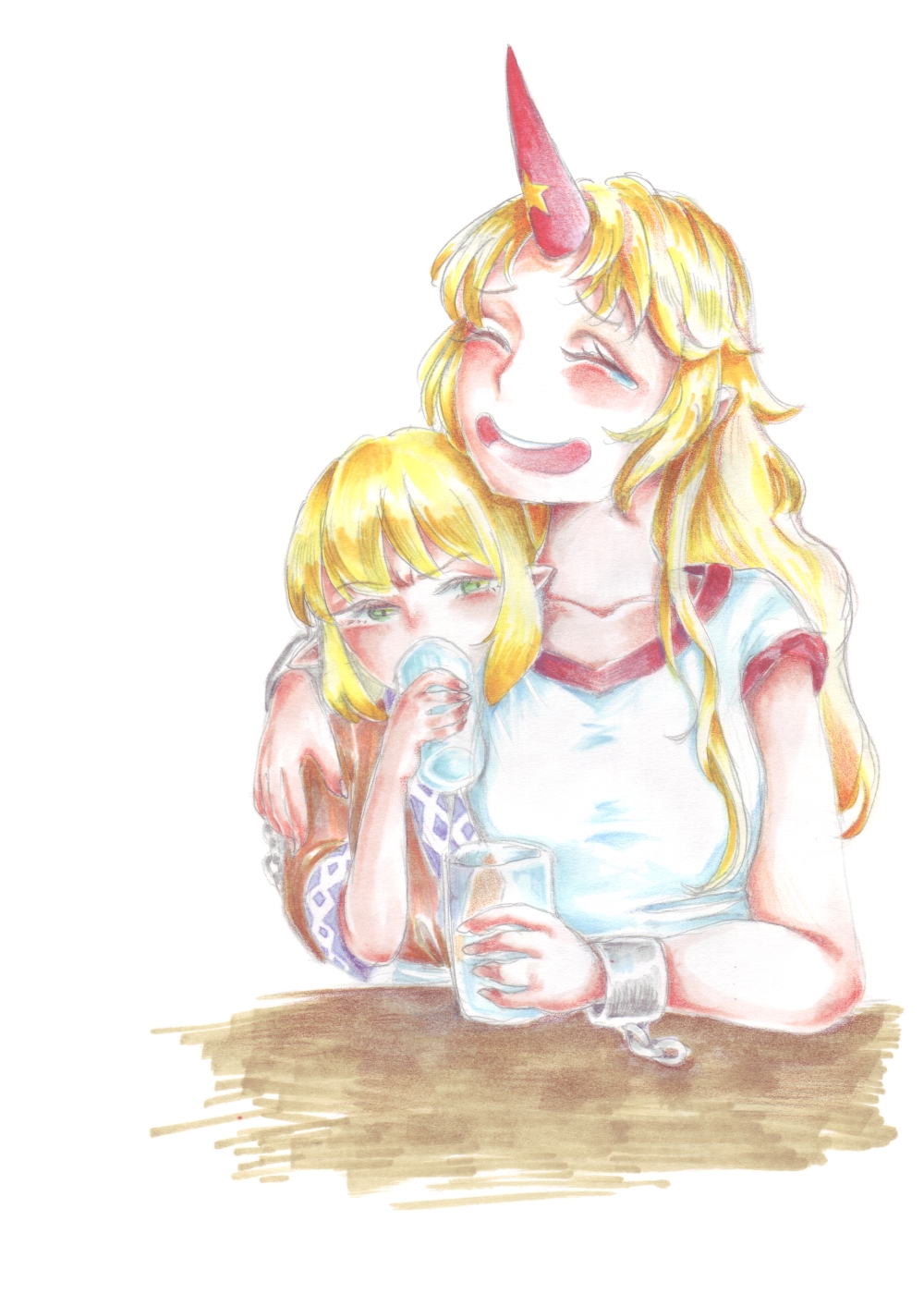楽園の確率~Paradiseshift.第3章 怨霊の聲 怨霊の聲 第3話
所属カテゴリー: 楽園の確率~Paradiseshift.第3章 怨霊の聲
公開日:2017年06月19日 / 最終更新日:2017年06月19日
楽園の確率 ~ Paradise Shift. 第3章
怨霊の聲 第3話
妖怪の山外縁。九天の滝の滝口には、地の底を見おろし続ける三人の天狗の姿。
千里眼で実際にそちらを見透している椛と、この視界を共有しているはたては、息まで揃えて唸り続けている。
「現状、どうなんですか」
二人に付き合い続け、側に控える文が語りかける。
一応は記者らしく、取材として調査状況を手元のネタ帳――文花帖にしたためているが、その内容は唸る二人の観察と、ここから無駄に演繹される連想の群れだけ。今のところ、全く意味を成さない落書きで埋まっていた。
「信じられないぐらい平和よ。土蜘蛛も鬼も」
旧地獄の中核、地霊殿の様子こそまだ見透せていないが、かつて妖怪の賢者を仲介と保証人に立て、不可侵関係と同時に交わされた彼女らが怨霊を封じ込めるという役割だけは、確かに果たされているらしい。
このはたての見立てにはしかし、今まで息を合わせていた椛が、小さく異議を唱える。
「確かに、土蜘蛛や鬼を始めとした、既存の妖怪は今のところ何も。ですが少し、気になるモノが入り込んでます」
「えっ!? ちょっと椛、私気付かなかったんだけど、どいつのこと?」
そも、先ほどまで唸り続けていた理由も、実は違っていたらしい。
「あの姿。恐らくは、天邪鬼……」
文の眉が動き、口の端に微か加わった力が、その色を薄くする。
「間違いない?」
「はい。はたてさん、念写してもらえますか? 旧都郊外のスラムに住み着いた、小さな二本角に、前髪だけ赤い鬼もどきです」
椛が幾度かその妖怪――正邪に意識して視覚を指向していたのもあり、すぐに「あいつか」と頷くと、千里眼の底上げに注ぎ込んでいた妖力を、自身の手中で弄ぶ電子式カメラに込めなおす。
画質こそ文のカメラに劣るが、即席カメラよりも早く結果を確認できるのが、これの長所の一つ。
はたてはおよそ旧地獄の方へ向き、また俯角を取ると「この辺かな?」と不安になるような呟きと共に、ボタンを押し込む。電子的で、雰囲気も台無しな「ピロリン」という擬似シャッター音が鳴ると、他には複雑な手順も術の行使も無く念写は終了。
「こいつでいい?」
椛は頷き、文は液晶画面に映し出された、やや不鮮明な画像に視線を定める。
「――でも天邪鬼なんて、私らが気にするような奴でもない小者でしょ」
続けてはたてが言ったとおり、それは、天狗から見ても取るに足らない妖怪のはず。
「ええ、その通り。でもその能力、使いようによっては侮れないわ」
なんでもひっくり返す能力の持ち主(しかしその地力の貧弱さからすぐに限界に達するらしい)、というのが、一般的な天狗が知る天邪鬼の能力であるが――
「知ってるって。奴は“舌禍”をもたらすモノ、要は煽動に定評があるんでしょ?」
それは神代に謳われる縁である。
かつて、高天原(たかまがはら:天の国)より葦原中国(あしはらのなかつくに:地上)に遣わされた天稚彦(あめのわかひこ)が、いつしか大国主(おおくにぬし)の娘と良き仲になり、本来天津神々が治めようとしていた地上を己が手の物にせんと画策していた。
それを知らない天津神は、一向に責を果たさない彼の元へ、メッセンジャーとして雉の鳴女(なきめ)を遣わして問いただすが、彼は天津神より授かっていた『天之麻迦古弓(あめのまかこゆみ)』を引き、天へ向けて『天羽々矢(あめのはばや)』を放つと、雉の鳴女を射落としたという。
「そのまま天に至った矢は射返され、哀れ天稚彦は大逆人として死亡。その切っ掛けになったのが、雉の鳴女の言葉を曲げて伝えた天探女(あめのさぐめ)。舌禍の神、天邪鬼の大元。こういうの聞くと、そもそも天稚彦を色々と唆してたのもコイツなんじゃ、って考えちゃうよね」
「そういう陰謀論はいらないから」
素っ気なく言う文に、はたては威勢よさげに啖呵を切りつつ、わざとらしい目線を投げかける。文はこれにも取り合わないので、はたても諦めて話を進める。
「はいはい、文が言いたいことぐらい分かるって。奴の力なんてたいしたことは無い。けど、地底の妖怪に対する働きかけは、十分警戒した方がいいってことでしょ」
「それも無いと思います。本来は」
今度は椛からの反論。
鬼が約定を違えるとはとても思えない。天狗として、妖怪の山の旧支配者たる鬼を恐れながらも、彼ら彼女らが確固として持つ矜持だけは信じての言葉だ。
「ええ、椛が言うとおり、本来はあり得ない。でも貴女が始めに撮った大蜘蛛の写真と、天邪鬼が今、旧地獄のスラムに居るっていうのが懸念なんですよ」
今の調査の起こりを思い出させる意図もあって、文は言った。
ただでさえ嫌われ者ばかりが集まる地底にあって、更にその辺縁に追いやられている者達も居るのだ。文の公算は、天邪鬼が煽動するとすればそちらだろうとのものであるが、彼らだけなら単なる地底の騒乱に留まる(まず勇儀がそれを許さないであろうとの、これも信頼と言える)であろうし、これも結局とるに足らない程度に収まる。
問題は土蜘蛛の影。
「土蜘蛛ねぇ。鬼の道具風情が、鬼に刃向かってどうにかできるなんて――」
文の顔色がにわかに険しくなる。眼光は鋭くはたてを射抜き、その心を責める。
「ちょっと何よ」
「そういう言い方は、止めろ」
何が文の気に障ったのか、思い当たるところが無い。
はたては彼女の怒りよりも、何故か険悪になった空気に戸惑い、椛に助けを求める。
「土蜘蛛は、誰かに使役される存在じゃないんですよ。当然、それは鬼達も」
彼女の確かな助言を受けると、はたては「しまった」と言う代わりに目をつぶって首を傾げてから、前方に頭を振り出す。
「分かった。撤回する」
ただし謝りはしない。
文も、自分に対してのそれは必要無いと思っている。しかし今ひとたびと責める。
「他の誰が彼らをどう呼ぼうとも、どうでもいいのよ。けれど、貴女がそう言うのだけは、私も見過ごせない」
「だからもう言わないって!」
「それにしても、土蜘蛛が敵に回れば、鬼とてただでは済まないですよ。彼らは鬼に比肩するほどの大力(だいりき)と、貴女が道具とのたまった通りの技能者の集団ですからね」
しつこい、さっきの失言はもう手打ちだろうと、はたては軽く逆上してむくれる。
「文様、傍から聞いてても、くどいし鬱陶しいです」
「肝心な事はこのぐらい言わないと、でしょう? 御母堂の手前もありますし」
はたてに重ねた椛の非難に、文は申し開きを述べつつも、しつこく当たったのは反省している。
そんな彼女から顔を逸らし、はたてと椛はヒソヒソと囁きあう。
「いつもはさ、鬼神が天魔様でもリスペクトも無いくせに、今のなんか矛盾してない?」
「それと貶すのは別なんですよ、文様的には」
聞こえていたのか否か、文はここでひとつ咳払い。
「ともかく、今注視すべきは、天邪鬼による土蜘蛛の煽動ね」
広げた文花帖を万年筆で一度二度と突き、余計な思考を止めながら文は言う。
しかしこれに、はたてと椛はまた顔を見合わせる。
文が何事かと尋ねようとすると、困った風に眉を寄せた椛が質問より先に答える。
「それが、その天邪鬼が見当たらないんですよ」
単に見逃した、追い損ねたという自身のミスからの問題なら、椛はそれなりに殊勝な様子を見せるであろう。しかし今の彼女の態度は、自身の誤びゅうでも意図の内でもない、某かの不可解な問題が起こったのだと告げていた。
「はたて?」
「いや、地底の瘴気もノイズの原因だったんだろうけど、アイツに寄れば寄るほどマジで視界が利かなくなってさ。もー、わけわからん」
問われたはたても、分かる限りの事実を語るのみ。
「なんで椛の浄天眼が、おかしい……」
彼女が授かったのは、天邪鬼が如き天に唾するモノを探し出す力。有頂天の更に上、まさしく天の国におわす方々(神仏それぞれに居るが)の総意によりもたらされたものである。
天邪鬼こそ、先の通り、元は天津神に弓引かせた存在であるが、本邦への仏の来訪以来は仏の力を誇示(宣伝)するため、よく明王部や天部に属する仏尊の足下に踏みしだかれてもいる。
このため千里眼、殊に椛のその能力は、その探索のために発揮されて然り。それが岩盤や瘴気に留まらず、更なる障壁にも阻まれているのだ。
文もこれには少しばかりの不安を抱きつつも、
「まあ、いいでしょう。貴女たちががもっと気合い入れればいいだけだから。あ、今更ですが記事のソースは共有で、抜け駆けは許さないからね」
どうせさもない理由であろうと断じ、しかし天邪鬼の探索と監視だけは土蜘蛛の動向よりも子細に行うべきかと決断する。
またもや勝手な判断を強制しようとする文には、二人からのブーイングが投げつけらた。
∴
食う寝る打つぐらいしか娯楽の無い地下世界。
今日も今日とて一等賑わうのは、土蜘蛛のご一行がぞろぞろと訪れ、更には勇儀一派までも参戦という『末げん』なる号の小料理屋。
旧地獄街道から路地を二つも入った奥まった立地のため、赤提灯のずらりと並ぶ表通りに比べれば落ち着いた感もあり、希少な食材も特別なルートで優先的に卸されている。
店主がいつも店頭に掲げている『本日のオススメ』ののぼりには、達筆で『人肉ありマス』と記されている。
しかしながらこれ、中身はただの鶏肉。
猛禽の嘴にざんばら頭の店主がこれに腕を振るうが、彼も当然、旧地獄の妖怪である。
訪れる客達には、この常設のオススメを本当の人肉だと信じて注文し、文句を言うモノなどはいない。悪ふざけで時たま詐欺だなんだと言うほかは。
それは、今ここを占拠する土蜘蛛と鬼も変わらない。
皆、席を寄せ、卓に植わった形の一風変わったいろりを囲み、薄く色づいた鍋の底に沈むつみれに箸を伸ばす。
「こんな事になるなら、来るんじゃなかったわ」
こぢんまりとしながらも活気に満ちた店内で、ひとり鬱々とした雰囲気を漂わせながらパルスィはそう呟き、横には彼女の分まで上機嫌でその肩に手を伸ばす勇儀の姿がある。
当然と言っていいものか、パルスィの不機嫌の原因は毎度の如く勇儀だ。
いろりの角を挟んだ隣では、ヤマメが手を合わせ、何度目になるか分からない「ゴメンなさい」のジェスチュアを繰り返していた。
「はぁ……あっちでなら落ち着いて呑めるかと思ったのに、なんでこうなるのよ!」
場所を移したのは、単に満席との理由による。
土蜘蛛一同がそんなこんなで『どん底』を諦め、ちょうどそれを見かけた勇儀達が土蜘蛛達と同道。ヤマメも現地へ着いて初めてそれを知り、嫌な予想を浮かべて戻ろうとするパルスィを無理矢理連れて来て――の今が、この有り様である。
勇儀が無理を通そうとすればあちらの店主も応じたであろうし、取り巻きなどはそうしようともした。しかし勇儀本人が、土蜘蛛達の後に続こうと彼らをたしなめたのだった。
ヤマメとしては、勇儀達とは会う予定であったし、場所こそ違えど当初の予定通り。
「姐さん姐さん。パルさんも嫌がってるし、ここはちょいと私とお話ししません?」
「なぁに、嫌よ嫌よも好きのうちって言うだろ。ねぇパルスィ」
「本気で嫌がってるのよ、私は!」
鬼の筆頭と見て差し支えない勇儀に、こうも無礼を通り越した態度を取っていられるのも、旧地獄ではパルスィぐらいのもの。彼女の妖怪としての起こりの古さが理由の一つとも言えるが、勇儀が本気で熱を上げている証拠でもあろう。
勇儀の手をふりほどいたパルスィは、利害の一致するヤマメを押し付けて逃れる。
「どうも、姐さん」
ようやく本題に入れるかと、腰を据えるヤマメ。
「あんたも見た目は綺麗なんだけどねぇ」
「いや、そうじゃなくて」
「分かってるよ。まあまあ、火が通ったヤツからつつきな。食べながらゆっくり話そうや」
言って、自身も箸を手に取る勇儀。ヤマメは遅参の詫びと共に「天邪鬼の件を」と伝えていたし、勇儀もその通り受け取っているはずである。
「あのー」
「軽く見てるわけじゃないよ。あいつ、小槌なんぞ見せびらかしてたし。でもありゃ私らか、鬼を倒した英雄の一族じゃなきゃ使えないような代物さ。まあ、あいつが持っていたのは偽物だろうがね」
一体何の話であろうかと、目をしばたかせるヤマメ。
「本物だ偽物だって、その小槌ってなんなんです?」
「知らないのかい。何でも願いが叶うっていう『打ち出の小槌』さ」
その能力の伝承は、主に人間によるもの。
だが人間の願いなどは大抵、富を得ることや長生きしたいという程度である。それらが得られれば、人界におけるその他の願いもおよそ叶おうというものだ。
故に、無限の力を持っているとも見なされるという呪具の限界も、そこまで高い物ではない。
「知りませんでした」
「あんたも早くに“こっち”に来たクチだし、この話が流布され始めたのも結構後になってからだし、知らなくても仕方ないか。ざっくり言えば、そういう能力を持った呪具を造り出した鬼が、小人に退けられた挙げ句にそれを奪われたって、そんなお伽噺があるんだよ」
結果として人間の味方となり英雄に奉られた小人は、朝廷から官位官職を授かり、神格まで与えられてめでたしめでたし。とのオチである。
ヤマメは、やっぱり初めて聞いた話だと首を傾げるが、小槌の真贋はいざしらず、そういった物をちらつかせた正邪の意図を推し量る。
「小槌って要は小さい木槌ですよね。だとしたらそれ、姐さん達にだけじゃなく、私達土蜘蛛に対してのあてつけかも知れませんよ」
聞くのに徹そうとしていたヤマメだったが、今の言葉に勇儀が興味を示したのを認めると、あえて語る。
「京のみやこより見て北の嶺、比叡山側は黒谷で討たれた大蜘蛛は、あわれ無数の鉄串に身を貫かれて晒された――」
ヤマメが語り始めると、土蜘蛛達は一同に彼女の方に向き直る。箸を持っていた手は升や盃に代え、「待ってました」と口々にはやし立てる。
「あー違う、今日のは違うからね。ほら散れ、散れ」
蜘蛛の子ならぬ男女を問わぬ大の土蜘蛛達は、期待が外れたとぶつくさ言いながら、約半分は元の位置へ。残りは依然としてヤマメの語りに耳を傾ける。
「では気を取り直しまして。
これな大蜘蛛、同じ蟲妖と言われども、我ら火の国の土蜘蛛は、彼のモノを知らぬなり」
ヤマメら始めの入植者、そして続く大半の土蜘蛛は、ほとんどが火の国の住人であった。
一応ヤマメも、古い姿の幻想郷へ辿り着く前、この黒谷の大蜘蛛の存在は耳にしていた。だが火の国に帰った際、このモノについて古老に尋ねてみたところ、彼らからも「知らぬ」との答えが返るばかりだったのだ。
「私でも知ってるのに、ヤマメ達が知らないっての?」
不意にパルスィが声を上げ、次いで彼女は「然知った」と口を押さえる。
「パルさんや。舞や詩吟を披露してるんじゃないし、気にしなさんな」
僅かも気を害した様子も無く、ヤマメは折角だからとパルスィの話を促す。
「いや、鬼も居る手前だからさ」
パルスィが彼らを一瞥し、最後に勇儀と目線を合わせると、勇儀は少し驚いた風にしてから、にへらと力の抜けた笑い顔を浮かべる。どうでもいいらしい。
「だってその大蜘蛛って葛城(かつらぎ)山の、源頼光(みなもとのよりみつ)に討たれたって奴でしょ。私もほら、色々あったけど、頼光の郎党の綱(つな)に討たれた、って事になってるし――」
今の言い方では橋姫は奴らに討たれたのではないのか、これは初耳だ一大事だと、土蜘蛛と鬼が揃ってざわめき声を上げると、パルスィは目を光らせてこれを黙らせる。
「――なってるし、その周りの話は知ってるのよ。そいつの正体は大和国(やまとのくに:奈良県)葛城山の一言主(ひとことぬし)。ヤマメ達とは別の起源を持った土蜘蛛よ」
話の脱線を自覚し、自分の番はこれで終わりと、パルスィは口をつぐむ。
「んー、そんなんだったっけね、確か。いや、流石は元みやこ住まいだね」
そう言うと、またひとたびと気を取り直してヤマメは続ける。
「我らを討ち果たしたは、にくきかな、あなにくきかな、阿蘇大明神の放った鏃、小碓尊(おうすのみこと:日本武尊)の謀、皇(すめら)の軍が携える椿の木槌なり」
そうした力に抗えずに破れたが、我ら決して下らず。
そう言ったところで、ヤマメは始めの木槌の話に戻る。
「と言うことで出てきました木槌。土蜘蛛への挑発かもってのは、こんなとこね。でもそいつ、今のところウチの誰にも接触したって聞かないし、勘ぐり過ぎかも知れないけれど。それと、ちょっと思い出した事もあるんだけど、話していい?」
否と言う者は無し。幻想郷でも一層隔絶されたここでは、ちょっとした四方山話でも大いに歓迎される模様である。
ただ、否とは唱えなかったが、ここで勇儀が声を上げる。
「火の国、鎮西(ちんぜい:九州)からの縁なら、私も心当たりがあるねぇ」
「よっ、姐さん、待ってましたっ!」
ヤマメがそう囃し立てる必要も無く、場は盛り上がる。これは勇儀直参の鬼達ですら聞いた覚えが無い話らしく、彼らも居住まいを正している。
「とくとお聞きよ皆の衆。
時は平安。鎮西総追捕使、源八郎為朝(ためとも)なる大悪党が鎮西を北へ南へと駆け、京へ戻ってから一敗地にまみれた後の話だ」
ヤマメは覚えのある名を耳にし、興味津々な風だった顔を穏やかな物に変える。
結句、己があの人間の英雄の先(未来)を知ることは叶わなかった。彼は何を思っていたのか。彼がみやこでの戦に打ち勝てば、見る事も叶ったやも知れなかったが、それもままならぬず彼は潰えた。
勇儀の話から、その一端でも知れるかもと期待する。
「みやこでの戦に敗れた鎮西八郎は、伊豆の大島に流される訳だが――」
不意に空気が震えたかと思うと、全くの出し抜けに大音響が場を包み、話は遮られる。
それが収まった後、店内はひと時の静寂を迎え、次には皆口々に「何事か」と大わらわ。
音と共に一度激しく揺れはしたが、続く振動は無く、地震でない事だけは分かった。
店舗も鬼や土蜘蛛が建てた物であるし、造りもしっかりして崩れる様子は無いが、念のために炭を除け、鍋の中身を守るために蓋を被せる。
動揺しているのか冷静なのか、それともみみっちいのか、よく分からない場面である。
勇儀が「外には違いないな」と言うと、鬼はぞろぞろと表に歩み出る。土蜘蛛達は、それに先だって店外へ躍り出ており、こちらの先頭にはヤマメが立つ。
何が起こったのか、土蜘蛛には心当たりがあった。
「確認してなかったけど、炭鉱組ってみんな来てる?」
言いながら、今の面子を確認するヤマメ。
少なくとも新坑道での会同に顔を出していた者の姿は揃っている。
「これで全部じゃないですけど、残りの奴らはいつも通り炭鉱に行ってるはずです」
現地で現場監督に立っていた男が答えた。
それに新規の炭鉱は封印したばかり。では従来の炭鉱で事故ったのか。いずれにしても、土蜘蛛の住まう風穴方面からの爆発だ。発破の量でも間違えたのか。
思いつく限りの言葉を交わしながら、彼ら彼女らはそちらへ駆け出す。
緊急の事態だからと、旧地獄街道の雑踏を飛び越える土蜘蛛達。
街の明かりが尽きる線――橋守不在の境の方から、何かを引きずる影を認めて降下。
「おーい、何があったの!? 人手は足りてる?」
降り立ち、引きずられている物を確認し、ヤマメは一瞬のどを詰まらせる。
戸板に横向きに縛り付けられた土蜘蛛の姿があったが、どう見ても無事とは言い難い。
髪や被服は焦げ、それらの一部は肌に貼り付いている。それら火傷に加えて、何かに切り裂かれた無数の傷も見て取れる。どちらも爆風にやられた物であろう。鮮血の滲んだ包帯と、その節約のため一緒に巻かれた添え木を見るに、骨折もしている模様。
何より、口からは血が溢れ続けている。衝撃波による負傷、爆発事故の証拠だ。
「ヤマメさん。見ての通りです、バカ共が勝手に新しい炭鉱掘りやがって、しょうもない事に試掘程度に掘ってただけで「ドカン」だ、そうですよ」
足を緩めず答えた彼を、ヤマメが連れていた女が助け、戸板を持ち上げる。
まだまだ負傷者が運ばれてくるのは確実。
ヤマメが仲間を引き連れ風穴を上がろうとすると、その背に向けて勇儀の声。
「宵の通りの一つ目鬼の所は駄目だ! あのヤブ、今は地獄に往診に行ってるよ!」
「でもあのオッサン以外、こんな傷診れる奴いませんよ?!」
「私は地霊殿を通して、ヤブが駄目ならいっそ地獄の医者でも連れて来させるように掛け合ってくるよ。あんたは最悪、地上の医者、例の竹林の奴に繋ぎを付けられるように算段しときな。こんなんで同族の数を減らしたかぁ無いだろ?!」
地底のモノが地上へ出る。
一人二人なら、個人的な交流と言うことで妖怪の賢者や天狗も目をつぶってくれようが、集団でとなるとそうはいかない。
怪我をしたからと正直に訴えても、信じるどころか謀だと疑ってかかるのが地上の妖怪達だ。
しかし今は、そんなきらいも振り切らなければならない。
「分かりました。伝手を辿って何とか――」
ヤマメは、勇儀に答えながら視線を走らせた先に見慣れぬ者を認める。
ただ、見慣れはしないがそれは、話でだけならヤマメも知るモノ。粗末な小槌を携えた小鬼、正邪であった。
怨霊の聲 第3話
妖怪の山外縁。九天の滝の滝口には、地の底を見おろし続ける三人の天狗の姿。
千里眼で実際にそちらを見透している椛と、この視界を共有しているはたては、息まで揃えて唸り続けている。
「現状、どうなんですか」
二人に付き合い続け、側に控える文が語りかける。
一応は記者らしく、取材として調査状況を手元のネタ帳――文花帖にしたためているが、その内容は唸る二人の観察と、ここから無駄に演繹される連想の群れだけ。今のところ、全く意味を成さない落書きで埋まっていた。
「信じられないぐらい平和よ。土蜘蛛も鬼も」
旧地獄の中核、地霊殿の様子こそまだ見透せていないが、かつて妖怪の賢者を仲介と保証人に立て、不可侵関係と同時に交わされた彼女らが怨霊を封じ込めるという役割だけは、確かに果たされているらしい。
このはたての見立てにはしかし、今まで息を合わせていた椛が、小さく異議を唱える。
「確かに、土蜘蛛や鬼を始めとした、既存の妖怪は今のところ何も。ですが少し、気になるモノが入り込んでます」
「えっ!? ちょっと椛、私気付かなかったんだけど、どいつのこと?」
そも、先ほどまで唸り続けていた理由も、実は違っていたらしい。
「あの姿。恐らくは、天邪鬼……」
文の眉が動き、口の端に微か加わった力が、その色を薄くする。
「間違いない?」
「はい。はたてさん、念写してもらえますか? 旧都郊外のスラムに住み着いた、小さな二本角に、前髪だけ赤い鬼もどきです」
椛が幾度かその妖怪――正邪に意識して視覚を指向していたのもあり、すぐに「あいつか」と頷くと、千里眼の底上げに注ぎ込んでいた妖力を、自身の手中で弄ぶ電子式カメラに込めなおす。
画質こそ文のカメラに劣るが、即席カメラよりも早く結果を確認できるのが、これの長所の一つ。
はたてはおよそ旧地獄の方へ向き、また俯角を取ると「この辺かな?」と不安になるような呟きと共に、ボタンを押し込む。電子的で、雰囲気も台無しな「ピロリン」という擬似シャッター音が鳴ると、他には複雑な手順も術の行使も無く念写は終了。
「こいつでいい?」
椛は頷き、文は液晶画面に映し出された、やや不鮮明な画像に視線を定める。
「――でも天邪鬼なんて、私らが気にするような奴でもない小者でしょ」
続けてはたてが言ったとおり、それは、天狗から見ても取るに足らない妖怪のはず。
「ええ、その通り。でもその能力、使いようによっては侮れないわ」
なんでもひっくり返す能力の持ち主(しかしその地力の貧弱さからすぐに限界に達するらしい)、というのが、一般的な天狗が知る天邪鬼の能力であるが――
「知ってるって。奴は“舌禍”をもたらすモノ、要は煽動に定評があるんでしょ?」
それは神代に謳われる縁である。
かつて、高天原(たかまがはら:天の国)より葦原中国(あしはらのなかつくに:地上)に遣わされた天稚彦(あめのわかひこ)が、いつしか大国主(おおくにぬし)の娘と良き仲になり、本来天津神々が治めようとしていた地上を己が手の物にせんと画策していた。
それを知らない天津神は、一向に責を果たさない彼の元へ、メッセンジャーとして雉の鳴女(なきめ)を遣わして問いただすが、彼は天津神より授かっていた『天之麻迦古弓(あめのまかこゆみ)』を引き、天へ向けて『天羽々矢(あめのはばや)』を放つと、雉の鳴女を射落としたという。
「そのまま天に至った矢は射返され、哀れ天稚彦は大逆人として死亡。その切っ掛けになったのが、雉の鳴女の言葉を曲げて伝えた天探女(あめのさぐめ)。舌禍の神、天邪鬼の大元。こういうの聞くと、そもそも天稚彦を色々と唆してたのもコイツなんじゃ、って考えちゃうよね」
「そういう陰謀論はいらないから」
素っ気なく言う文に、はたては威勢よさげに啖呵を切りつつ、わざとらしい目線を投げかける。文はこれにも取り合わないので、はたても諦めて話を進める。
「はいはい、文が言いたいことぐらい分かるって。奴の力なんてたいしたことは無い。けど、地底の妖怪に対する働きかけは、十分警戒した方がいいってことでしょ」
「それも無いと思います。本来は」
今度は椛からの反論。
鬼が約定を違えるとはとても思えない。天狗として、妖怪の山の旧支配者たる鬼を恐れながらも、彼ら彼女らが確固として持つ矜持だけは信じての言葉だ。
「ええ、椛が言うとおり、本来はあり得ない。でも貴女が始めに撮った大蜘蛛の写真と、天邪鬼が今、旧地獄のスラムに居るっていうのが懸念なんですよ」
今の調査の起こりを思い出させる意図もあって、文は言った。
ただでさえ嫌われ者ばかりが集まる地底にあって、更にその辺縁に追いやられている者達も居るのだ。文の公算は、天邪鬼が煽動するとすればそちらだろうとのものであるが、彼らだけなら単なる地底の騒乱に留まる(まず勇儀がそれを許さないであろうとの、これも信頼と言える)であろうし、これも結局とるに足らない程度に収まる。
問題は土蜘蛛の影。
「土蜘蛛ねぇ。鬼の道具風情が、鬼に刃向かってどうにかできるなんて――」
文の顔色がにわかに険しくなる。眼光は鋭くはたてを射抜き、その心を責める。
「ちょっと何よ」
「そういう言い方は、止めろ」
何が文の気に障ったのか、思い当たるところが無い。
はたては彼女の怒りよりも、何故か険悪になった空気に戸惑い、椛に助けを求める。
「土蜘蛛は、誰かに使役される存在じゃないんですよ。当然、それは鬼達も」
彼女の確かな助言を受けると、はたては「しまった」と言う代わりに目をつぶって首を傾げてから、前方に頭を振り出す。
「分かった。撤回する」
ただし謝りはしない。
文も、自分に対してのそれは必要無いと思っている。しかし今ひとたびと責める。
「他の誰が彼らをどう呼ぼうとも、どうでもいいのよ。けれど、貴女がそう言うのだけは、私も見過ごせない」
「だからもう言わないって!」
「それにしても、土蜘蛛が敵に回れば、鬼とてただでは済まないですよ。彼らは鬼に比肩するほどの大力(だいりき)と、貴女が道具とのたまった通りの技能者の集団ですからね」
しつこい、さっきの失言はもう手打ちだろうと、はたては軽く逆上してむくれる。
「文様、傍から聞いてても、くどいし鬱陶しいです」
「肝心な事はこのぐらい言わないと、でしょう? 御母堂の手前もありますし」
はたてに重ねた椛の非難に、文は申し開きを述べつつも、しつこく当たったのは反省している。
そんな彼女から顔を逸らし、はたてと椛はヒソヒソと囁きあう。
「いつもはさ、鬼神が天魔様でもリスペクトも無いくせに、今のなんか矛盾してない?」
「それと貶すのは別なんですよ、文様的には」
聞こえていたのか否か、文はここでひとつ咳払い。
「ともかく、今注視すべきは、天邪鬼による土蜘蛛の煽動ね」
広げた文花帖を万年筆で一度二度と突き、余計な思考を止めながら文は言う。
しかしこれに、はたてと椛はまた顔を見合わせる。
文が何事かと尋ねようとすると、困った風に眉を寄せた椛が質問より先に答える。
「それが、その天邪鬼が見当たらないんですよ」
単に見逃した、追い損ねたという自身のミスからの問題なら、椛はそれなりに殊勝な様子を見せるであろう。しかし今の彼女の態度は、自身の誤びゅうでも意図の内でもない、某かの不可解な問題が起こったのだと告げていた。
「はたて?」
「いや、地底の瘴気もノイズの原因だったんだろうけど、アイツに寄れば寄るほどマジで視界が利かなくなってさ。もー、わけわからん」
問われたはたても、分かる限りの事実を語るのみ。
「なんで椛の浄天眼が、おかしい……」
彼女が授かったのは、天邪鬼が如き天に唾するモノを探し出す力。有頂天の更に上、まさしく天の国におわす方々(神仏それぞれに居るが)の総意によりもたらされたものである。
天邪鬼こそ、先の通り、元は天津神に弓引かせた存在であるが、本邦への仏の来訪以来は仏の力を誇示(宣伝)するため、よく明王部や天部に属する仏尊の足下に踏みしだかれてもいる。
このため千里眼、殊に椛のその能力は、その探索のために発揮されて然り。それが岩盤や瘴気に留まらず、更なる障壁にも阻まれているのだ。
文もこれには少しばかりの不安を抱きつつも、
「まあ、いいでしょう。貴女たちががもっと気合い入れればいいだけだから。あ、今更ですが記事のソースは共有で、抜け駆けは許さないからね」
どうせさもない理由であろうと断じ、しかし天邪鬼の探索と監視だけは土蜘蛛の動向よりも子細に行うべきかと決断する。
またもや勝手な判断を強制しようとする文には、二人からのブーイングが投げつけらた。
∴
食う寝る打つぐらいしか娯楽の無い地下世界。
今日も今日とて一等賑わうのは、土蜘蛛のご一行がぞろぞろと訪れ、更には勇儀一派までも参戦という『末げん』なる号の小料理屋。
旧地獄街道から路地を二つも入った奥まった立地のため、赤提灯のずらりと並ぶ表通りに比べれば落ち着いた感もあり、希少な食材も特別なルートで優先的に卸されている。
店主がいつも店頭に掲げている『本日のオススメ』ののぼりには、達筆で『人肉ありマス』と記されている。
しかしながらこれ、中身はただの鶏肉。
猛禽の嘴にざんばら頭の店主がこれに腕を振るうが、彼も当然、旧地獄の妖怪である。
訪れる客達には、この常設のオススメを本当の人肉だと信じて注文し、文句を言うモノなどはいない。悪ふざけで時たま詐欺だなんだと言うほかは。
それは、今ここを占拠する土蜘蛛と鬼も変わらない。
皆、席を寄せ、卓に植わった形の一風変わったいろりを囲み、薄く色づいた鍋の底に沈むつみれに箸を伸ばす。
「こんな事になるなら、来るんじゃなかったわ」
こぢんまりとしながらも活気に満ちた店内で、ひとり鬱々とした雰囲気を漂わせながらパルスィはそう呟き、横には彼女の分まで上機嫌でその肩に手を伸ばす勇儀の姿がある。
当然と言っていいものか、パルスィの不機嫌の原因は毎度の如く勇儀だ。
いろりの角を挟んだ隣では、ヤマメが手を合わせ、何度目になるか分からない「ゴメンなさい」のジェスチュアを繰り返していた。
「はぁ……あっちでなら落ち着いて呑めるかと思ったのに、なんでこうなるのよ!」
場所を移したのは、単に満席との理由による。
土蜘蛛一同がそんなこんなで『どん底』を諦め、ちょうどそれを見かけた勇儀達が土蜘蛛達と同道。ヤマメも現地へ着いて初めてそれを知り、嫌な予想を浮かべて戻ろうとするパルスィを無理矢理連れて来て――の今が、この有り様である。
勇儀が無理を通そうとすればあちらの店主も応じたであろうし、取り巻きなどはそうしようともした。しかし勇儀本人が、土蜘蛛達の後に続こうと彼らをたしなめたのだった。
ヤマメとしては、勇儀達とは会う予定であったし、場所こそ違えど当初の予定通り。
「姐さん姐さん。パルさんも嫌がってるし、ここはちょいと私とお話ししません?」
「なぁに、嫌よ嫌よも好きのうちって言うだろ。ねぇパルスィ」
「本気で嫌がってるのよ、私は!」
鬼の筆頭と見て差し支えない勇儀に、こうも無礼を通り越した態度を取っていられるのも、旧地獄ではパルスィぐらいのもの。彼女の妖怪としての起こりの古さが理由の一つとも言えるが、勇儀が本気で熱を上げている証拠でもあろう。
勇儀の手をふりほどいたパルスィは、利害の一致するヤマメを押し付けて逃れる。
「どうも、姐さん」
ようやく本題に入れるかと、腰を据えるヤマメ。
「あんたも見た目は綺麗なんだけどねぇ」
「いや、そうじゃなくて」
「分かってるよ。まあまあ、火が通ったヤツからつつきな。食べながらゆっくり話そうや」
言って、自身も箸を手に取る勇儀。ヤマメは遅参の詫びと共に「天邪鬼の件を」と伝えていたし、勇儀もその通り受け取っているはずである。
「あのー」
「軽く見てるわけじゃないよ。あいつ、小槌なんぞ見せびらかしてたし。でもありゃ私らか、鬼を倒した英雄の一族じゃなきゃ使えないような代物さ。まあ、あいつが持っていたのは偽物だろうがね」
一体何の話であろうかと、目をしばたかせるヤマメ。
「本物だ偽物だって、その小槌ってなんなんです?」
「知らないのかい。何でも願いが叶うっていう『打ち出の小槌』さ」
その能力の伝承は、主に人間によるもの。
だが人間の願いなどは大抵、富を得ることや長生きしたいという程度である。それらが得られれば、人界におけるその他の願いもおよそ叶おうというものだ。
故に、無限の力を持っているとも見なされるという呪具の限界も、そこまで高い物ではない。
「知りませんでした」
「あんたも早くに“こっち”に来たクチだし、この話が流布され始めたのも結構後になってからだし、知らなくても仕方ないか。ざっくり言えば、そういう能力を持った呪具を造り出した鬼が、小人に退けられた挙げ句にそれを奪われたって、そんなお伽噺があるんだよ」
結果として人間の味方となり英雄に奉られた小人は、朝廷から官位官職を授かり、神格まで与えられてめでたしめでたし。とのオチである。
ヤマメは、やっぱり初めて聞いた話だと首を傾げるが、小槌の真贋はいざしらず、そういった物をちらつかせた正邪の意図を推し量る。
「小槌って要は小さい木槌ですよね。だとしたらそれ、姐さん達にだけじゃなく、私達土蜘蛛に対してのあてつけかも知れませんよ」
聞くのに徹そうとしていたヤマメだったが、今の言葉に勇儀が興味を示したのを認めると、あえて語る。
「京のみやこより見て北の嶺、比叡山側は黒谷で討たれた大蜘蛛は、あわれ無数の鉄串に身を貫かれて晒された――」
ヤマメが語り始めると、土蜘蛛達は一同に彼女の方に向き直る。箸を持っていた手は升や盃に代え、「待ってました」と口々にはやし立てる。
「あー違う、今日のは違うからね。ほら散れ、散れ」
蜘蛛の子ならぬ男女を問わぬ大の土蜘蛛達は、期待が外れたとぶつくさ言いながら、約半分は元の位置へ。残りは依然としてヤマメの語りに耳を傾ける。
「では気を取り直しまして。
これな大蜘蛛、同じ蟲妖と言われども、我ら火の国の土蜘蛛は、彼のモノを知らぬなり」
ヤマメら始めの入植者、そして続く大半の土蜘蛛は、ほとんどが火の国の住人であった。
一応ヤマメも、古い姿の幻想郷へ辿り着く前、この黒谷の大蜘蛛の存在は耳にしていた。だが火の国に帰った際、このモノについて古老に尋ねてみたところ、彼らからも「知らぬ」との答えが返るばかりだったのだ。
「私でも知ってるのに、ヤマメ達が知らないっての?」
不意にパルスィが声を上げ、次いで彼女は「然知った」と口を押さえる。
「パルさんや。舞や詩吟を披露してるんじゃないし、気にしなさんな」
僅かも気を害した様子も無く、ヤマメは折角だからとパルスィの話を促す。
「いや、鬼も居る手前だからさ」
パルスィが彼らを一瞥し、最後に勇儀と目線を合わせると、勇儀は少し驚いた風にしてから、にへらと力の抜けた笑い顔を浮かべる。どうでもいいらしい。
「だってその大蜘蛛って葛城(かつらぎ)山の、源頼光(みなもとのよりみつ)に討たれたって奴でしょ。私もほら、色々あったけど、頼光の郎党の綱(つな)に討たれた、って事になってるし――」
今の言い方では橋姫は奴らに討たれたのではないのか、これは初耳だ一大事だと、土蜘蛛と鬼が揃ってざわめき声を上げると、パルスィは目を光らせてこれを黙らせる。
「――なってるし、その周りの話は知ってるのよ。そいつの正体は大和国(やまとのくに:奈良県)葛城山の一言主(ひとことぬし)。ヤマメ達とは別の起源を持った土蜘蛛よ」
話の脱線を自覚し、自分の番はこれで終わりと、パルスィは口をつぐむ。
「んー、そんなんだったっけね、確か。いや、流石は元みやこ住まいだね」
そう言うと、またひとたびと気を取り直してヤマメは続ける。
「我らを討ち果たしたは、にくきかな、あなにくきかな、阿蘇大明神の放った鏃、小碓尊(おうすのみこと:日本武尊)の謀、皇(すめら)の軍が携える椿の木槌なり」
そうした力に抗えずに破れたが、我ら決して下らず。
そう言ったところで、ヤマメは始めの木槌の話に戻る。
「と言うことで出てきました木槌。土蜘蛛への挑発かもってのは、こんなとこね。でもそいつ、今のところウチの誰にも接触したって聞かないし、勘ぐり過ぎかも知れないけれど。それと、ちょっと思い出した事もあるんだけど、話していい?」
否と言う者は無し。幻想郷でも一層隔絶されたここでは、ちょっとした四方山話でも大いに歓迎される模様である。
ただ、否とは唱えなかったが、ここで勇儀が声を上げる。
「火の国、鎮西(ちんぜい:九州)からの縁なら、私も心当たりがあるねぇ」
「よっ、姐さん、待ってましたっ!」
ヤマメがそう囃し立てる必要も無く、場は盛り上がる。これは勇儀直参の鬼達ですら聞いた覚えが無い話らしく、彼らも居住まいを正している。
「とくとお聞きよ皆の衆。
時は平安。鎮西総追捕使、源八郎為朝(ためとも)なる大悪党が鎮西を北へ南へと駆け、京へ戻ってから一敗地にまみれた後の話だ」
ヤマメは覚えのある名を耳にし、興味津々な風だった顔を穏やかな物に変える。
結句、己があの人間の英雄の先(未来)を知ることは叶わなかった。彼は何を思っていたのか。彼がみやこでの戦に打ち勝てば、見る事も叶ったやも知れなかったが、それもままならぬず彼は潰えた。
勇儀の話から、その一端でも知れるかもと期待する。
「みやこでの戦に敗れた鎮西八郎は、伊豆の大島に流される訳だが――」
不意に空気が震えたかと思うと、全くの出し抜けに大音響が場を包み、話は遮られる。
それが収まった後、店内はひと時の静寂を迎え、次には皆口々に「何事か」と大わらわ。
音と共に一度激しく揺れはしたが、続く振動は無く、地震でない事だけは分かった。
店舗も鬼や土蜘蛛が建てた物であるし、造りもしっかりして崩れる様子は無いが、念のために炭を除け、鍋の中身を守るために蓋を被せる。
動揺しているのか冷静なのか、それともみみっちいのか、よく分からない場面である。
勇儀が「外には違いないな」と言うと、鬼はぞろぞろと表に歩み出る。土蜘蛛達は、それに先だって店外へ躍り出ており、こちらの先頭にはヤマメが立つ。
何が起こったのか、土蜘蛛には心当たりがあった。
「確認してなかったけど、炭鉱組ってみんな来てる?」
言いながら、今の面子を確認するヤマメ。
少なくとも新坑道での会同に顔を出していた者の姿は揃っている。
「これで全部じゃないですけど、残りの奴らはいつも通り炭鉱に行ってるはずです」
現地で現場監督に立っていた男が答えた。
それに新規の炭鉱は封印したばかり。では従来の炭鉱で事故ったのか。いずれにしても、土蜘蛛の住まう風穴方面からの爆発だ。発破の量でも間違えたのか。
思いつく限りの言葉を交わしながら、彼ら彼女らはそちらへ駆け出す。
緊急の事態だからと、旧地獄街道の雑踏を飛び越える土蜘蛛達。
街の明かりが尽きる線――橋守不在の境の方から、何かを引きずる影を認めて降下。
「おーい、何があったの!? 人手は足りてる?」
降り立ち、引きずられている物を確認し、ヤマメは一瞬のどを詰まらせる。
戸板に横向きに縛り付けられた土蜘蛛の姿があったが、どう見ても無事とは言い難い。
髪や被服は焦げ、それらの一部は肌に貼り付いている。それら火傷に加えて、何かに切り裂かれた無数の傷も見て取れる。どちらも爆風にやられた物であろう。鮮血の滲んだ包帯と、その節約のため一緒に巻かれた添え木を見るに、骨折もしている模様。
何より、口からは血が溢れ続けている。衝撃波による負傷、爆発事故の証拠だ。
「ヤマメさん。見ての通りです、バカ共が勝手に新しい炭鉱掘りやがって、しょうもない事に試掘程度に掘ってただけで「ドカン」だ、そうですよ」
足を緩めず答えた彼を、ヤマメが連れていた女が助け、戸板を持ち上げる。
まだまだ負傷者が運ばれてくるのは確実。
ヤマメが仲間を引き連れ風穴を上がろうとすると、その背に向けて勇儀の声。
「宵の通りの一つ目鬼の所は駄目だ! あのヤブ、今は地獄に往診に行ってるよ!」
「でもあのオッサン以外、こんな傷診れる奴いませんよ?!」
「私は地霊殿を通して、ヤブが駄目ならいっそ地獄の医者でも連れて来させるように掛け合ってくるよ。あんたは最悪、地上の医者、例の竹林の奴に繋ぎを付けられるように算段しときな。こんなんで同族の数を減らしたかぁ無いだろ?!」
地底のモノが地上へ出る。
一人二人なら、個人的な交流と言うことで妖怪の賢者や天狗も目をつぶってくれようが、集団でとなるとそうはいかない。
怪我をしたからと正直に訴えても、信じるどころか謀だと疑ってかかるのが地上の妖怪達だ。
しかし今は、そんなきらいも振り切らなければならない。
「分かりました。伝手を辿って何とか――」
ヤマメは、勇儀に答えながら視線を走らせた先に見慣れぬ者を認める。
ただ、見慣れはしないがそれは、話でだけならヤマメも知るモノ。粗末な小槌を携えた小鬼、正邪であった。
感想をツイートする
ツイート