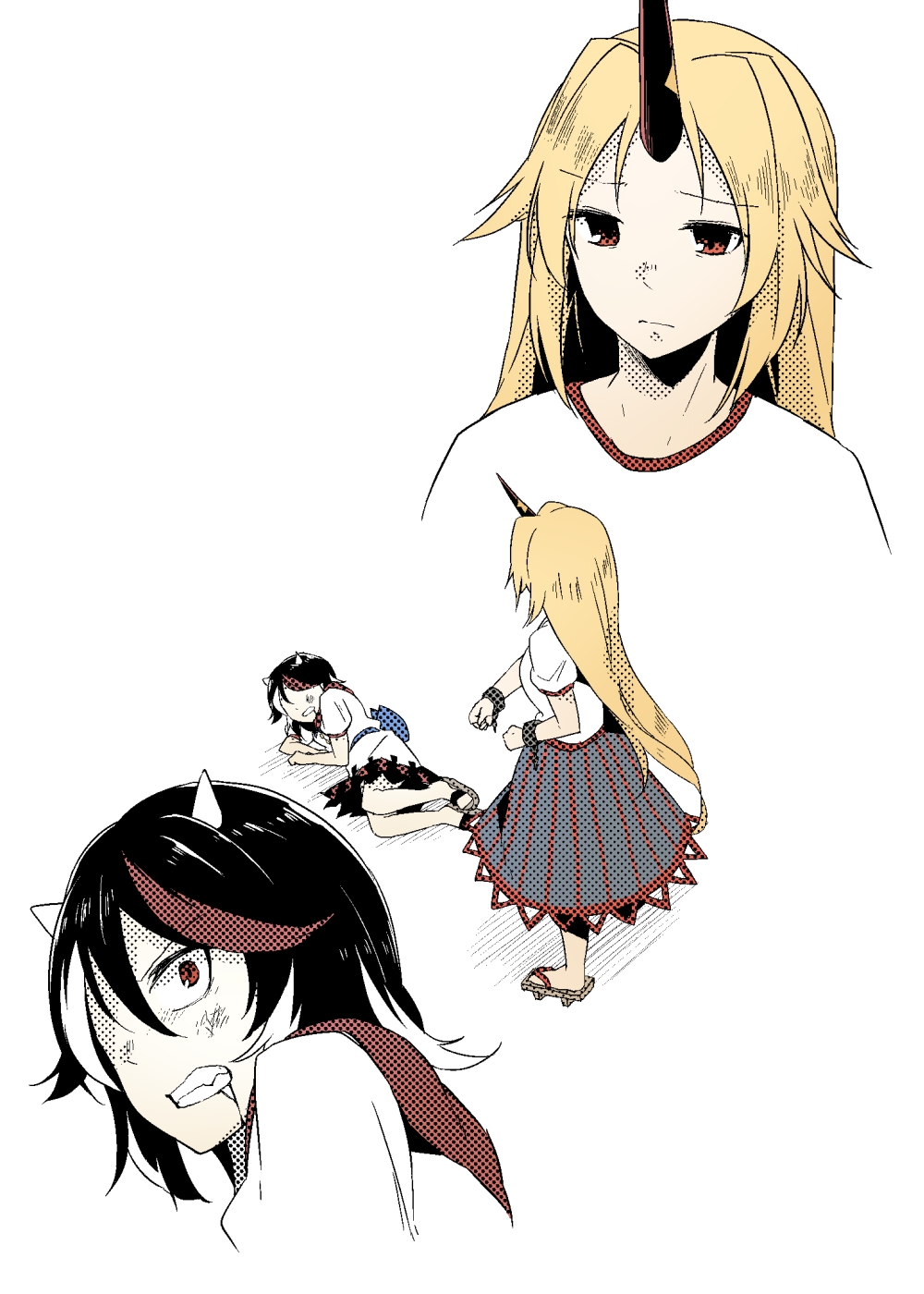楽園の確率~Paradiseshift.第3章 怨霊の聲 怨霊の聲 第7話
所属カテゴリー: 楽園の確率~Paradiseshift.第3章 怨霊の聲
公開日:2017年07月17日 / 最終更新日:2017年07月17日
楽園の確率 ~ Paradise Shift. 第3章
怨霊の聲 第7話
パルスィとの道程は楽しかったが、旧地獄街道へ至れば覿面に足取りも重くなるヤマメ。
同道するパルスィは「やれやれ」と肩をすくめつつ、ヤマメを導く。
「ねぇ、ヤマメ。さっきは言わなかったけどね、今回の是非曲直庁のお使いのお出ましは査定のついでだって言うし、そう縮こまらなくていいと思うわ」
「査定って?」
だるそうに首を巡らせ、そのまま首を傾げて問いかけるヤマメに、パルスィははたとした貌で答える。
「そっか、土蜘蛛には関係なかったっけ。旧地獄の妖怪の中から、見込みのある奴を地獄に雇用しようって試みよ。土蜘蛛は古くから専任の仕事があるものね」
今後はヤマメが「そう言えば」と頷く。
「今回のは定期の雇用、春除目ってとこ。それに何か処罰を加えるつもりなら、事前にこんな通知してこないと思わない?」
「それはどうか、分からないけど。そうなると怖いのは地獄の御使者より姐さんね」
「そっちならいよいよ心配いらないでしょ、今頃は推薦する妖怪をまとめるのに忙しくて。ヤマメ――土蜘蛛を呼んだのだって多分、それどころじゃ無くなるから対応よろしくって話だと思うわよ……ホントはどうか聞いてないけど」
「えー、パルスィ~」
ケレン味たっぷりに泣きつくヤマメをひらりとかわし、心の準備が出来たのならと足を速めるパルスィ。
鬼が何かを語らう場は酒の席と決まっている。
二人はその席が儲けられた『末げん』に到着すると、早速のれんをくぐり戸を開た彼女たちを迎えたのは、居並ぶ人物ではなく違和感であった。
勇儀が動けば取り巻きも同時に動く。そして行く先はいつも満員御礼となるのが常(勇儀が狼藉を禁じている分、店にとっては良い客であろう)。しかし今、店内には彼女と、直参の十人足らずの鬼が居るだけ。
これも査定が近いためかとヤマメは考えつつ、勇儀の前まで歩み出る。
「姐さん。今回は忙しい中また一層のご面倒をかけて、本当に申し訳ありません」
彼女が浮かない貌をしていたため、ヤマメもいつにも増して畏まった声音で挨拶をするが、勇儀は苦笑いを返して着席を促す。
「ちょっと、パルスィもこっちに来なよー」
「これだけ空いてるのにアンタの側に寄る理由は無いわ」
ツンとそっぱを向くパルスィに、天狗の様に鼻が高く、短く太い二本角を生やした赤鬼が近寄り「どうぞ今宵だけは呼ばれとくれんさい」と頭を下げる。
パルスィも彼が直参なのは知っているが、普段は見ない顔の鬼である。この席は、そういう人物も集まっている重要な会合だというのが察せられたし、気のよさそうな彼の言葉は、勇儀と違って断りにくかった。
「すまないね、茂吉どん。さぁさパルスィ、今日は絡んだりしないから」
――どうやって立ち入ったのかは謎だが、この鬼、旧地獄どころか幻想郷全体にもまず姿を現さない人物であるはずだ。これはパルスィやヤマメが思うより、重大事が起こっていると見てもいいのかも知れない――
茂吉どんと呼ばれた鬼は「礼には及ばない」とばかりに手を振るだけ。
「ああ、査定の時は手伝いで来てもらってるんだ。権現格の天狗にも負けないぐらいの事情通だからね。って体さ……」
耳打ちしようとする勇儀に、ヤマメ達と、近くに座っていた鬼も耳を寄せる。
「いつもの奴らなら、あらかた下ノ町に流れちまったよ。こんな状況を是非曲直庁の奴らに見られたら――いや、古明地のにだって何言われるか分からないね」
旧地獄の存在意義とは怨霊の管理、封印。
怨霊は、地上の妖怪にはかなり危険でありながら、現地獄にとってはそこまで労力を割くに至らない、中途半端な危険物。そんな現地獄に変わってこれの管理を負うことで、今の旧地獄の住人はここへの居住を認められ、その名目上の管理者にさとりが立っている。
さとりが処断の権限を持っているのでは無いが、旧都の治安悪化は、管理者としての彼女自身の評価にも響く。これを踏まえれば、お小言ですまない叱責が落とされるであろう。
「それよりも、我ながらこの人望の無さにはガッカリさ」
まんまとやられたと、勇儀は頭を掻く。言葉とは裏腹に悔恨の情は見えない。
「全く話が見えませんよ。一体何が起こったんです!?」
自身への責めなど霞むほどの拙(まず)い事態の生起を悟ったヤマメは、明らかに狼狽する。
「ああ、皆、天邪鬼の甘言に籠絡されたのさ。こんな、短期間どころか、短時間に手下をごっそり持ってかれるとは、まさかとも思わなかったねぇ」
勇儀の自嘲気味な吐息に、直参の鬼達は「不義理者どもが」「先があれば覚えていろと言うものだ」と、怒りを露わにしている。彼らが怒りを表すのは、有象無象の取り巻き達の日常茶飯事のそれとは異なり、危険な事である。そして何より恐ろしいのは、彼らの怒りでは留まらなくなる――勇儀がその力を振るうに至ること。
「その“先”がさ、私らの側にあるのか怪しいからねぇ。いや努力はするよ。そのためには当面、さとりと地獄の御使者をどうにかせにゃいかん訳でね」
勇儀の旧都での立場は、ここの暮らしが始まった時からの自然な流れと、他の有力な鬼の気儘な振る舞いの果てに成り立ったのであるが、それ故に即座に排斥という目もある。
「じゃあ、地獄からの使者が来るまでに、私に出来る事は?」
「いいや、ヤマメにここに来てもらった理由はパルスィに言付けを頼んだとおり、変わらないよ。事故の方は既にあちらさんに知られてるからね。これは旧都のゴタゴタと違って誤魔化しようが無い。あくまで事故についてどう説明するかの算段をしておいて欲しい」
件の炭鉱については、里としてもヤマメ自身も新規開拓には消極的な方針でもあったし、里として問題とされるのは事故を起こした当事者らへの管理責任であろう。
事故自体の責任も、当事者個人に帰させるか、それか土蜘蛛を組織と見なして全体でそれを負うのかは、土蜘蛛の側では決められまい。
「分かりました。里の方でも、やらかした奴らから話は聞き始めてますし。対応に必要な調書が必要なら、御使者が来るまでにまとめられるとも思います。他は?」
「いや、あんたに任せたいのはそこまでさ」
用件は意外とあっさり終わった。ならばと席を立つヤマメを、パルスィが引き留める。
「ねえ勇儀。さっきヤマメにも話したんだけどさ、旧地獄って今、うるさくない?」
「ん、何のこと?」
「なんて言ったらいいか言葉が浮かばないんだけど、嫉妬とよく絡みつく、怨嗟の呻きとか、そういう風な声が、旧都どころか旧地獄全般に充満してるの」
「……何それ?」
やはり知らなかったかとパルスィは頭を振る。
大半の鬼はそれを生み出す側であり、その中で暮らすことに慣れきっている。聞こえなくても仕方が無い。ここで、その大半に当てはまらない鬼が声を上げる。
「そう言えば、どうもいかん感じがすると思ってただが」
「そうかい、茂吉どんにも分かるぐらいなのか」
普段はこちらに居ない茂吉鬼には、それがよく分かるらしい。
「てことは、だ。これ――」
「古明地さんには当然、視えているでしょうね。あ、ちなみに出所は下ノ町みたい」
第三の目で他者の心を“視る(聞く)”のが専門の覚妖怪である。いくら在所が旧地獄の奥であるとは言え、橋姫どころか鬼にまで感じられるそれが、見透せない理由がない。
「あー……詰んだかな、こりゃ」
既にさとりには知られていると考えて間違いない。
己が任せられた旧都で、陰に日向に、二重三重にここまで事が起きてはどんな責め句が飛び出すことであろうかと、さしもの勇儀も頭を垂れるのだった。
これはいよいよ拙い方向に話が進んでいないかと、三人の天狗は事態の推移をまとめながら考える。
正邪による勇儀の手下の切り崩しが易々と済んだのも、あれだけの力を示せば当然だと言えよう。何より今回の取材の初動、はたての念写した蜘蛛らしき姿。あれが本性を現した土蜘蛛の姿である懸念が益々高まった。
「一気にきな臭くなってきたわね……」
「どうすんのよ、これ」
どうしろと言われても、今の取材行為を正式な調査に切り替えると妖怪の山に奏上するぐらいしか、打てる策は無い。その手前にやるべき以上の事は、文も既にやっている。
後のシナリオもいくらか想像はつくが、有力であろうと考えられるのは――
「ふと思い出したんですが、打ち出の小槌の効果って刹那的じゃなかったでしたっけ?」
これは正しく泡沫(うたかた)の夢である。
打ち出の小槌の力で以て、一生使い切れないほどの金銀財宝を出してみても、それは宵を越せば全て消え失せるという。宵越しの金は持たないとは刹那主義者の物言いだが、打ち出の小槌で顕現された物である限りはどのみち変わらない。
「ええ、伝承ではそうなってます」
――これは考え得るシナリオの、担保の一つでもある。
「それマ!? じゃあ天邪鬼が治した土蜘蛛はどうなっちゃうのよ!」
「意外ですね、はたてが鬼の道具の心配をするなんて」
少しばかり含めて文が言うが、はたてはそれどころで無い様子。
「いやさ、それってアイツに時限爆弾式の人質取られてるようなもんじゃん!」
そういう事だ。
「その前に、ヤマメ自身は天邪鬼に頼み込んで同胞を治癒して貰ったという負い目があります。理由は何にせよ、土蜘蛛が額ずいたんですよ。その行為の上に大変な借りを作っています。もし味方しろなどと言われたら、断れるかどうか。あと、椛が言ったのは伝承上の話ですが、効果のコントロールは利くと見ていいでしょう」
「では時限人質方式は、いざと言う時の切り札にするかも知れませんね」
そうなれば、死にたくない土蜘蛛は、同胞を死なせたくない彼らは、己の意思をねじ曲げながら正邪の命令を聞き続けるかも知れない。
文はふと思う。己はこれまでこの様に考えたが、ヤマメはどうなのかと。
「土蜘蛛、どう出る……」
天上から知恵が差し出されることなど彼女は望むまい。手を差し伸べるなど尚のこと。
今はただ、見守るしか無い。
∴
幾日か経ち、是非曲直庁の査定を待つ前夜となった旧地獄。
昼夜の別なく賑わう旧地獄街道も、既に掃き清められ、清潔な様子である。屑拾いが生業として成り立っているため、雑然とした通りではあっても、普段もそんなに汚くはない。
こちらの静かな様子はしかし、人通りの減少が一つの原因でもある。少なくない数の旧都の妖怪が、スラムである下ノ町に集っているのだ。
その下ノ町。
元からのこちらの住人に今は旧都からの流入者も加わり、地上であれば山合の平野と言った風な鳥辺野は、大小様々な妖怪であふれかえっている。
その狭苦しい平野の中央では、鬼哭の声もいよいよと高く上がっていた。
元の住人がその核であり、怨霊と混じった彼らは祭壇を囲うかの様に、中心から一定の距離を取って円を描いている。
その目に見えぬ祭壇に座するのは、盲目の妖怪、田道間である。
目の見えぬ彼にこそ、目に映らぬモノが見えていた。
鬼哭を上げるモノの本性、彼らが請い願う事、そして怨霊の聲。
「ははは、こんなに集まるとは思わなかったわな。のお正邪よ」
「集まって当たり前だろ。見えず、聞こえないモノこそおっかないのは、妖怪も人間も変わらない。そして今は、これが逆転してる」
人が闇を恐れるのは、地鳴りに怯えるのは、潜在的に生存を脅かす存在を忌避するためだ。妖は闇を恐れないが、その耳に届かない怨霊の怨嗟は、知覚よりも先にその魂に染みつき、やがてここの住人のようになる。それは生物なら死と同義とされる、恐れるべき事。
ただうるさいだけならば、耳を塞げばよい。それができなかった者達こそ、声に冒されそれと一体となり、畏れを忘れるのだ。ここに集ったモノ達のように。
逆に言えば、それらの声が腹に響かないモノは、乗り越える事が出来るのであろう。
覚妖怪や橋姫がそうであるように、あるいはそれらの聲が意味を成さない妖獣が怨霊を食らってしまうように。もしくは盲いて、怨霊の聲にまで耳を傾けるに至った、彼の様に。
「しっかし、爺さんが小槌の力に限界があるのを教えてくれなきゃ、無駄足になるところだったな。全部の怨霊を束ねてたらどれだけかかっていたことか」
「だろう。事を起こすに適した怨霊を束ねれば、こんなものよ」
小槌を使った反逆の企みは正邪の物であったが、これだけの短時間で実現せしめたのは、田道間の知恵による所であった。
――天狗でも彼に匹敵する知恵と覚悟を持つ者、どれだけ居る者か――
「で、覚悟は良いかな?」
「今更何を。ようやく復讐の機会を得たのだ、この老いぼれ、もう何を迷うことなど無い。ここに集いたる叛逆の怨霊の聲、今こそこの身に依らせ、想念ごと世の回天を顕現せん」
光を映さぬ目をカッと見開いて田道間が声を上げると、鬼哭は鳥辺野から溢れ天井にも木霊する。
「では『帰神(かむがかり)の法』これより執り行う」
帰神の法とは、『幽齋の法』とも呼ばれる法である。これはふつう神殿宮社にて天神地祇を奉るを『顕齋の法』と言うのに対し、霊を以て霊に対する法であるからだ。
――顕と幽の別、顕幽の論については極めて込み入った論述が必要なためここでは割愛するが、彼らが行おうとしている法、隠世(かくりょ)に在る者を顕界に降ろすと言う意味においてはいずれにしても大差無い――
帰神のなかにも幽顕があり、幽の帰神というのは、本人も気付かないうちに霊境に入り、霊感を得ることを言う。これに対するのが顕の帰神、ふつうに言う神がかりの事で、こちらは神の憑(よ)り坐(ま)したことは、本人にも周りにも明瞭に見て取れる。
今、後者を為せるのは田道間か正邪のみとなるが、先ほどからの会話から察するに、それらの憑坐(よりまし)となるのは彼であろう。
しかし延々とこの地底で過ごしてきた田道間自身には、この法についての資質は無いはず。ではどうするつもりか。
ひと言に帰神の法、その幽顕の法と称したが、その内にもまたそれぞれに、自感法、他感法の別がある。
自感法は、巫女がその身に神を降ろす行為などが分かり易い。導入には舞などからのトランス状態、あるいは逆に精神統一からの顕幽一体が主である。
片や他感法とは、神を降ろす者と憑坐とを別にする法。彼らが執り行おうとしているのはこちらであろう。
そもそも他感法には審神者(さにわ)がおり、霊媒たる神主がおり、正式には弦楽を以て神霊の来格を乞い、審神者が伺いを立てるのである。
怨霊の前に立つのは、天邪鬼とひょうすべ。およそ儀式に必要な物など、ここには無い。だが打ち出の小槌の存在で、これら全てを事足りさせるのが叶う。
唯一正邪に必要であったのは、霊媒、憑坐――田道間だ。
旧地獄で彼の他に適任者がいるとすれば、これは先ほどの怨霊の聲を聴けるモノと同じく、覚妖怪と橋姫ぐらいだが、彼女らが天邪鬼に協力するとは今以て考えられない。そして、始めから鬼の助力があれば、彼女もこうは回りくどいことをしなかったであろう。
「はっはっはっ! では始めようか、爺さん! 怨霊共!」
正邪が笑い声を張り上げ、打ち出の小槌を一振りすると、まず六弦の琴が宙に顕れ、次に自然のままの形を持つ石笛が顕れる。
先に音を鳴らしたのは後に顕れた石笛だった。
清澄な音を鳴らす石笛に、平野に溢れるモノ達も正邪も、程度の差はあれど苦悶に近い貌を浮かべる。それは本来魔払いの音、当然の反応だ。
しかし石笛の音は止まず、そこへ琴が加わる。それらは心魂を集め、ふるわす楽。嫌でも鳴らさなければ儀式は進まないのだ。
「くそっ忌々しい……
かけまくもあやにかしこきかしこみ
いちごんに伏して奉(まお)さく
いみじからずも地に伏すわれらかれらに
大義大業を為させたもうに――」
その詩、祝詞の元で、鬼哭の聲は激しく、やがて一体となってゆく。
もはや止まらない。
田道間を核として、鬼すらも平伏せしめる妖が顕現しようとしている。
一揃いの思いを持つ、怨霊の聲の中で。
「――打ち出の小槌よ!」
正邪がそれを激しく打ち振るうと、願いは叶えられた。
∴
旧地獄全体に波及する異変を知ったところで、己に何が出来たものか。
ヤマメは明日の事故調査に先立って、事故当事者達を引き連れつつ、いつも通りに旧地獄街道を行く。異変を頭の隅に追いやりながら。
「ヤマメさん、その、ここはもっと殊勝にしといた方がいいと思うんで、俺らは……」
「前にも言ったでしょ、大丈夫だって。それに今は姐さん達も、誰が登用されてもいいようにって前祝いしてるんだし。私達もお呼ばれだよ」
勇儀の取り巻き以外にも獄卒候補は多く居る。そして候補となるような者は、地獄の仕事に適した、怨霊の聲に負けない壮健な心身の持ち主である。当然ながら、今旧地獄を覆う異変には大きな影響を受けてはいない。
勇儀は直参の者達と、査定の候補者を集めて『末げん』にて一席を設けているとの事。
そう言えば最近は、ひいきのはずの『どん底』から足が遠ざかっているなと、ヤマメは思い返す。最初は満席だからとの由でのキャンセルだったが、その後は違う。そう、思い返せば正邪が訪れてから、一度もそちらに足を運んでいない。
旧地獄街道沿いではあるので、どうしても店の前は通るのだ。だのに。
ヤマメが考え込んでいると、連れ立つ土蜘蛛の一人が困惑気味の声音で彼女を呼ぶ。
「ヤマメさん、あれ誰です?」
往来に堂々と経つ、剃り上げた頭の大男。十斤もありそうな穂を持つ矛を手に仁王立ちする様は上代の兵士のようであるが、纏うのは短甲などではなく蓑である。携えた矛は総身が鋼らしく、炎に照らされた柄までも鈍色に輝いていた。
土蜘蛛達には見覚えの無い人物。だが、ヤマメだけがその姿に目を見開き、次にその名を確かに口にする。
「田道間、様……!?」
他の土蜘蛛も揃って驚く。
鬼にも負けぬ逞しい手足、屈強という言葉をそのまま表したかのような立ち姿。その上にあるのも眼光鋭い若々しい男の相貌であるが、そこには確かに彼の面影があった。
何よりそれは、古い時代の筑前国で、ヤマノメと共に人間の英雄の前に立ちはだかった、ひょうずの長の姿であったのだ。
「はは、本当に、しばらくぶりになってしまったな。どうかな、天狗の言葉を借りれば、いめちぇんという奴だ」
ヤマメ以下土蜘蛛は何をどう答えていいか分からず、立ち尽くす。
「まあ驚くのも無理は無い。どうだ、久しぶりに『どん底』で一杯」
矛の鞘を確認し、それを倒してからそちらに爪先を向ける彼に、ヤマメは先約を告げる。
「すいません田道間様。実は私達、姐さんに呼ばれてまして――」
「ああ、知っておるよ」
不意に、辻から軒下から、包囲する形で気配が迫る。土蜘蛛達もそれに気付いて隊形を整えるが、これをヤマメは手で制する。
「正邪殿のお誘いだ。嫌とは言うまい?」
ヤマメは天井を仰ぐ。断る術など無いと悟ったのだ。
居酒屋『どん底』の様子は、一見するといつも通りの様子だった。
勇儀の取り巻きにいつもの客、店内の装いも変わらない。ただ取り巻きはいてもその中心人物が違う。そこには今、正邪が居座っていた。
「先日はお世話になったね。鬼人さん」
「正邪って呼びなよ。なんなら正邪様でもいいよ」
ニッと乱杭歯を覗かせて彼女は笑う。悪しく上に立つ者、他者を見下す者の嘲笑の笑みだ。明らかな挑発にも、ヤマメは静かに応じる。
「そう、じゃあ正邪。一体何を企んでいるのか聞かせて。田道間様のあの様子は? 下ノ町で何をしてたの?」
「あれか、地上侵攻の最終兵器だ。凄いぞ、叛逆の怨霊を集い纏わせたらああなった」
「地上侵攻……!」
諦めた訳では無かったのか。この地底で大人しく暮らす気など、やはりこの妖には無かったのだ。
(コイツはそういう妖怪だと、知ってるじゃないか……)
そうだ、私達は知っていたではないか。
これが争乱と混沌を招来する、叛逆の徒だと。
ヤマメは、それを知りつつここまで正邪を放置していたのを悔いる。自身は、勇儀のような責を担う者とは違う。しかし僅かなりとも、天邪鬼というモノを知っていたのに、と。
「そこでだ、あんたには直接持ちかけてなかったんだけど、どうだい? 土蜘蛛も私と手を組んで、共に地上支配を目指そうじゃないか!」
今、後ろに立つ彼らを、同胞を救って貰った恩がある。あの時は正邪が「構わない」とは言ったが、未だに借りは返せていない。
元勇儀の取り巻き達の、敵意に満ちた視線は土蜘蛛を囲み、店主の不安そうな眼差しは、ヤマメに問いかける風に向く。
そして田道間の眼光は、ヤマメの心底を視ていた。
どん底での事態などつゆ知らず『末げん』にて土蜘蛛達を待つ勇儀達。
それ自体には特に疑問を持たずに盃を重ねていた彼女であったが、一人の人物の来訪を以てそれは終わる。
引き戸が激しく開かれ、勢い余って桟から外れるが、それも無視してドカドカと勇儀に歩み寄るパルスィ。
「ちょっと勇儀! 暢気に呑んでる場合!?」
「おや、珍しいじゃないか、パルスィ」
パルスィは更に怒り、勇儀自慢の星熊盃を取り上げて、残っていた中身を飲み干す。
「おっ、間接接吻」
「やかましい!」
直参の鬼達が揃ってパルスィをなだめにかかると、彼女はにわか赤くなる顔色と比例して、落ち着いた様子になってゆく。
「さてもその様子だと、役者は揃ったかね」
「役者?」
「天邪鬼が、ヤマメに接触して来たんじゃないのかい?」
「知ってたの?」
パルスィの驚きに、勇儀は少し寂しそうな貌で答える。
「あんたが来て知った。策を弄するのは嫌いだし苦手だけど、そういうのが必要な時も、得意な人もいるからね。なあ、古明地の」
「ええ、そうですね」
第三の目の視線を右へ左へと走査させ、気怠そうな様子で答えたのは、古明地さとりだった。普段から眠そうな目つきだが、具合の悪さは旧地獄に満ちる怨嗟の声が原因であろうとは、好まないながらもそれを糧とするパルスィにも察せられた。
あれだけの怨嗟の声、やはり悟られぬ訳はなかったか。パルスィが驚きつつも事の収集への見通しに期待を高めていると、更に一人、見慣れない人物が口を開く。
「此度の件、旧地獄の面々には特に罪を問いませんが、私の処断は邪魔しないで下さい。貴方の求めに応じて、獄卒達のローテーションまで崩して来たんですから」
肩まで伸びた緑髪を揺らす女。法服に似た色合いの朝服を纏い、手には笏を持っている。見れば店の奥は、似たような装いの者達で埋まっていた。
それら奥に並ぶ者達は、一様に梵字が書かれた白布を顔の前に下ろし、酒には一切見向きもしていない。
紛れもなく地獄の使者の一団、それが前倒しに訪れたのだとパルスィは考えた。
「じゃあ、嘘つき退治に行きますかね!」
「星熊童子。重ねて言っておきますが、私が罪に問わないとしたのは、旧地獄の者だけです。もしそこから外れようとする者がいれば……分かっていますね」
有象無象の取り巻きなどはどうとでも、現在進行形の話ならば、それは土蜘蛛――ヤマメを対照にした言葉であろう。
先ほどからの発言に、彼女は地獄の官人でもかなり高位の官僚であろうかとパルスィは思った。無論、この様な事態に当たるには、それなりの人物が必要であるが。
「ええ、承知してますよ。閻魔(えんま)様」
閻魔。その言葉はパルスィにも予想外だった。
この度訪れたのは、是非曲直庁の十王直轄の官僚で、その支部である幻想郷(ザナドゥ)の地獄の最高責任者。閻魔(ヤマ)、四季映姫であった。
ヤマメは決断を迫られていた。
正邪への借りだけならばまだ、断る余地もあった。しかしヤマメを悩ませるのは、田道間の存在である。
同胞と同じぐらいに深い彼との縁が、ヤマメを縛っている。
同じく鎮西の出ではあるが、彼は彼の同胞と離れ、ひょうすべ一族の中で唯一ここに移り住んだ人物である。
土蜘蛛達は安住の地を求めてこちらへ移ったが、彼は違う。彼の一族は既に筑前、太宰府に安住の地を得て久しかった。彼はそれを捨ててまでこちらに来たのだ。
それは古い頃のヤマノメへの恩義に応え、ヤマメを助けるための行いだった。
二人の間には、どちらがどれだけ貸しを、借りをなどと言う気持ちは無い。共通した一人の人物が繋いだ縁から、今に至るまでの運命共同体だ。
「田道間様、一つ聞いていい?」
「納得いくまで、いくらでも」
普段のようにゆるゆるとではなく、升で一合グイッとあおり、田道間は問いを待つ。
「私はどうすればいい?」
「好きにすればいい」
「どうすれば良いか分からないの。ずっと、何も考えずに生きてきたから。ここにどうやって辿り着いたのかすら、もう、覚えてない。パルスィにも言われたけど、私はずっと虚ろなまま過ごして来たんだと思う。誰かさんをなぞって」
同胞の前に立って戦い続け、やがて堕とされた古の土蜘蛛を、ヤマメは思い出す。彼女呉れたまぼろしの記憶より、己の思い出がずっと希薄なのも。
田道間はヤマメの目をジッと見据えてから、新たに注がれた酒も飲み干す。
「ならば、なぞれば良い。お主は立派にそう勤めてきた。そして誇れ、進め、今やお主は御前よりも先に居るのだ。心に、従え」
正邪が怪訝な貌を向けるのにも構わず、田道間は言い募る。
「我らは征く。それは変わらん」
彼の中に渦巻く意思は、決して揺るぐ様子を見せない。この後は従前の通り、軍勢を率いて地上に這い出る事であろう。
「ったく、ゴチャゴチャと面倒な奴だね。土蜘蛛よ、一つだけ教えてやる。後ろのお仲間にかけてやった小槌の癒術だけどな、アレ、いますぐ解くことも出来るんだよ?」
これは正邪の切り札であったはずだ。しかし彼女は早々にこれを切った。
「正邪殿、それはまだ言い出す予定ではなかったのでは?」
「迷ってんなら後押ししてやるだけだって。なあ、そいつらが生きるも死ぬも、いや、死ななくても今すぐにズタボロになるのも、私の胸先三寸なんだよねぇ」
天邪鬼が偽り事ばかりを述べる妖なのは、ヤマメもよく知っている。今の言葉、正邪だけが放った物ならすぐに疑ってかかるところだったが、田道間の言葉を聞く限りそれは真実である。
しかし、惑わない。
「みんな、恨むなら恨んで……」
その呟きの意味を後ろに立つ彼ら、彼女らは当然理解する。
連れられた七人の反応はそれぞれだ。怯える者、呆ける者、地獄の処断よりはと覚悟する者。皆、死や苦痛に恐怖するがしかし、誰一人、ヤマメにも正邪にも命乞いはしない。
「お前に受けた恩は、ここで返そう。私達は、断る!」
「は? ……はぁ?!」
ヤマメの返事に、正邪は素っ頓狂な声を上げ、取り巻き達は一同に立ち上がる。
田道間は微笑みを浮かべ、店主に今日のオススメを尋ねる。
「ほれ、この通りよ。天邪鬼よりも御しがたく、度し難いのよ、土蜘蛛は」
「はあ、全くで」
そんな会話など正邪の耳には入らない。わなわなと身を震わし、彼女は叫ぶ。
「はっはぁ! 上等だ! 賤民共が思い知れ!!」
彼女がそう願い(の解除)を込め、小槌を振るおうとした時であった。
「パルスィ任せた!」
戸が荒々しく開かれ、緑眼を輝かせた蛇が宙を泳ぐ。蛇は迷う事無く小槌に食いつき、正邪の手中にあったそれを易々と奪い取った。
「なっ!?」
まず姿を現したのは当然勇儀、そしてパルスィ。後ろには直参や、映姫達も控えている。
「貴様……おい勇儀さんよ、お前は何とも思わないのかい!? こいつ私の恩を仇で返そうとしやがったんだぞ、それにこのジジイにも借りがあるんだろうが! ここじゃそういう仁義が物を言うんじゃないのかい?!」
「うるさいね、あんたが仁義を云々するんじゃないよ。それにその借りってのも、あんたのマッチポンプなんじゃないのかい?」
勇儀は手近に居た女の土蜘蛛を手招きすると、さとりの前に送り出す。
「ふむ……どうも事故当時の思考が、おかしいですね……」
「はっ、何を言ってるんだ? お前が心を読めるって言ったところで、それはお前にしか分からないだろうが。都合の良い話でっち上げようとしてるのはそっちじゃないのか?」
「私は公正な立場で視てるんですよ。あくまで事故調査の手伝いですから。それに、私の能力を疑うなら、第三者の目にも触れられる物をご覧に入れましょう」
さとりは映姫の、帽子から降ろした薄布の向こうの目と視線を重ね、頷き合う。
「本来は、亡者を裁くための閻魔王庁の備品なのですが、今日は特別ですよ」
映姫が手の所作だけで従者に指示すると、彼らは布に覆われた重々しい板を運び込み、それを立てかける。
帳らしき布を取り払うと、そこには六尺ほどもある楕円形の姿見がそびえていた。
「浄玻璃の鏡、本来は亡者の生前の行いを、真実を晒すための宝具です」
正邪の顔が青ざめる。
あの事故の裏で何が起こったのかは、もはや見るべくも無い。
「いや、そりゃ私じゃない……私は、あいつの言う通りにやったんだ! あのジジイだ、あのジジイが地底と地上の妖怪全部に復讐してやるためだって、そのためには先ず土蜘蛛をはめれてやればいいって、私は言われた通りにしたんだ!」
それは正邪の知る限りの事実であり、彼女の心を読めば、浄玻璃の鏡で映せば、その通りであったと分かる。
「天邪鬼が、珍しい。命が惜しいからか随分正直に白状しますね。でも、誰がそれを信じます?」
迫る映姫にたじろぐ正邪に、更に勇儀が言う。
「それにだ、あの爺様はずっと昔のヤマメへの恩と借りに報いるため、進んでこっちに来たんだよ。静かな終の棲家まで捨ててね」
それは彼自身の鎮魂と懺悔でもあったのだろう。
「はぁ? そんなの私が知るかよ! じゃあ読めばいい、映し出せばいい、あのジジイが私に何を吹き込んだのか!」
正邪は叫んで、己に策を授けた張本人に向き直るが、そこには重々しい鋼の矛が立てかけられているだけ。彼の姿などどこにも無かった。
「くそっ逃げやがったなジジイ! でも無駄だ、お前に憑り坐した怨霊を剥がせば――」
周囲の上下を全て逆転させ、その場に居る全員が文字通り浮き足立つ。正邪は僅かな隙を逃さずパルスィに組み付き、すぐに小槌を奪い取った。
「小槌よ――」
土蜘蛛達がいち早く体勢を立て直し、まず勇儀を助けていた。
「無駄だ……!」
その勇儀は、正邪が小槌を振るうより先に、上方へ、即ち地面に彼女を殴り飛ばす。
正邪の能力は覿面に解かれ、固定されていなかった物がまた反転して地面に落ちる。
店内の状況は地震の後より酷い有り様だが、幸いにも怪我を負った者は皆無。殴り飛ばされた正邪以外は。
「無駄なんだよ、天邪鬼」
勇儀の貌は、また酷く寂しげである。
「田道間様、なんでそんな無茶を……」
反転し、鞘を破って屹立する矛にヤマメは語りかける。
彼の姿はもう、この世のどこにも無かった。
∴
「限界だったんでしょう。もとより水界のモノが、それも清い水辺で住むべき河童が、地底にあんな地底に住むなんて無理だったんですよ」
ヤマメ達の代わりに一部始終を視た椛とはたては、その様子だけを伝えた後、衝撃で絶句していた。
唯一、その様子を視ていなかった文だけは冷静そうな素振りを見せているが、心中の動揺が一番大きいのも文だった。
「それが、あれだけの量の怨霊を依らせて、無事で済むはずが無い。もっとも、それも計算の内だったのでしょうけれどね」
「文、計算の内って……」
「彼に依っていた怨霊は、恐らく彼の魂に依り憑いたまま。つまりは道連れですよ。六道輪廻の理から外れた外道に、行く先はありません。潰えれば、そのまま消えるんです」
「怨霊を一掃した上に天邪鬼を追っ払って、一挙両得って事? 自分の命まで使って?!」
「ええ、その通りですよ。と言う訳で、私は今回の件、記事に起こしません、お蔵入りにするつもりです」
人の死などの暗いことを生地にするのを文は嫌う、自殺などはもってのほか。
はたても文のポリシーは承知しているが、ここまで引っ張っておいてお蔵入りというのは、労力を顧みると耐え難い。
「いやでも、折角の一大事、それも解決したみたいなのに……」
「私が記事にしないだけです。はたては好きにすれば良いでしょう」
言って、文は飛び立つ。
伝えるべき事だけ言った今、誰とも言葉を交わしたくなくなったのだ。
己が最も嫌う、誰かのための、迂遠な自殺などという物を目にしては。
∵
旧地獄は一連の事件から解放され、ようやく平静な様子を取り戻しつつあった。
炭鉱で事故を起こした土蜘蛛達は、正邪の能力で思考をねじ曲げられたのがその原因であると判明し、関係する行いは全て無実と判じられた。
勇儀の取り巻き達は辛うじて元の通りに納まったものの、そこには直参の鬼のキツい責めが待っていた。
下ノ町の鬼哭は消えたが、またしばらくすれば、誰かがここに辿り着くのであろうか。
そして這々の体で逃れた正邪は、打ち出の小槌の持ち主と共に地上で事を起こすのだが、それはまた別のお話。
怨霊の聲 第7話
パルスィとの道程は楽しかったが、旧地獄街道へ至れば覿面に足取りも重くなるヤマメ。
同道するパルスィは「やれやれ」と肩をすくめつつ、ヤマメを導く。
「ねぇ、ヤマメ。さっきは言わなかったけどね、今回の是非曲直庁のお使いのお出ましは査定のついでだって言うし、そう縮こまらなくていいと思うわ」
「査定って?」
だるそうに首を巡らせ、そのまま首を傾げて問いかけるヤマメに、パルスィははたとした貌で答える。
「そっか、土蜘蛛には関係なかったっけ。旧地獄の妖怪の中から、見込みのある奴を地獄に雇用しようって試みよ。土蜘蛛は古くから専任の仕事があるものね」
今後はヤマメが「そう言えば」と頷く。
「今回のは定期の雇用、春除目ってとこ。それに何か処罰を加えるつもりなら、事前にこんな通知してこないと思わない?」
「それはどうか、分からないけど。そうなると怖いのは地獄の御使者より姐さんね」
「そっちならいよいよ心配いらないでしょ、今頃は推薦する妖怪をまとめるのに忙しくて。ヤマメ――土蜘蛛を呼んだのだって多分、それどころじゃ無くなるから対応よろしくって話だと思うわよ……ホントはどうか聞いてないけど」
「えー、パルスィ~」
ケレン味たっぷりに泣きつくヤマメをひらりとかわし、心の準備が出来たのならと足を速めるパルスィ。
鬼が何かを語らう場は酒の席と決まっている。
二人はその席が儲けられた『末げん』に到着すると、早速のれんをくぐり戸を開た彼女たちを迎えたのは、居並ぶ人物ではなく違和感であった。
勇儀が動けば取り巻きも同時に動く。そして行く先はいつも満員御礼となるのが常(勇儀が狼藉を禁じている分、店にとっては良い客であろう)。しかし今、店内には彼女と、直参の十人足らずの鬼が居るだけ。
これも査定が近いためかとヤマメは考えつつ、勇儀の前まで歩み出る。
「姐さん。今回は忙しい中また一層のご面倒をかけて、本当に申し訳ありません」
彼女が浮かない貌をしていたため、ヤマメもいつにも増して畏まった声音で挨拶をするが、勇儀は苦笑いを返して着席を促す。
「ちょっと、パルスィもこっちに来なよー」
「これだけ空いてるのにアンタの側に寄る理由は無いわ」
ツンとそっぱを向くパルスィに、天狗の様に鼻が高く、短く太い二本角を生やした赤鬼が近寄り「どうぞ今宵だけは呼ばれとくれんさい」と頭を下げる。
パルスィも彼が直参なのは知っているが、普段は見ない顔の鬼である。この席は、そういう人物も集まっている重要な会合だというのが察せられたし、気のよさそうな彼の言葉は、勇儀と違って断りにくかった。
「すまないね、茂吉どん。さぁさパルスィ、今日は絡んだりしないから」
――どうやって立ち入ったのかは謎だが、この鬼、旧地獄どころか幻想郷全体にもまず姿を現さない人物であるはずだ。これはパルスィやヤマメが思うより、重大事が起こっていると見てもいいのかも知れない――
茂吉どんと呼ばれた鬼は「礼には及ばない」とばかりに手を振るだけ。
「ああ、査定の時は手伝いで来てもらってるんだ。権現格の天狗にも負けないぐらいの事情通だからね。って体さ……」
耳打ちしようとする勇儀に、ヤマメ達と、近くに座っていた鬼も耳を寄せる。
「いつもの奴らなら、あらかた下ノ町に流れちまったよ。こんな状況を是非曲直庁の奴らに見られたら――いや、古明地のにだって何言われるか分からないね」
旧地獄の存在意義とは怨霊の管理、封印。
怨霊は、地上の妖怪にはかなり危険でありながら、現地獄にとってはそこまで労力を割くに至らない、中途半端な危険物。そんな現地獄に変わってこれの管理を負うことで、今の旧地獄の住人はここへの居住を認められ、その名目上の管理者にさとりが立っている。
さとりが処断の権限を持っているのでは無いが、旧都の治安悪化は、管理者としての彼女自身の評価にも響く。これを踏まえれば、お小言ですまない叱責が落とされるであろう。
「それよりも、我ながらこの人望の無さにはガッカリさ」
まんまとやられたと、勇儀は頭を掻く。言葉とは裏腹に悔恨の情は見えない。
「全く話が見えませんよ。一体何が起こったんです!?」
自身への責めなど霞むほどの拙(まず)い事態の生起を悟ったヤマメは、明らかに狼狽する。
「ああ、皆、天邪鬼の甘言に籠絡されたのさ。こんな、短期間どころか、短時間に手下をごっそり持ってかれるとは、まさかとも思わなかったねぇ」
勇儀の自嘲気味な吐息に、直参の鬼達は「不義理者どもが」「先があれば覚えていろと言うものだ」と、怒りを露わにしている。彼らが怒りを表すのは、有象無象の取り巻き達の日常茶飯事のそれとは異なり、危険な事である。そして何より恐ろしいのは、彼らの怒りでは留まらなくなる――勇儀がその力を振るうに至ること。
「その“先”がさ、私らの側にあるのか怪しいからねぇ。いや努力はするよ。そのためには当面、さとりと地獄の御使者をどうにかせにゃいかん訳でね」
勇儀の旧都での立場は、ここの暮らしが始まった時からの自然な流れと、他の有力な鬼の気儘な振る舞いの果てに成り立ったのであるが、それ故に即座に排斥という目もある。
「じゃあ、地獄からの使者が来るまでに、私に出来る事は?」
「いいや、ヤマメにここに来てもらった理由はパルスィに言付けを頼んだとおり、変わらないよ。事故の方は既にあちらさんに知られてるからね。これは旧都のゴタゴタと違って誤魔化しようが無い。あくまで事故についてどう説明するかの算段をしておいて欲しい」
件の炭鉱については、里としてもヤマメ自身も新規開拓には消極的な方針でもあったし、里として問題とされるのは事故を起こした当事者らへの管理責任であろう。
事故自体の責任も、当事者個人に帰させるか、それか土蜘蛛を組織と見なして全体でそれを負うのかは、土蜘蛛の側では決められまい。
「分かりました。里の方でも、やらかした奴らから話は聞き始めてますし。対応に必要な調書が必要なら、御使者が来るまでにまとめられるとも思います。他は?」
「いや、あんたに任せたいのはそこまでさ」
用件は意外とあっさり終わった。ならばと席を立つヤマメを、パルスィが引き留める。
「ねえ勇儀。さっきヤマメにも話したんだけどさ、旧地獄って今、うるさくない?」
「ん、何のこと?」
「なんて言ったらいいか言葉が浮かばないんだけど、嫉妬とよく絡みつく、怨嗟の呻きとか、そういう風な声が、旧都どころか旧地獄全般に充満してるの」
「……何それ?」
やはり知らなかったかとパルスィは頭を振る。
大半の鬼はそれを生み出す側であり、その中で暮らすことに慣れきっている。聞こえなくても仕方が無い。ここで、その大半に当てはまらない鬼が声を上げる。
「そう言えば、どうもいかん感じがすると思ってただが」
「そうかい、茂吉どんにも分かるぐらいなのか」
普段はこちらに居ない茂吉鬼には、それがよく分かるらしい。
「てことは、だ。これ――」
「古明地さんには当然、視えているでしょうね。あ、ちなみに出所は下ノ町みたい」
第三の目で他者の心を“視る(聞く)”のが専門の覚妖怪である。いくら在所が旧地獄の奥であるとは言え、橋姫どころか鬼にまで感じられるそれが、見透せない理由がない。
「あー……詰んだかな、こりゃ」
既にさとりには知られていると考えて間違いない。
己が任せられた旧都で、陰に日向に、二重三重にここまで事が起きてはどんな責め句が飛び出すことであろうかと、さしもの勇儀も頭を垂れるのだった。
これはいよいよ拙い方向に話が進んでいないかと、三人の天狗は事態の推移をまとめながら考える。
正邪による勇儀の手下の切り崩しが易々と済んだのも、あれだけの力を示せば当然だと言えよう。何より今回の取材の初動、はたての念写した蜘蛛らしき姿。あれが本性を現した土蜘蛛の姿である懸念が益々高まった。
「一気にきな臭くなってきたわね……」
「どうすんのよ、これ」
どうしろと言われても、今の取材行為を正式な調査に切り替えると妖怪の山に奏上するぐらいしか、打てる策は無い。その手前にやるべき以上の事は、文も既にやっている。
後のシナリオもいくらか想像はつくが、有力であろうと考えられるのは――
「ふと思い出したんですが、打ち出の小槌の効果って刹那的じゃなかったでしたっけ?」
これは正しく泡沫(うたかた)の夢である。
打ち出の小槌の力で以て、一生使い切れないほどの金銀財宝を出してみても、それは宵を越せば全て消え失せるという。宵越しの金は持たないとは刹那主義者の物言いだが、打ち出の小槌で顕現された物である限りはどのみち変わらない。
「ええ、伝承ではそうなってます」
――これは考え得るシナリオの、担保の一つでもある。
「それマ!? じゃあ天邪鬼が治した土蜘蛛はどうなっちゃうのよ!」
「意外ですね、はたてが鬼の道具の心配をするなんて」
少しばかり含めて文が言うが、はたてはそれどころで無い様子。
「いやさ、それってアイツに時限爆弾式の人質取られてるようなもんじゃん!」
そういう事だ。
「その前に、ヤマメ自身は天邪鬼に頼み込んで同胞を治癒して貰ったという負い目があります。理由は何にせよ、土蜘蛛が額ずいたんですよ。その行為の上に大変な借りを作っています。もし味方しろなどと言われたら、断れるかどうか。あと、椛が言ったのは伝承上の話ですが、効果のコントロールは利くと見ていいでしょう」
「では時限人質方式は、いざと言う時の切り札にするかも知れませんね」
そうなれば、死にたくない土蜘蛛は、同胞を死なせたくない彼らは、己の意思をねじ曲げながら正邪の命令を聞き続けるかも知れない。
文はふと思う。己はこれまでこの様に考えたが、ヤマメはどうなのかと。
「土蜘蛛、どう出る……」
天上から知恵が差し出されることなど彼女は望むまい。手を差し伸べるなど尚のこと。
今はただ、見守るしか無い。
∴
幾日か経ち、是非曲直庁の査定を待つ前夜となった旧地獄。
昼夜の別なく賑わう旧地獄街道も、既に掃き清められ、清潔な様子である。屑拾いが生業として成り立っているため、雑然とした通りではあっても、普段もそんなに汚くはない。
こちらの静かな様子はしかし、人通りの減少が一つの原因でもある。少なくない数の旧都の妖怪が、スラムである下ノ町に集っているのだ。
その下ノ町。
元からのこちらの住人に今は旧都からの流入者も加わり、地上であれば山合の平野と言った風な鳥辺野は、大小様々な妖怪であふれかえっている。
その狭苦しい平野の中央では、鬼哭の声もいよいよと高く上がっていた。
元の住人がその核であり、怨霊と混じった彼らは祭壇を囲うかの様に、中心から一定の距離を取って円を描いている。
その目に見えぬ祭壇に座するのは、盲目の妖怪、田道間である。
目の見えぬ彼にこそ、目に映らぬモノが見えていた。
鬼哭を上げるモノの本性、彼らが請い願う事、そして怨霊の聲。
「ははは、こんなに集まるとは思わなかったわな。のお正邪よ」
「集まって当たり前だろ。見えず、聞こえないモノこそおっかないのは、妖怪も人間も変わらない。そして今は、これが逆転してる」
人が闇を恐れるのは、地鳴りに怯えるのは、潜在的に生存を脅かす存在を忌避するためだ。妖は闇を恐れないが、その耳に届かない怨霊の怨嗟は、知覚よりも先にその魂に染みつき、やがてここの住人のようになる。それは生物なら死と同義とされる、恐れるべき事。
ただうるさいだけならば、耳を塞げばよい。それができなかった者達こそ、声に冒されそれと一体となり、畏れを忘れるのだ。ここに集ったモノ達のように。
逆に言えば、それらの声が腹に響かないモノは、乗り越える事が出来るのであろう。
覚妖怪や橋姫がそうであるように、あるいはそれらの聲が意味を成さない妖獣が怨霊を食らってしまうように。もしくは盲いて、怨霊の聲にまで耳を傾けるに至った、彼の様に。
「しっかし、爺さんが小槌の力に限界があるのを教えてくれなきゃ、無駄足になるところだったな。全部の怨霊を束ねてたらどれだけかかっていたことか」
「だろう。事を起こすに適した怨霊を束ねれば、こんなものよ」
小槌を使った反逆の企みは正邪の物であったが、これだけの短時間で実現せしめたのは、田道間の知恵による所であった。
――天狗でも彼に匹敵する知恵と覚悟を持つ者、どれだけ居る者か――
「で、覚悟は良いかな?」
「今更何を。ようやく復讐の機会を得たのだ、この老いぼれ、もう何を迷うことなど無い。ここに集いたる叛逆の怨霊の聲、今こそこの身に依らせ、想念ごと世の回天を顕現せん」
光を映さぬ目をカッと見開いて田道間が声を上げると、鬼哭は鳥辺野から溢れ天井にも木霊する。
「では『帰神(かむがかり)の法』これより執り行う」
帰神の法とは、『幽齋の法』とも呼ばれる法である。これはふつう神殿宮社にて天神地祇を奉るを『顕齋の法』と言うのに対し、霊を以て霊に対する法であるからだ。
――顕と幽の別、顕幽の論については極めて込み入った論述が必要なためここでは割愛するが、彼らが行おうとしている法、隠世(かくりょ)に在る者を顕界に降ろすと言う意味においてはいずれにしても大差無い――
帰神のなかにも幽顕があり、幽の帰神というのは、本人も気付かないうちに霊境に入り、霊感を得ることを言う。これに対するのが顕の帰神、ふつうに言う神がかりの事で、こちらは神の憑(よ)り坐(ま)したことは、本人にも周りにも明瞭に見て取れる。
今、後者を為せるのは田道間か正邪のみとなるが、先ほどからの会話から察するに、それらの憑坐(よりまし)となるのは彼であろう。
しかし延々とこの地底で過ごしてきた田道間自身には、この法についての資質は無いはず。ではどうするつもりか。
ひと言に帰神の法、その幽顕の法と称したが、その内にもまたそれぞれに、自感法、他感法の別がある。
自感法は、巫女がその身に神を降ろす行為などが分かり易い。導入には舞などからのトランス状態、あるいは逆に精神統一からの顕幽一体が主である。
片や他感法とは、神を降ろす者と憑坐とを別にする法。彼らが執り行おうとしているのはこちらであろう。
そもそも他感法には審神者(さにわ)がおり、霊媒たる神主がおり、正式には弦楽を以て神霊の来格を乞い、審神者が伺いを立てるのである。
怨霊の前に立つのは、天邪鬼とひょうすべ。およそ儀式に必要な物など、ここには無い。だが打ち出の小槌の存在で、これら全てを事足りさせるのが叶う。
唯一正邪に必要であったのは、霊媒、憑坐――田道間だ。
旧地獄で彼の他に適任者がいるとすれば、これは先ほどの怨霊の聲を聴けるモノと同じく、覚妖怪と橋姫ぐらいだが、彼女らが天邪鬼に協力するとは今以て考えられない。そして、始めから鬼の助力があれば、彼女もこうは回りくどいことをしなかったであろう。
「はっはっはっ! では始めようか、爺さん! 怨霊共!」
正邪が笑い声を張り上げ、打ち出の小槌を一振りすると、まず六弦の琴が宙に顕れ、次に自然のままの形を持つ石笛が顕れる。
先に音を鳴らしたのは後に顕れた石笛だった。
清澄な音を鳴らす石笛に、平野に溢れるモノ達も正邪も、程度の差はあれど苦悶に近い貌を浮かべる。それは本来魔払いの音、当然の反応だ。
しかし石笛の音は止まず、そこへ琴が加わる。それらは心魂を集め、ふるわす楽。嫌でも鳴らさなければ儀式は進まないのだ。
「くそっ忌々しい……
かけまくもあやにかしこきかしこみ
いちごんに伏して奉(まお)さく
いみじからずも地に伏すわれらかれらに
大義大業を為させたもうに――」
その詩、祝詞の元で、鬼哭の聲は激しく、やがて一体となってゆく。
もはや止まらない。
田道間を核として、鬼すらも平伏せしめる妖が顕現しようとしている。
一揃いの思いを持つ、怨霊の聲の中で。
「――打ち出の小槌よ!」
正邪がそれを激しく打ち振るうと、願いは叶えられた。
∴
旧地獄全体に波及する異変を知ったところで、己に何が出来たものか。
ヤマメは明日の事故調査に先立って、事故当事者達を引き連れつつ、いつも通りに旧地獄街道を行く。異変を頭の隅に追いやりながら。
「ヤマメさん、その、ここはもっと殊勝にしといた方がいいと思うんで、俺らは……」
「前にも言ったでしょ、大丈夫だって。それに今は姐さん達も、誰が登用されてもいいようにって前祝いしてるんだし。私達もお呼ばれだよ」
勇儀の取り巻き以外にも獄卒候補は多く居る。そして候補となるような者は、地獄の仕事に適した、怨霊の聲に負けない壮健な心身の持ち主である。当然ながら、今旧地獄を覆う異変には大きな影響を受けてはいない。
勇儀は直参の者達と、査定の候補者を集めて『末げん』にて一席を設けているとの事。
そう言えば最近は、ひいきのはずの『どん底』から足が遠ざかっているなと、ヤマメは思い返す。最初は満席だからとの由でのキャンセルだったが、その後は違う。そう、思い返せば正邪が訪れてから、一度もそちらに足を運んでいない。
旧地獄街道沿いではあるので、どうしても店の前は通るのだ。だのに。
ヤマメが考え込んでいると、連れ立つ土蜘蛛の一人が困惑気味の声音で彼女を呼ぶ。
「ヤマメさん、あれ誰です?」
往来に堂々と経つ、剃り上げた頭の大男。十斤もありそうな穂を持つ矛を手に仁王立ちする様は上代の兵士のようであるが、纏うのは短甲などではなく蓑である。携えた矛は総身が鋼らしく、炎に照らされた柄までも鈍色に輝いていた。
土蜘蛛達には見覚えの無い人物。だが、ヤマメだけがその姿に目を見開き、次にその名を確かに口にする。
「田道間、様……!?」
他の土蜘蛛も揃って驚く。
鬼にも負けぬ逞しい手足、屈強という言葉をそのまま表したかのような立ち姿。その上にあるのも眼光鋭い若々しい男の相貌であるが、そこには確かに彼の面影があった。
何よりそれは、古い時代の筑前国で、ヤマノメと共に人間の英雄の前に立ちはだかった、ひょうずの長の姿であったのだ。
「はは、本当に、しばらくぶりになってしまったな。どうかな、天狗の言葉を借りれば、いめちぇんという奴だ」
ヤマメ以下土蜘蛛は何をどう答えていいか分からず、立ち尽くす。
「まあ驚くのも無理は無い。どうだ、久しぶりに『どん底』で一杯」
矛の鞘を確認し、それを倒してからそちらに爪先を向ける彼に、ヤマメは先約を告げる。
「すいません田道間様。実は私達、姐さんに呼ばれてまして――」
「ああ、知っておるよ」
不意に、辻から軒下から、包囲する形で気配が迫る。土蜘蛛達もそれに気付いて隊形を整えるが、これをヤマメは手で制する。
「正邪殿のお誘いだ。嫌とは言うまい?」
ヤマメは天井を仰ぐ。断る術など無いと悟ったのだ。
居酒屋『どん底』の様子は、一見するといつも通りの様子だった。
勇儀の取り巻きにいつもの客、店内の装いも変わらない。ただ取り巻きはいてもその中心人物が違う。そこには今、正邪が居座っていた。
「先日はお世話になったね。鬼人さん」
「正邪って呼びなよ。なんなら正邪様でもいいよ」
ニッと乱杭歯を覗かせて彼女は笑う。悪しく上に立つ者、他者を見下す者の嘲笑の笑みだ。明らかな挑発にも、ヤマメは静かに応じる。
「そう、じゃあ正邪。一体何を企んでいるのか聞かせて。田道間様のあの様子は? 下ノ町で何をしてたの?」
「あれか、地上侵攻の最終兵器だ。凄いぞ、叛逆の怨霊を集い纏わせたらああなった」
「地上侵攻……!」
諦めた訳では無かったのか。この地底で大人しく暮らす気など、やはりこの妖には無かったのだ。
(コイツはそういう妖怪だと、知ってるじゃないか……)
そうだ、私達は知っていたではないか。
これが争乱と混沌を招来する、叛逆の徒だと。
ヤマメは、それを知りつつここまで正邪を放置していたのを悔いる。自身は、勇儀のような責を担う者とは違う。しかし僅かなりとも、天邪鬼というモノを知っていたのに、と。
「そこでだ、あんたには直接持ちかけてなかったんだけど、どうだい? 土蜘蛛も私と手を組んで、共に地上支配を目指そうじゃないか!」
今、後ろに立つ彼らを、同胞を救って貰った恩がある。あの時は正邪が「構わない」とは言ったが、未だに借りは返せていない。
元勇儀の取り巻き達の、敵意に満ちた視線は土蜘蛛を囲み、店主の不安そうな眼差しは、ヤマメに問いかける風に向く。
そして田道間の眼光は、ヤマメの心底を視ていた。
どん底での事態などつゆ知らず『末げん』にて土蜘蛛達を待つ勇儀達。
それ自体には特に疑問を持たずに盃を重ねていた彼女であったが、一人の人物の来訪を以てそれは終わる。
引き戸が激しく開かれ、勢い余って桟から外れるが、それも無視してドカドカと勇儀に歩み寄るパルスィ。
「ちょっと勇儀! 暢気に呑んでる場合!?」
「おや、珍しいじゃないか、パルスィ」
パルスィは更に怒り、勇儀自慢の星熊盃を取り上げて、残っていた中身を飲み干す。
「おっ、間接接吻」
「やかましい!」
直参の鬼達が揃ってパルスィをなだめにかかると、彼女はにわか赤くなる顔色と比例して、落ち着いた様子になってゆく。
「さてもその様子だと、役者は揃ったかね」
「役者?」
「天邪鬼が、ヤマメに接触して来たんじゃないのかい?」
「知ってたの?」
パルスィの驚きに、勇儀は少し寂しそうな貌で答える。
「あんたが来て知った。策を弄するのは嫌いだし苦手だけど、そういうのが必要な時も、得意な人もいるからね。なあ、古明地の」
「ええ、そうですね」
第三の目の視線を右へ左へと走査させ、気怠そうな様子で答えたのは、古明地さとりだった。普段から眠そうな目つきだが、具合の悪さは旧地獄に満ちる怨嗟の声が原因であろうとは、好まないながらもそれを糧とするパルスィにも察せられた。
あれだけの怨嗟の声、やはり悟られぬ訳はなかったか。パルスィが驚きつつも事の収集への見通しに期待を高めていると、更に一人、見慣れない人物が口を開く。
「此度の件、旧地獄の面々には特に罪を問いませんが、私の処断は邪魔しないで下さい。貴方の求めに応じて、獄卒達のローテーションまで崩して来たんですから」
肩まで伸びた緑髪を揺らす女。法服に似た色合いの朝服を纏い、手には笏を持っている。見れば店の奥は、似たような装いの者達で埋まっていた。
それら奥に並ぶ者達は、一様に梵字が書かれた白布を顔の前に下ろし、酒には一切見向きもしていない。
紛れもなく地獄の使者の一団、それが前倒しに訪れたのだとパルスィは考えた。
「じゃあ、嘘つき退治に行きますかね!」
「星熊童子。重ねて言っておきますが、私が罪に問わないとしたのは、旧地獄の者だけです。もしそこから外れようとする者がいれば……分かっていますね」
有象無象の取り巻きなどはどうとでも、現在進行形の話ならば、それは土蜘蛛――ヤマメを対照にした言葉であろう。
先ほどからの発言に、彼女は地獄の官人でもかなり高位の官僚であろうかとパルスィは思った。無論、この様な事態に当たるには、それなりの人物が必要であるが。
「ええ、承知してますよ。閻魔(えんま)様」
閻魔。その言葉はパルスィにも予想外だった。
この度訪れたのは、是非曲直庁の十王直轄の官僚で、その支部である幻想郷(ザナドゥ)の地獄の最高責任者。閻魔(ヤマ)、四季映姫であった。
ヤマメは決断を迫られていた。
正邪への借りだけならばまだ、断る余地もあった。しかしヤマメを悩ませるのは、田道間の存在である。
同胞と同じぐらいに深い彼との縁が、ヤマメを縛っている。
同じく鎮西の出ではあるが、彼は彼の同胞と離れ、ひょうすべ一族の中で唯一ここに移り住んだ人物である。
土蜘蛛達は安住の地を求めてこちらへ移ったが、彼は違う。彼の一族は既に筑前、太宰府に安住の地を得て久しかった。彼はそれを捨ててまでこちらに来たのだ。
それは古い頃のヤマノメへの恩義に応え、ヤマメを助けるための行いだった。
二人の間には、どちらがどれだけ貸しを、借りをなどと言う気持ちは無い。共通した一人の人物が繋いだ縁から、今に至るまでの運命共同体だ。
「田道間様、一つ聞いていい?」
「納得いくまで、いくらでも」
普段のようにゆるゆるとではなく、升で一合グイッとあおり、田道間は問いを待つ。
「私はどうすればいい?」
「好きにすればいい」
「どうすれば良いか分からないの。ずっと、何も考えずに生きてきたから。ここにどうやって辿り着いたのかすら、もう、覚えてない。パルスィにも言われたけど、私はずっと虚ろなまま過ごして来たんだと思う。誰かさんをなぞって」
同胞の前に立って戦い続け、やがて堕とされた古の土蜘蛛を、ヤマメは思い出す。彼女呉れたまぼろしの記憶より、己の思い出がずっと希薄なのも。
田道間はヤマメの目をジッと見据えてから、新たに注がれた酒も飲み干す。
「ならば、なぞれば良い。お主は立派にそう勤めてきた。そして誇れ、進め、今やお主は御前よりも先に居るのだ。心に、従え」
正邪が怪訝な貌を向けるのにも構わず、田道間は言い募る。
「我らは征く。それは変わらん」
彼の中に渦巻く意思は、決して揺るぐ様子を見せない。この後は従前の通り、軍勢を率いて地上に這い出る事であろう。
「ったく、ゴチャゴチャと面倒な奴だね。土蜘蛛よ、一つだけ教えてやる。後ろのお仲間にかけてやった小槌の癒術だけどな、アレ、いますぐ解くことも出来るんだよ?」
これは正邪の切り札であったはずだ。しかし彼女は早々にこれを切った。
「正邪殿、それはまだ言い出す予定ではなかったのでは?」
「迷ってんなら後押ししてやるだけだって。なあ、そいつらが生きるも死ぬも、いや、死ななくても今すぐにズタボロになるのも、私の胸先三寸なんだよねぇ」
天邪鬼が偽り事ばかりを述べる妖なのは、ヤマメもよく知っている。今の言葉、正邪だけが放った物ならすぐに疑ってかかるところだったが、田道間の言葉を聞く限りそれは真実である。
しかし、惑わない。
「みんな、恨むなら恨んで……」
その呟きの意味を後ろに立つ彼ら、彼女らは当然理解する。
連れられた七人の反応はそれぞれだ。怯える者、呆ける者、地獄の処断よりはと覚悟する者。皆、死や苦痛に恐怖するがしかし、誰一人、ヤマメにも正邪にも命乞いはしない。
「お前に受けた恩は、ここで返そう。私達は、断る!」
「は? ……はぁ?!」
ヤマメの返事に、正邪は素っ頓狂な声を上げ、取り巻き達は一同に立ち上がる。
田道間は微笑みを浮かべ、店主に今日のオススメを尋ねる。
「ほれ、この通りよ。天邪鬼よりも御しがたく、度し難いのよ、土蜘蛛は」
「はあ、全くで」
そんな会話など正邪の耳には入らない。わなわなと身を震わし、彼女は叫ぶ。
「はっはぁ! 上等だ! 賤民共が思い知れ!!」
彼女がそう願い(の解除)を込め、小槌を振るおうとした時であった。
「パルスィ任せた!」
戸が荒々しく開かれ、緑眼を輝かせた蛇が宙を泳ぐ。蛇は迷う事無く小槌に食いつき、正邪の手中にあったそれを易々と奪い取った。
「なっ!?」
まず姿を現したのは当然勇儀、そしてパルスィ。後ろには直参や、映姫達も控えている。
「貴様……おい勇儀さんよ、お前は何とも思わないのかい!? こいつ私の恩を仇で返そうとしやがったんだぞ、それにこのジジイにも借りがあるんだろうが! ここじゃそういう仁義が物を言うんじゃないのかい?!」
「うるさいね、あんたが仁義を云々するんじゃないよ。それにその借りってのも、あんたのマッチポンプなんじゃないのかい?」
勇儀は手近に居た女の土蜘蛛を手招きすると、さとりの前に送り出す。
「ふむ……どうも事故当時の思考が、おかしいですね……」
「はっ、何を言ってるんだ? お前が心を読めるって言ったところで、それはお前にしか分からないだろうが。都合の良い話でっち上げようとしてるのはそっちじゃないのか?」
「私は公正な立場で視てるんですよ。あくまで事故調査の手伝いですから。それに、私の能力を疑うなら、第三者の目にも触れられる物をご覧に入れましょう」
さとりは映姫の、帽子から降ろした薄布の向こうの目と視線を重ね、頷き合う。
「本来は、亡者を裁くための閻魔王庁の備品なのですが、今日は特別ですよ」
映姫が手の所作だけで従者に指示すると、彼らは布に覆われた重々しい板を運び込み、それを立てかける。
帳らしき布を取り払うと、そこには六尺ほどもある楕円形の姿見がそびえていた。
「浄玻璃の鏡、本来は亡者の生前の行いを、真実を晒すための宝具です」
正邪の顔が青ざめる。
あの事故の裏で何が起こったのかは、もはや見るべくも無い。
「いや、そりゃ私じゃない……私は、あいつの言う通りにやったんだ! あのジジイだ、あのジジイが地底と地上の妖怪全部に復讐してやるためだって、そのためには先ず土蜘蛛をはめれてやればいいって、私は言われた通りにしたんだ!」
それは正邪の知る限りの事実であり、彼女の心を読めば、浄玻璃の鏡で映せば、その通りであったと分かる。
「天邪鬼が、珍しい。命が惜しいからか随分正直に白状しますね。でも、誰がそれを信じます?」
迫る映姫にたじろぐ正邪に、更に勇儀が言う。
「それにだ、あの爺様はずっと昔のヤマメへの恩と借りに報いるため、進んでこっちに来たんだよ。静かな終の棲家まで捨ててね」
それは彼自身の鎮魂と懺悔でもあったのだろう。
「はぁ? そんなの私が知るかよ! じゃあ読めばいい、映し出せばいい、あのジジイが私に何を吹き込んだのか!」
正邪は叫んで、己に策を授けた張本人に向き直るが、そこには重々しい鋼の矛が立てかけられているだけ。彼の姿などどこにも無かった。
「くそっ逃げやがったなジジイ! でも無駄だ、お前に憑り坐した怨霊を剥がせば――」
周囲の上下を全て逆転させ、その場に居る全員が文字通り浮き足立つ。正邪は僅かな隙を逃さずパルスィに組み付き、すぐに小槌を奪い取った。
「小槌よ――」
土蜘蛛達がいち早く体勢を立て直し、まず勇儀を助けていた。
「無駄だ……!」
その勇儀は、正邪が小槌を振るうより先に、上方へ、即ち地面に彼女を殴り飛ばす。
正邪の能力は覿面に解かれ、固定されていなかった物がまた反転して地面に落ちる。
店内の状況は地震の後より酷い有り様だが、幸いにも怪我を負った者は皆無。殴り飛ばされた正邪以外は。
「無駄なんだよ、天邪鬼」
勇儀の貌は、また酷く寂しげである。
「田道間様、なんでそんな無茶を……」
反転し、鞘を破って屹立する矛にヤマメは語りかける。
彼の姿はもう、この世のどこにも無かった。
∴
「限界だったんでしょう。もとより水界のモノが、それも清い水辺で住むべき河童が、地底にあんな地底に住むなんて無理だったんですよ」
ヤマメ達の代わりに一部始終を視た椛とはたては、その様子だけを伝えた後、衝撃で絶句していた。
唯一、その様子を視ていなかった文だけは冷静そうな素振りを見せているが、心中の動揺が一番大きいのも文だった。
「それが、あれだけの量の怨霊を依らせて、無事で済むはずが無い。もっとも、それも計算の内だったのでしょうけれどね」
「文、計算の内って……」
「彼に依っていた怨霊は、恐らく彼の魂に依り憑いたまま。つまりは道連れですよ。六道輪廻の理から外れた外道に、行く先はありません。潰えれば、そのまま消えるんです」
「怨霊を一掃した上に天邪鬼を追っ払って、一挙両得って事? 自分の命まで使って?!」
「ええ、その通りですよ。と言う訳で、私は今回の件、記事に起こしません、お蔵入りにするつもりです」
人の死などの暗いことを生地にするのを文は嫌う、自殺などはもってのほか。
はたても文のポリシーは承知しているが、ここまで引っ張っておいてお蔵入りというのは、労力を顧みると耐え難い。
「いやでも、折角の一大事、それも解決したみたいなのに……」
「私が記事にしないだけです。はたては好きにすれば良いでしょう」
言って、文は飛び立つ。
伝えるべき事だけ言った今、誰とも言葉を交わしたくなくなったのだ。
己が最も嫌う、誰かのための、迂遠な自殺などという物を目にしては。
∵
旧地獄は一連の事件から解放され、ようやく平静な様子を取り戻しつつあった。
炭鉱で事故を起こした土蜘蛛達は、正邪の能力で思考をねじ曲げられたのがその原因であると判明し、関係する行いは全て無実と判じられた。
勇儀の取り巻き達は辛うじて元の通りに納まったものの、そこには直参の鬼のキツい責めが待っていた。
下ノ町の鬼哭は消えたが、またしばらくすれば、誰かがここに辿り着くのであろうか。
そして這々の体で逃れた正邪は、打ち出の小槌の持ち主と共に地上で事を起こすのだが、それはまた別のお話。
感想をツイートする
ツイート