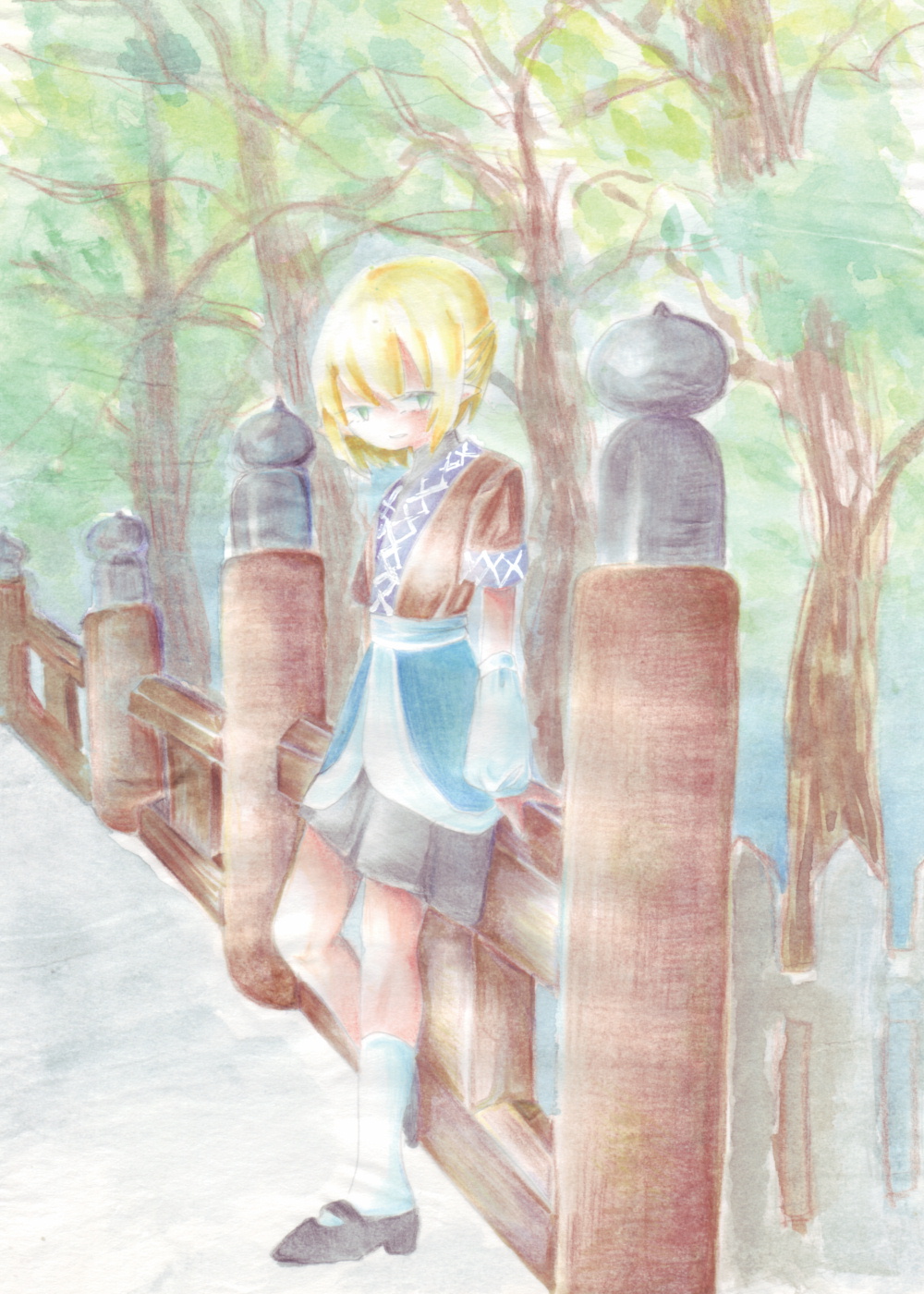楽園の確率~Paradiseshift.第4章 明けぬ夜を征く 明けぬ夜を往く 第3話
所属カテゴリー: 楽園の確率~Paradiseshift.第4章 明けぬ夜を征く
公開日:2017年10月02日 / 最終更新日:2017年10月02日
楽園の確率 ~ Paradise Shift. 第4章
明けぬ夜を征く 第3話
全周に弾幕を転回して退路を局限させつつ、避けた所へと体内の魔力すら封じ込める撮像術を叩き込む。スペルルールでは御法度レベルの、やはり不可能弾幕水準のスペル。
正邪はまず、ばらまかれた弾幕を切り抜けると、ひらり布を用いて撮像術を回避。しかしにとりの方には、多数の流れ弾が迫る。
「ちょっとちょっと、なんだってんだよ!」
にとりは無力化された射撃を中断し、防御型のスペルである『オプティカルカモフラージュ』の障壁を展開し、自身に降りかかる弾幕を防御。
正式な妖怪の山の一員であるにとりが不法侵入者である正邪を迎え撃つのは、正当な行為と言える。むしろその存在を認めておいて素通りを許すなど、却って責めを負おうという話になりかねない。
その正当な行いをしているはずなのに、受けるのは巻き込まれての無差別攻撃。にとりにとってはたまったものではないし、憤るべき場面だ。
それに河童にも、その縄張りの内でなら自治権はある。それも頭越しにされては流石に我慢ならぬと、にとりは文のスペルの時間切れを見て『オプティカルカモフラージュ』を意図的に効力停止。
「こんにゃろ! いくら天狗様でもこんな横暴許せるもんか!」
そう啖呵を切って、背負ったリュックの下に手をやると、両手に大型の拳銃型水鉄砲携えてスペルを宣言、
瀑符『ケゴンガン』
「あっちもこっちも、鬱陶しいんだよ!」
左右の銃先をそれぞれ正邪に、文に向け、瀑の名に見合った水流を浴びせる。
正邪は頭上から迫っていた文に向けていた注意を姿勢と共に翻し、にとりの姿を下方、視線の端に捉えると、再度ひらり布を使用。
水流を避ける正邪。にとりは先ほどのスペル回避時にひらり布の効果を見抜き、それに惑わされず、水流を浴びせ続ける。
主指向方向は正邪。ついでに銃先を向けられた程度の文は、己の飛行能力のみで易々とケゴンガンを回避。更に木や岩に当たって砕け、妖力を纏ったままの無数の飛沫もひらりひらりとすり抜ける。
にとりの意図は文を追い払う事にあったため、その姿が離れたのを見て銃先を両方とも正邪に集中させる。
正邪はケゴンガンの切れ目無い射撃に焦る。ひらり布の効力発揮時間が決まっているため、このままではどうしても、次の使用まで被弾を余儀なくされてしまう。
それは攻撃を加える側のにとりにも同じ事が言えた。今撃ち出しているのは水妖エネルギー。ただの水鉄砲よりは持続性があるが、それもまた限りがある。
ひらり布の効果が停止するのとケゴンガンの射撃が中断したのは、ほぼ同時だった。
にとりが繭形タンクのカートリッジを交換しようと左手の銃をしまい込んだ瞬間、正邪が気弾をバラ撒きながら突進。
「こんちくしょぉぉぉ!」
「ひゅいっ!」
にとりはスペルも妖術も行使する間も無く、通常弾幕を展開。正邪は被弾覚悟でそのままにとりに激突――
「やかましいガキが! お前が道を開けろ!」
――しなかった。
にとりの天地が反転し、宙に身を浮かす為に発揮していた妖力がその身を大地へ誘う。これは正邪の能力ではない。それはあらゆる妖術と同様に、小槌の魔力が喪失すると同時に取り上げられたままになっている。
今の現象は、ひらり布をにとり本人に対して用い、本来彼女が飛んでいた方向から明後日の方へと逸らしたのだ。
下にすっ飛んでいくとは思っていなかった正邪。しかし結果としては最高、の一つ下。
「チッ、命拾いしたな」
偶然か否か、にとりは辛くも地面に叩き付けられるのを免れ、沢の流入口の小さな滝壺へ突っ込んでいた。ただし河童とは言え、水面に衝突した衝撃もあって沈んだまま。
それを尻目に逃げようとする正邪。そこへ一連の戦闘から一旦は距離を置いていた文が戻る。だが正邪を追うのは断念。
自身が直接そうした訳ではないものの、間接的ににとりが被害を負う結末を招いてしまった。にとりへの口止めも考えているが、それ以前にこの状況を看過し、彼女の身に万一の事が起こった場合の方が厄介だ。
衣服を纏っているだけなら、それは死と共に諸共消えて無くなってくれるであろう。衣は魂の一部ともなり得、かつ、魂は妖怪の主体。そして外道たる妖怪はこの世に残すべき物を持たないのだから。
だが彼女の場合は、背に負った鞄やら機械類やら、痕跡が大量に残る。いずれにせよ、死人に口なしとはいかない。
正邪の姿はもう木々の向こうに消えていったが、それに代わってどんな獣より素早い足音が近づく。
「文様!」
椛は事の次第を千里眼で観察していたため、状況はおよそ理解している。文がかなり強引に割り込んで、このような結果を招いたのも。
では己がにとりの救護を。そう滝壺に向かおうとした椛を、文は止める。
「椛、天邪鬼はあなたが追って。妖力の残滓を辿ろうとしても、痕跡が弱すぎて難しい。ここはあなたの眼の本領発揮よ。でも、分かってるね?」
一瞬「ヲフ」と犬のような鳴き声を上げようとして、椛は留まる。
「もちろん!」
確かに意図を理解してそう返し、椛はすぐに駆け出した。
殺すよりも怪我を負わせた方が有効だとは考えていなかった正邪。一手遅れた椛の追跡には気付かないまま低空を飛び回る。
地の利など一切無い山中、どちらに向かえばいいのかも分からなくなっている。山には旧地獄の鬼達と同様、独立独歩の妖怪がいるとは聞き及んでいたが、そもそも自分でも、どこを目指していたのか分からない。
とりあえず尾根をひとつ越えてみれば状況も変わるかと、意図せず妖怪の山中枢に変針した時だった。
正面に現れる妖獣の影に、進路を遮られた。
白狼天狗の存在自体は聞いた覚えもあったが、その姿までは知らない。すわ追っ手かと即座戦闘態勢。
そんな正邪の様子を見た影は、戦意が無い事を示すため両手を挙げつつ、たしなめる。
「儂は敵じゃない。それにしても見たところ、苦戦しとるようじゃのぉ」
森林特有の明暗のコントラストから正体が掴めずにいたが、立ち止まって目を慣らしてみれば、それが自身の聞き及んだ白狼天狗の特徴と一致しないのに正邪は気付く。
「お前、寺に住み着いていた化け狸!」
その通り、と言わんばかりに身体と同じほどもある大きな尾を宙で左右に揺らしてから、化け狸――マミゾウは訂正を加えつつ応じる。
「儂はちょくちょく軒先を借りに行ってるだけで、別に住み着いとる訳じゃないがな。ときにあんさん、こんな所に来てしまって大丈夫だったのかな?」
「何の話だ」
当然心当たりはある、しかしマミゾウはそれを知らないはず。まともに取り合うつもりも無いと、脇を抜けて飛び去ろうとする正邪を、マミゾウが呼び止める。
「いや、例の黒白魔法使いがあんさんを探しとったんでな。逆さ城にも攻めてきた霧雨魔理沙じゃ、知っとるじゃろ?」
これは正邪にこそ寝耳に水だった。
「アイツが?」
一体どんな意図で、自分の行く先を知られたが故の行動か。それにしてもなぜわざわざ、自ら危険だと言った所に来るのか。時間と追っ手に追われた正邪には答えが導き出せない。
「まあまあ、ここが危険な場所だというのはよぉく分かったじゃろうて。そこでじゃ、このピンチを切り抜けるのにちょっとした策を授けてやろう」
するとマミゾウは、右手にひらり布を左手に小さな地蔵を取り出す。正邪は驚き、腰に提げた麻袋をまさぐる。いずれも自身の持ち物であるマジックアイテムなのに、それらがいつの間にか失せていた。小さな地蔵は名付けて『身代わり地蔵』、その名の通りに所有者へのダメージを皆無にするアイテムだ。
相手は化け狸、化かすのはお手の物。そんな妖怪に手元のアイテムを盗られた程度で驚くのは天邪鬼の名が廃ると、正邪は脂汗を流しながらも声音を落ち着かせる。
「どうやってギッたのかはどうでもいい、それがどうした」
「いや、これだけじゃが?」
これだけ、マミゾウは両方の手それぞれにアイテムを持っているだけ。それだけだった。
「察しが悪いのお。手が二つあるならアイテムも二つ扱えるじゃろ」
言われてみればその通り。
魔力の消費はアイテムに貯えられた分が主で、正邪が使用時に消費する妖力はそこまで大きくない。二つ同時でも扱えなくはない理屈だ、完璧とはいかないが。
「たかだかこの程度の事に気付かないなんて。くそっ、礼は言わないぞ」
「礼を言われたいが為にお前さんに親切にしてやってる訳じゃないからな。そんなもんはいらんよ。折角じゃから、あっちこっち引っかき回して貰えたら楽しいと思っただけじゃ。まっ、妖怪の山はちと逸りすぎだったかも知れんがの。そこまで生き急ぐなら、いっそあの世巡りをしてみるのもええじゃろう」
それも何かのヒントか。マミゾウの思惑がどこにあるのかは不明ながら、それはアドバイスにも思える。ただ旧地獄での件もあり、とてもそこに踏み出す切っ掛けにはし辛い。
一体何を考えてそんなに情報を寄越そうとするのか。その意図を問いただそうとした正邪に、最後のアドバイスがもたらされる。
「ほれ来たぞ。儂はここでおさらばするが、まあせいぜい頑張っとくれ」
追っ手を撒ききれた訳ではなかったのか。正邪が一瞬だけ来た方を向き、そちらから逃れようとまた正面を向くと、マミゾウの姿はそこには無かった。
流石は狢の総大将と言うべきか、椛が正邪を補足した時には、自身を少し大きめのヤマガラに化けさせ、既に木々の梢の中に消え去っていた。
椛もそれは認識していたが、今はそちらへの用は無い。
「けっ、まあいい、やってやる」
正邪が麻袋に手を突っ込んでみれば、マジックアイテムは元通り。そこから改めて二種のマジックアイテムを取り出す。選定に理由など無い、行き当たりばったり。
椛を背にしながら、逃げもせず空中で留まる正邪に、椛は脇差しほどの警棒を向ける。
「天邪鬼! 御山への侵入など狼藉の廉で、お前を捕縛する。神妙に縛に就け!」
正邪は乱杭歯をギチギチと鳴らしながら、
「はっ! お前がかよ、ワンコ! いいさ、とっととぶっちめてやるから掛かってこい。今度は負けやしない、負けるもんか!」
溜め息にも悲鳴にも思える不快な声で言い放つ。
椛の動きは、その啖呵を受けて僅かに後れを取った。
今度は。
今まさに敵と対峙しながらも、その言葉がいつを指すのかに考えが及び、椛は逡巡する。確かにかつて、天邪鬼とは戦った覚えもある。
ずっと古い話であるが、今この姿を取っているのも、年老いた山犬が天邪鬼に射殺された所から始まっている。そもそも千里眼――天眼通に非ずの浄天眼は、天邪鬼の如き勿怪を追随するため、天部におわす方より与えられた物。少なくとも転化転生したばかりであった頃の山犬にとっては、天邪鬼追捕こそ至上命題だったかも知れない。
正邪は意図せず生じた椛の隙を突き、飛び去りながら弾幕を展開。
意識を正邪に戻した椛は、咄嗟に背負っていた盾を構え、殆ど全身をそれに隠して第一波を凌ぐ。スペルを用いたでも妖術を用いたでもない気弾、貸与品の盾でも易く防げた。
「この、抵抗するのなら!」
気弾の第二波を防ぎながら正邪の前方に躍り出て、頭を押さえに掛かる。
椛は背側に佩いた大太刀を逆手に抜くと、風切り音を鳴らしながら手中で半回転。その刃に法力を乗せながらスペルを宣言。
牙符『咀嚼玩味』
刃は今の椛にとっての牙であり、唯一にして最大の護り。
扇状に弾幕を展開して正邪の進路を局限。周囲の大木が着弾に応じて激しく揺れ、穿たれる。その威力を正邪が目にするよりも先に、上下に光弾の壁が出現する。
空中に形作られたのは犬狼の腭。これも当然、不可能弾幕水準のスペル。椛が刃を一振りすると、それら弾幕の牙は正邪を噛み砕かんと閉じてゆく。
退くか進むか。正邪がいずれに向かうにしても、弾幕の口腔から逃れる必要がある。しかし手元に準備しているのは現状に適した『ひらり布』ではない。正邪は意を決して前進。にとりの時とは違い、運任せの突撃に賭けようと決心。その前に僅かな布石を打つ。
「大したモンだよ犬ころ! 人に飼われてのんびりしてた頃とは違うみたいだなぁ!」
そんな覚えは、確かにある。それも山犬にとっての“始め”であったからだ。ではこの天邪鬼は己が知るモノなのか。
天邪鬼には複数の形態があり、それぞれに伝承類話が無数に乗っている。そういった物の中に、犬が天邪鬼を退治する物があったかも知れない。
いや、そんな話には覚えが無い。それより己はなぜ今、そんな事を考える。
正邪自身には、訳の分からない話で混乱させる程度の意図しか無かった。しかし適当に打った布石は、彼女の想像の遙かに上をゆく結果をもたらした。
「ははっ! 所詮ワンコはワンコだな!」
椛の困惑に呼応して勢力を減じた弾幕をすり抜けながら、正邪は気を大きくして喚く。
椛はすぐに自分を取り戻し、弾幕の閉塞を早めようと妖力を込める。腭は得物を弄んでいたかのように、瞬く間に閉じた。
(墜としたか?)
残心を取り、光弾の群れに磨り潰された正邪の方を見る椛。ここで見逃して、またあらぬ方へ行かれてはかなわない。
見逃す心配だけはすぐに解消する。
「こん畜生が――」
光弾の壁から叫びながら現れた正邪に、今のスペルのダメージは無い。左手に携えた『身代わり地蔵』の効力により、ダメージを皆無なまでに減じていた。
椛の攻撃もこれで終わりではない。弾幕の腭を抜けて来た者は、白刃の衝撃で迎え撃つ。
「喰らえ!」
白刃が振るわれることにより発された衝撃を正面から圧し、進む正邪。その右手には蒔絵を施した小槌が握られている。
打ち出の小槌は既に取り上げられている。この小槌は紛い物に違いない、虚仮威しだ。
椛のその判断は、半分まで合っていた。失敗は、その小槌が先般正邪が旧地獄に持ち込み、本身の威力を見せつけるのに使用したレプリカではないのに気付かなかったこと。
椛が刃を戻した時には、正邪の姿は文字通りに目と鼻の先。そうであっても対応できるだけの力量を備えてこその白狼天狗。懐に入り込んだなら、柄で殴り、蹴り上げるだけ。
ただし椛はあえてそれをしない。
――分かってるね?
文の言いつけは十二分に理解している。始めから、捕らえる気も倒す気も無い。目的はあくまでも、これ以上目立つ行動をする前に追い返すだけ。
戦いながらも、椛の眼は先に新たな影を捉えていた。
ならばここはあえて受け、負けてやればいい。
妖怪の山という確固たる組織の中に在する椛は、己の勝敗よりも、課せられた役目を全うすることこそを――今それを下したのがその組織から少し外れた人物であるのを承知しながらも――至上と考えている。
刃を後ろに置き、盾を前に突き出す。正邪の次の一手は小槌の打撃に相違ないと、全身の動きから識別していた。
次の瞬間、振り下ろされたのは確かに打ち出の小槌だった。しかし椛には、その小槌の姿が山の神社が据えた御柱にも匹敵する強大さに見えていた。
いや、逆だ。椛が受けた衝撃が余りにも大きすぎたため、それまで見ていた小槌を巨大な神槌と、遡行して錯覚したのだった。
マジックアイテム『打ち出の小槌(レプリカ)』。それは形影として打ち出の小槌の力を招いたわけでなく、ただ強力な鈍器として機能していた。
思いの外強烈な衝撃に、油断していた椛は耐えきれず、背中から地面に叩き付けられた。
椛が目を覚ますと、そこには文とにとりの姿があった。
太陽は稜線に隠れたばかりで、周囲は明暗のあいまいな世界になっている。
そう時間は経っていないのを認識してから、椛は文に話しかける。
「すいません、不覚を取りました」
「あれ、わざと負けたんじゃなかったの?」
嫌味でなく文は、椛が堂に入った芝居をしたものだと思っていた。椛の方もその通りで、あの瞬間まではそれに徹しようとしていたのだ。
「はい、そのつもりでは当たっていたんですが。マジックアイテムのバリエーション、結構増えているみたいですね。打ち出の小槌を模した物で、この通りです」
十分に身構えていれば、軟着陸して負けたふりで済んだのに。油断したのは本当だった。
椛の心中にそれ以上は踏み入らず、文は尋ねる。
「……“それ”からは、例の魔力は感じ取れた?」
「分かりませんでした。あれを認識したのが突然だというのもあったので」
少なくともそれが、旧地獄へ持ち込まれた物と同一の器物でないのだけは判別できた。これだけは、二人とも揃って安心できた点だった。
「ところで天邪鬼は、黒白と合流を?」
「ええ、間に合ったみたい。今のところ目撃者は無し。ひとまず撃退には成功ね」
同時に大きく息を吐き出す二人に、とても心穏やかには見えないにとりが割り込む。
「ちょっとお二人さん。てか天狗様、あたしは口止めに同意しちゃいないんだけど」
「言ったでしょう。これは今後の幻想郷の如何に関わるかも知れない事態なんで協力して下さいと。私も当初は賛同しませんでしたが、よく考えてれば妥当だと分かりますから」
「天邪鬼の背景を探り、黒幕を見つけ出して叩き潰す? 知らないよ、そんなの」
にとりにしてみれば、幻想郷の如何などと言われても、非現実的な話でしかない。
幻想郷の内外を行き来するには、妖怪の山にあるという抜け穴か結界のほころびを抜けるか、その他の不正な手段を取るぐらいしか考えられない。
それらの手段を取れない者にとって幻想郷の存亡は自身と一蓮托生。にとりの身も直接関わる。そうであるからこそ、事が大きすぎて、そんなものは妖怪の山の上層部か博麗の巫女でなんとかしてくれとしか言えない。
しかし文は、その妖怪の山という組織への口止めも、にとりに提示していたのだ。
「だから納得できないんだよ。スペルに巻き込まれた件は、お互い様だけど」
言いながらも、にとりは甲斐甲斐しく椛の手当を進めている。にとりとは将棋仲間という程度に付き合いもある椛も、そうされながら真意を明かせないことに忸怩たる思いを抱く。
ここでにとりを抹殺して死人に口なし、という手は、先ほど見過ごせなかった時点で二人の選択肢には無い。文としては、彼女より先に正邪にアプローチできなかったという時点で、自身の失敗だと考えていた。
「分かりました、仕方ありませんね。ではせめて、私があなたに口止めをしたという事だけは、せめて黙っていて下さい」
にとりがチラと椛の方を向くと、椛も軽く頭を下げて拝む。
「はいはい、分かりましたよ。ついでにわざと天邪鬼とやらを逃がしたことも黙っててやる。でも奴がここに入り込んだ件は、然るべき筋から上申するからね」
「それは随意に」
文はにとりの誓約に、僅かな期待も抱かなかった。言葉通りに一部を伏せることすらも。
「やはり説得は駄目でしたね」
「あのシチュエーションじゃ、黙ってろって言うのが無理ね。私も焦ってやり過ぎたし。それに、にとり個人はどうか知らないけれど、種族としての河童には天邪鬼と因縁もあるからね。確執が魂に染みついている種族に一時とは言え[利敵行為をしろ]も難しいわ」
「因縁、ですか?」
河童の元の形態の一つに、術士に使役された藁人形だったという物がある。
藁人形と言っても、橋姫が貴船の杜に打ち付けていた物のように手の込んだ物ではなく、藁を纏めて手足を模した棒を通しただけ粗末な物。これが河童の元になったと言われ、数千ものそれを自在に使役したのが、壱岐の天邪鬼(あまんしゃぐめ)であるという話だ。
――もしそれらを何かに比定させたなら、それはまた別の悲劇の物語となろうか――
「まっ、今更何を言ったところで、出遅れた時点でアウトだったのよ。これからは、奴の件をどう落ち着けるかを考えるわ。なんとか人の目に触れないように進めたいけど……」
文は樹冠の向こう、夕闇の中に更に暗い影を認め、椛にもそうするよう促しながら降下。
視線の先には、ここで目に触れてはならない人物達が悠々と帰途を辿っていた。
正邪を導いて飛ぶ魔理沙は、森の中から鋭い妖力を叩き付けるモノを知覚していた。向けられた意思は「悠長に飛んでいないでとっとと帰れ」との忠告。
ただ存在は知覚されても、意図は魔理沙に伝わっていなかった。
「ったく、なんで行くなって言った所に行くかな」
これも悠長な様子で正邪に問いかける。天邪鬼にそんな事を言うだけ野暮というものだが、それでも口に出さずにはいられなかった。
「へっ。お前が行くなって言ったから、逆に行きたくなったんだよ」
納得したくもない、納得できる答え。
行けと言われれば行かないという話でもなく、結局正邪が幻想郷を巡る間、魔理沙の忠告を聞き入れない限り、いずれは辿り着いていただろう。
「本当にお前は、誰かさんにそっくりだよ」
「誰のことだ? 私そっくりなんて相当捻くれた奴だな」
「ああ、本当に嫌になるぐらいにな。ところで、私の忠告を無視してまでここまで来たんだ、何か成果はあったんだろうな」
「新しいマジックアイテムは無かった。今日は新しい潜伏先を探してたんだ」
「おいおい……」
こちらにいくらか企みがあるとは言っても、彼女にとっては平穏無事な宿であるはず。わざわざそこから出て、あえて危険地帯に乗り込むなどとは。魔理沙は天邪鬼というモノの扱いづらさを、つくづくと思い知らされる。
「もっとも、河童は出るわ鴉は出るわ犬ころに噛まれるわ、ろくな目に遭わなかった」
「そりゃそうだろう、生きていただけマシだと思え」
魔理沙は、正邪が言う鴉と犬ころが、文と椛である事を祈る。
彼女らならば事情を知っていると聞いている。問題は河童だが、妖怪の山では射命丸も比較的上位種とは聞いているため、常からつるんでいる椛も含めて彼女らだったのならどうにかするであろうと。
妖怪の山の方は、もう祈るより他ない。今は闇夜に紛れて正邪を連れ帰るのみ。
これら魔理沙の懸念の先は、正邪の追跡がおおっぴらなものになること。
これまではただ迷惑を振り撒きまくった妖怪という話だけで、各所で警戒していた者が迎撃、あるいは既に被害を被っていた者達が各個前進で襲い掛かっていただけだったが、妖怪の山は確固たるテリトリーを持つ上に、情報の発信能力がある。
そこで考えられる最悪の事態は、正邪の手配書の発行。
もしこの懸念が現実となれば、現在荷担している企みは、大きく後退するかご破算となる可能性も高い。
魔理沙の荷担する謀。それは先般の輝針城異変に係るもの。
――「天邪鬼の背後に黒幕の影あり」
そう言い出したのは、幻想郷の妖怪の賢者の一人である紫だった。そしてこれを知らされているのは、今のところごく一握りの人物に限られている。
直接異変解決に当たった霊夢と魔理沙、紅魔館のメイド長十六夜咲夜。輝針城異変に近しい時期にイリーガルな手段で外の世界から入り込んだため、まず容疑を向けられたマミゾウ。それに妖怪の山でも一応は話が通じると思われる文と、その協力者としての椛。
もしかしたら、咲夜からは主人であるレミリア・スカーレットに断りが入っているかも知れないが、紅魔館としては事が大きくならない限り静観するであろうと見込まれていた。
先の異変のもう一人の元凶、針妙丸自身は、正邪の口車に乗っただけであり、その背後に何か居るかも知れないなどとは思ってすらいなかった。――
魔理沙も紫のうさんくささは思い知っていても、今回の件については納得がいった。何より幻想郷の管理者然とした紫が、幻想郷の如何に係る話をするのは自然であったし、それに貧相な地力しか持たない小者妖怪を、妖怪の賢者とまで称される紫が執拗にいたぶる理由もあまり思い浮かばない。
紫の言うとおり、正邪の背後に幻想郷へ悪意を抱いた人物がいるのなら、これをどうにかしたいと思うのは、魔理沙の素直な心だった。
里の商売人の子として生まれ、しかし夜空の星に魅せられ魔法に傾倒し、家出してまで才能を磨く事を決心して、今に至っている魔理沙。家族や里の知人に未練があるとも無いとも口にはしないし、今の生活が快適かどうかなどとも語らない。しかし、それらを口にしないのは、彼ら彼女らを今も強く思っている事の裏返し。
(もし幻想郷にそんな奴が居るのなら――)
「でも、収穫はあったぞ」
不安と懸念にまみれた心の整理を進めていた魔理沙は、正邪からの語りかけに、胸中の動揺などおくびにも出さずに応じる。
「マジックアイテム以外の収穫が?」
「ああ、お前には関係ないけどな。これで少しは私も強くなった。化け狸様々だ」
マミゾウの動きに、魔理沙は首を傾げる。
彼女も紫と同じく、この度の企みの首謀者である。それがここでヒョコヒョコ出て来て、何か策を授けた。その思惑を魔理沙は推し量るが、嫌な方向にしか考えが向かない。
(単にマジックアイテム探索を助ける気か。それとももっと強力な奴らを宛がって、コイツが黒幕の所へ行くのを促す気か)
または、いくら化け狸とはいえ、天狗の目がある危険な場所で張っていたのを考えると、妖怪の山へ正邪が訪れた時点で、天狗の動きがどう転んでもいいように逃走に寄与する策を授けようとしたのか。
いくらでも可能性は考えられる。折を見て直接訪ねるまでは、考えるだけ無意味だろう。
「私に関係ないなら聞く意味も無いな。それはおいおい見せてくれ」
「ああ、いずれ見せてやるよ」
おおかた、また寝込みを襲う気であろう。何度撃退しても懲りないのだからしょうがない。これも天邪鬼のサガかと魔理沙は諦めている。あとは粛々とトラップマジックを張って安眠を確保するだけ。
「いずれじゃなくて、今見せてもらうことになりそうだ」
魔力感知術式を展開していた魔理沙は、自身を捉えようとしている何かの存在を知覚する。千里眼ほど精細ではないが、ただそれが向いているのを知るだけなら十分事足りる。
「正邪、私を撃ちまくれ。ただし本気ではやるな」
「急にどうしたんだ?」
「誰か来る、もう視られてるかも知れない。とりあえず私を襲っていた風に装え。危なくなったらちゃんと助けてやるから、さっき言った収穫でもってまずは一人で戦ってみろ」
正邪と仲良く飛んでいる場面を押さえられたら、魔理沙もしばらく身を隠さなくてはならなくなる。少なくとも紫の謀が終わるかして、事情が明らかにされるまでは。今の指示は、そういった事態に至らないように練っていた腹案の一つだった。
「あいあい、私としても寝床が無くなるのは都合が悪いしな」
魔理沙の表向きの意図は一応正邪に伝わっている。天邪鬼がその意図に素直に従うかは、また別の話だが。
正邪の応答を聞き、魔理沙はすぐに距離を取る。咄嗟後方からの全力射撃。
「お前! 全力でやるなって言っただろ!」
「ははは、迫真の演技だろ」
天邪鬼だからで何でも納得してはいられないが、魔理沙もここは我慢する。それに正邪の射撃自体は全力だが、避けた先への射撃の指向変更、彼女自身の飛行は単調かつ悠長。確かに“演技”ではあるようだ。
魔理沙も回避機動を繰り返す。遠目からなら魔理沙が追われてるように見えるだろう。
追跡者はまんまとそれに引っかかったが、
「待てー記事ネター! いや天邪鬼ー! 黒白なんてほっといて私の取材を受けろー!」
そう叫ぶ追っ手は、はたてだった。
「……天狗かよ、最悪だ」
たとえここで正邪が勝って逃げおおせても、妖怪の山が騒ぎ始めるのがほぼ確定した。
∴
普段のラフな装いを改めて正装に身を包み、幅三間もある薄闇の廊下を粛々と歩む文。
夜半から今まで、時間の概念が飛んでいる。今し方、晨朝(じんちょう)の鐘が遠くで鳴り響くのを聞き、ようやく刻限が知れた。
ここは西塔(さいとう)と称される区画の中核にある、八葉堂という名の伽藍。妖怪の山の行政機関である。早朝ではあっても、真昼の門前町の賑わいと真逆の威勢と威厳に満ちている。
そんな時間にこの様な場所に文が召喚されていた理由は当然、正邪の妖怪の山侵入と、それへの対応の顛末の説明の他に無い。
河童からの申告への対応にしては異常なまでに迅速に話が進むものだと、召喚を受けた当初は驚いていたが、あの後、はたてが文字通りの突撃取材を敢行したと聞いて納得した。
そのはたてと、先に対応に当たっていた椛、そしてにとりへの聴取は終わっている。(一応にとりは、口止めの件を言わないという約束は守ってくれたようだ)
侵入者排除は文の職責に係る話ではなく、妖怪の山のモノ全ての権利であり義務であるとも言える。それを見つけ次第追い払った事に関して責めがあったのではない。
ただしそこから先こそ、文の職責に係る話。
「呼ばれた時から嫌な予感はしてたけど、これはちょっとねぇ……」
やはりと言うべきか、先般の異変の元凶が妖怪の山へ忍び込んで来たのに対して、妖怪の山上層部が黙っている理由は無かった。
気の重さに背を丸め肩を落とした文の後ろから、しゃなりしゃなりとした足音が近づく。
「どうしたのかな? 一貫坊(いっかんぼう)」
一貫坊とは、かつての文の名乗り。その身の軽さから、修行していた時に与えられた僧坊の名がそれで、そのままそれを称したのだが、今はその名乗りを知る者、そう呼ぶ者は極めて限られている。(最も付き合いの古い者達ですら、今は射命丸あるいは文と呼ぶ)
話しかけてきたのは、紫衣(しえ)を纏い、優美な長髪を揺らした人物。線、特に肩の細さ、物腰の柔らかさから、容姿からは男とも女とも判別しがたい。そして今、文を呼び止めた声も、どちらかと言えば女性的である。
ただ、妖怪の山は護法の聖地。男性の立場の方が圧倒的に高いこの地で、女性が高位に在るはずもない。そう“彼”は妖怪の山の権力者の一人だ。
文は丸めていた背を伸ばしてから振り向き、礼拝して応じる。
「これは鞍馬(くらま)様。いえ、先ほどの天邪鬼手配の件、私の如きが差配してよいものかと」
この人物は鞍馬僧正坊(そうじょうぼう)。かつて鞍馬山を治めていた権現であり、その験力や見識、何より信仰上の実績などからして、天魔を除けば妖怪の山の事実上のトップと言える。
「何を言っておるのか、それがお前の勤めであろうが」
叱責の声を上げたのは鞍馬ではない。
文に存在すら認識させず、風の如き静けさを以て佇むのは、鞍馬とは全く対照的な剃り上げた頭に強ばった肩、普段からそうしている通りの胴丸を身につけた人物であった。
「飯綱(いづな)様。此度の件、反対に回った貴方様が、今度はこれをよく進めよと仰るのですか」
「天魔様の御前にて、我ら八葉の合議を以て下された決だ。一度これと決まった事を、後からとやかく言う筋は無い」
日本第三の天狗と祀られ、中世の武将からの信仰も厚かった大権現、飯綱三郎。自他に対して極めて厳格であるのが、その面にも現れている。
そう、鞍馬同様に彼も妖怪の山の最高意思決定機関『御八葉(おはちよう)』の一員であり、文の所属する『書陵課』の上級部署を束ねる『宗務総長』でもある。
――八葉とは、大日如来が座する蓮華の花弁の数。その花弁には、四菩薩と四如来の八尊が位置している。妖怪の山に比定される八ヶ岳の八峰、それに富士山頂の八神峰も八葉と称されるほど、この数字は妖怪の山の信仰に深く関わっている。
この地では、その中央に天魔を置き、八葉それぞれに権現が座しているのだ――
ちなみに鞍馬などは、その見た目とは裏腹に、荒事すら担当する実働機関である『検非違寮』や『執行部』などを直々に指揮している。
その様な最高位の八人の権現のうち、二人を前にしても、文はさして緊張していない。西塔での文の地位は末端に近いが、幻想郷でも相当に古い人物であるというのが、年功序列上等の組織の中で立場をかなり強く補強している。
組織上は頭を下げ、その命令には従うが、それはあくまで組織の中に限っての振る舞い。あえて高位を目指さないのも、フットワークが重くなるのを嫌うからだったりする。
何か起これば、その速度で誰よりも早く駆けつける。それが今の文。妖怪の山での地位など、安定した飯の種ぐらいにしか考えていない。
「はあ、私も飯綱様と同じ意見を述べたのですが、なぜ御八葉はこの度の件を公にしようとするのです? 御山へ侵入者があったなど喧伝すれば、却ってその名に疵を付けようというものだと思うのですが」
「くどい!」
さすがに強面の彼にピシャリと一喝されると、文も身をすぼめてしまう。
「まあまあ、飯綱殿。彼女の言う事ももっともですよ。ですが一貫坊、我々は天邪鬼の追討を公とすることで、御山へ害なす者への見せしめにしようと、そう決を下したのです」
もっともな話ではある。
正邪は既にあちこちの組織の勢力圏に入り込んでは、縄張りを荒らし回っている。今更、妖怪の山に入り込んだのを周囲に知られた所で恥にもならない。逆にここで幻想郷全体に檄を飛ばせば、妖怪の山という勢力が幻想郷でイニシアチブを握っている様にも見えよう。
「ふん、相変わらず射命丸には甘いのですな、鞍馬殿は。こやつなど精々、新聞作りの腕と人里に近しいことぐらいしか取り柄など無いのに」
ついでに誰よりも速く飛べるぐらいですかね、と文は茶化したくなる気持ちを抑えつつ「全く以て仰る通り」と頭を下げる。
「いえいえ、叶うなら執行部へと引き抜きたいぐらい優秀ですよ。頂けませんか?」
「残念ながら新聞作りの巧さというのが、情報の収集能力、発信力に直結するものですからな。書陵課も人材が不足しておりますので、已む無くこちらに置くしかないのです」
それは残念と、言葉通りに口惜しそうな貌で言う鞍馬。
飯綱の方はまた文の方を睨むと、改めて下命する。
「権令史(ごんのれいし)、射命丸。急ぎ天邪鬼の手配書を作成し、早々に天邪鬼追討の周知を行え!」
「はっ!」
ここで時間稼ぎなどしてもどうにもなるまい。こうなれば紫達と共に、実態解明を急ぐのみと、文はひとまず手元の仕事に集中する道を選んだ。
∴
妖怪の山の尋常ではない動きの早さは、魔理沙もすぐに思い知ることになった。
昼に人里に出でて、所用を済ませて帰ろうとする頃には、大通りをすれ違う人々の手にすら正邪の人相書きが渡っていたのだ。
道ばたに捨てられていたそれを拾い上げれば、そこには人相書きの他、これまでの悪行が子細に記されていた。ついでに、生死を問わず無力化すれば褒賞を出すなどとも。
人間が天邪鬼の手配書を受け取ったところで、ただ怖がるか自警団が備えを固めるだけにしかならない。故に、これは他の妖怪への流布が主体であろうとは、容易に想像できた。
(そりゃまぁ、こうなるよな)
先の「妖怪の山へ行くな」という忠告、実は文からのものであったが、こうも素早く言われた通りになるとはと、二重に驚く魔理沙。(ただし、この手配書が文当人の手による物だとは露程にも思っていない)
とりあえず今は、どこか別の隠れ家へ送り込むか。それともいっそ、正邪の背後関係を探る話をおおっぴらに進めるべきか。
前者の当ては無いでもない。後者であるが、誰が紫の言う黒幕か分からない以上、協力者が増えるほど証拠隠蔽のリスクが大きくなる。
採るべき手立ては前者かと、すぐに腹を決める。
その前に紫達と合流して相談をと博麗神社に行ってみるが、そちらでは針妙丸と霊夢が縁側で仲良くお茶をしている光景があるだけ。紫かマミゾウの行方を聞いたところで「知ったことではない」と塩を撒くかの如き対応。霊夢としては関わりたくないのが本音。
(霊夢の感働きがこれだと、紫の心配も杞憂かもなぁ……)
などと魔理沙は今更に思いもするが、彼女の勘が鈍ることもままあるため、それは頭から振り払って帰途に就く。
「おーい、帰ったぞー」
廊下のランタンに油を詰め直し、火を付けながら正邪を呼ぶ。返事は無い。
「どうした? 逃げたのかー」
手配書が回った今、ふらふらとほっつき歩かれては敵わない。魔理沙は少しばかり焦るが、警戒用の術式は出入りした者が無かったのを示している。
よく耳をそばだてれば、奥の方からは地響きに似た不快な音。正邪の居室に行ってみれば、正邪は大イビキをかいて寝ていた。
「しっかし、寝顔すら可愛くないってのは凄いな……」
乱杭歯の目立つ大口を開けてそうしているのを見て、年相応に可愛い物好き魔理沙はついついそれを口に出す。
「おい、起きろ」
「フガ?」
寝ぼけ眼で見上げてくる正邪に、魔理沙は手配書を突き付ける。
「ほら、お前が忠告を無視して妖怪の山に行った代償だ。これで満足か?」
写真から起こしたのであろう、特徴を強調して描かれた大写しの人相書き、その端に並べ立てられた悪行の数々を見て、正邪はクツクツと笑い出す。
「……ふふっ、面白いなぁ。こうだよ、こうじゃないと!」
つくづくこいつは天邪鬼だと、魔理沙は呆れかえる。
「言ってる場合か。これでウチで匿うのは難しくなった。近いうちに次のヤサに移すから、準備だけはしておけ」
「準備って言ったって、私にはこれだけしか無いけどな」
机の上に広げられたマジックアイテムに視線を向けて正邪は言う。それが彼女の全て。
ただそれだけ。思い返せばそう、寄る辺も無く暮らし、その末に「弱者が見捨てられない楽園を築く」などと嘯いただけのこと。
その真意はただの私利私欲であろう。そうではあっても、その身の上に同情する気持ちも魔理沙にはある。
「ああ、そうだったな。お前には、それしか無いんだよな」
正邪はその言葉に歯を鳴らすと、魔理沙の胸ぐらに手を伸ばす。魔理沙は彼女の動きに咄嗟に反応し、その腕を取ると、捻り上げながら布団に押し付けた。
「クソッ! 人間のガキが私を哀れむなよ!」
「ああ、悪かったよ。もう同情なんかしない。やっぱりお前は、よく似てる」
「だからそれ誰だよ!」
「私にさ」
拘束を解きながら答える魔理沙に、正邪は怪訝そうな貌を向ける。
「はあ? お前にだぁ?」
「ああ、そう感じるんだ。それは絶対同情とかじゃない。むしろお前なんかに似てるって言われても、これまでなら真っ平だと思ってただろうな」
「それはこっちの台詞だ!」
お互い根無し草のひねくれ者、だからではない。
戻ろうと思えば、魔理沙には親も知り合いも居る。誰かの寝首を掻こうとした試しなど無いし、嘘ばかりついている訳でもない。
「お前、ずっと反抗ばかりしてるけど、どこまでがお前の本心なんだ? 本当は誰にも逆らいたくなくて、平穏無事に過ごしたいんじゃないのか?」
やりたくないから、そうしてしまう。
なぜ天邪鬼がそういうサガを持って生まれたのかは分からないが、自分への危害も、実はそんな思いの裏返しなのではないかとも考えている。
別に正邪に好かれようが嫌われようがどうでもいい。ただそうした正邪の心情の解決が、自分の心情にも連なっているように思えたのだ。
(そう、素直じゃないんだよな)
ただそうするための存在に生まれたからと言ってしまえば、それまでの事でもある。
「はあ、私が穏やかに暮らしたいだぁ? 誰がそんなこと考えるかバーカ!」
正邪はそう叫ぶと、唾を吐きかけ、怯んだ魔理沙の脇をすり抜けてマジックアイテムを回収。そのまま出口へ向かって飛び出す。
「無駄だ! 私が術を解かなきゃ――」
『亡霊の送り提灯』with『天狗のトイカメラ』
提灯の効果で術を躱すと、一挙に速度を増し、そのまま外へ飛び出す。
魔理沙はその後を追って外に飛び出るが、正邪の姿は急速に沈んだ夕闇の向こうに消えていた。
∴
正邪はひたすら東へ飛んだ。
手配書が回ったなら、どこに行っても追跡の手が迫るであろう。ただ一箇所を除けば。
それに加えて頭の中に残っていたマミゾウの助言が、不意に思い出される。
「こういうのはなんて言ったかなぁ、虎口に飛び込んで虎児を得る、だっけ?」
その正否を答える者は無いが、次の潜伏先の当ては決まっていた。
辿り着いたのは博麗神社――の手前の杜の中。
そこでは地隙の陰になった風穴が口を開けている。
「またここに来るなんてなぁ。さて、何日持つかな」
あの世巡りをするならば、天上の冥界、白玉楼へ向かうか、妖怪の山から中有の道を抜けて三途の川へ至るか、普通ならそう考えるであろう。
しかし正邪が目指すのは、地獄の跡地。ここでもまた、天邪鬼のサガが出た。
だが正邪は、異変の前にここで盛大に事を起こしている。
まず旧地獄に至るまでに多く住まう土蜘蛛達こそ、正邪に積もる恨みを抱いていよう。幻想風穴という虎口に飛び込んで、そのまま噛み砕かれても文句の言えない立場だ。
「アイテムを使えば、行けるだろう」
そんな呟きも反響する風穴。その先には、巨大な縦穴が広がっていた。
旧地獄への降下は驚くほどすんなりといった。もちろんマジックアイテム頼みである。
「さて、ここからが問題かな」
まず縦坑からは距離を取りたい。しかし旧都を抜けて潜伏できそうな奥地へ向かうには、まず橋姫の在する橋を渡らなければならない。
正邪は橋守の姿が無い事を期待し、マジックアイテムを携えてそこまで進む。
姿を現す朱塗りの橋。そこに正邪はまぼろしを見る。
瘴気など含まない清々しい風が吹き渡り、橋の下には澄み渡った川の流れ。その水面が映す緑に顔を上げてみれば、そこには青々とした森が広がっている。
何者による幻惑かと、正邪はその光景を、己の五感一切を信じようとしない。そこに居る、一人の人物の姿以外。
「へへっ、早速かよ……」
目を向けた先には正邪が懸念した人物、欄干に寄りかかる一人の乙女の姿があった。
明けぬ夜を征く 第3話
全周に弾幕を転回して退路を局限させつつ、避けた所へと体内の魔力すら封じ込める撮像術を叩き込む。スペルルールでは御法度レベルの、やはり不可能弾幕水準のスペル。
正邪はまず、ばらまかれた弾幕を切り抜けると、ひらり布を用いて撮像術を回避。しかしにとりの方には、多数の流れ弾が迫る。
「ちょっとちょっと、なんだってんだよ!」
にとりは無力化された射撃を中断し、防御型のスペルである『オプティカルカモフラージュ』の障壁を展開し、自身に降りかかる弾幕を防御。
正式な妖怪の山の一員であるにとりが不法侵入者である正邪を迎え撃つのは、正当な行為と言える。むしろその存在を認めておいて素通りを許すなど、却って責めを負おうという話になりかねない。
その正当な行いをしているはずなのに、受けるのは巻き込まれての無差別攻撃。にとりにとってはたまったものではないし、憤るべき場面だ。
それに河童にも、その縄張りの内でなら自治権はある。それも頭越しにされては流石に我慢ならぬと、にとりは文のスペルの時間切れを見て『オプティカルカモフラージュ』を意図的に効力停止。
「こんにゃろ! いくら天狗様でもこんな横暴許せるもんか!」
そう啖呵を切って、背負ったリュックの下に手をやると、両手に大型の拳銃型水鉄砲携えてスペルを宣言、
瀑符『ケゴンガン』
「あっちもこっちも、鬱陶しいんだよ!」
左右の銃先をそれぞれ正邪に、文に向け、瀑の名に見合った水流を浴びせる。
正邪は頭上から迫っていた文に向けていた注意を姿勢と共に翻し、にとりの姿を下方、視線の端に捉えると、再度ひらり布を使用。
水流を避ける正邪。にとりは先ほどのスペル回避時にひらり布の効果を見抜き、それに惑わされず、水流を浴びせ続ける。
主指向方向は正邪。ついでに銃先を向けられた程度の文は、己の飛行能力のみで易々とケゴンガンを回避。更に木や岩に当たって砕け、妖力を纏ったままの無数の飛沫もひらりひらりとすり抜ける。
にとりの意図は文を追い払う事にあったため、その姿が離れたのを見て銃先を両方とも正邪に集中させる。
正邪はケゴンガンの切れ目無い射撃に焦る。ひらり布の効力発揮時間が決まっているため、このままではどうしても、次の使用まで被弾を余儀なくされてしまう。
それは攻撃を加える側のにとりにも同じ事が言えた。今撃ち出しているのは水妖エネルギー。ただの水鉄砲よりは持続性があるが、それもまた限りがある。
ひらり布の効果が停止するのとケゴンガンの射撃が中断したのは、ほぼ同時だった。
にとりが繭形タンクのカートリッジを交換しようと左手の銃をしまい込んだ瞬間、正邪が気弾をバラ撒きながら突進。
「こんちくしょぉぉぉ!」
「ひゅいっ!」
にとりはスペルも妖術も行使する間も無く、通常弾幕を展開。正邪は被弾覚悟でそのままにとりに激突――
「やかましいガキが! お前が道を開けろ!」
――しなかった。
にとりの天地が反転し、宙に身を浮かす為に発揮していた妖力がその身を大地へ誘う。これは正邪の能力ではない。それはあらゆる妖術と同様に、小槌の魔力が喪失すると同時に取り上げられたままになっている。
今の現象は、ひらり布をにとり本人に対して用い、本来彼女が飛んでいた方向から明後日の方へと逸らしたのだ。
下にすっ飛んでいくとは思っていなかった正邪。しかし結果としては最高、の一つ下。
「チッ、命拾いしたな」
偶然か否か、にとりは辛くも地面に叩き付けられるのを免れ、沢の流入口の小さな滝壺へ突っ込んでいた。ただし河童とは言え、水面に衝突した衝撃もあって沈んだまま。
それを尻目に逃げようとする正邪。そこへ一連の戦闘から一旦は距離を置いていた文が戻る。だが正邪を追うのは断念。
自身が直接そうした訳ではないものの、間接的ににとりが被害を負う結末を招いてしまった。にとりへの口止めも考えているが、それ以前にこの状況を看過し、彼女の身に万一の事が起こった場合の方が厄介だ。
衣服を纏っているだけなら、それは死と共に諸共消えて無くなってくれるであろう。衣は魂の一部ともなり得、かつ、魂は妖怪の主体。そして外道たる妖怪はこの世に残すべき物を持たないのだから。
だが彼女の場合は、背に負った鞄やら機械類やら、痕跡が大量に残る。いずれにせよ、死人に口なしとはいかない。
正邪の姿はもう木々の向こうに消えていったが、それに代わってどんな獣より素早い足音が近づく。
「文様!」
椛は事の次第を千里眼で観察していたため、状況はおよそ理解している。文がかなり強引に割り込んで、このような結果を招いたのも。
では己がにとりの救護を。そう滝壺に向かおうとした椛を、文は止める。
「椛、天邪鬼はあなたが追って。妖力の残滓を辿ろうとしても、痕跡が弱すぎて難しい。ここはあなたの眼の本領発揮よ。でも、分かってるね?」
一瞬「ヲフ」と犬のような鳴き声を上げようとして、椛は留まる。
「もちろん!」
確かに意図を理解してそう返し、椛はすぐに駆け出した。
殺すよりも怪我を負わせた方が有効だとは考えていなかった正邪。一手遅れた椛の追跡には気付かないまま低空を飛び回る。
地の利など一切無い山中、どちらに向かえばいいのかも分からなくなっている。山には旧地獄の鬼達と同様、独立独歩の妖怪がいるとは聞き及んでいたが、そもそも自分でも、どこを目指していたのか分からない。
とりあえず尾根をひとつ越えてみれば状況も変わるかと、意図せず妖怪の山中枢に変針した時だった。
正面に現れる妖獣の影に、進路を遮られた。
白狼天狗の存在自体は聞いた覚えもあったが、その姿までは知らない。すわ追っ手かと即座戦闘態勢。
そんな正邪の様子を見た影は、戦意が無い事を示すため両手を挙げつつ、たしなめる。
「儂は敵じゃない。それにしても見たところ、苦戦しとるようじゃのぉ」
森林特有の明暗のコントラストから正体が掴めずにいたが、立ち止まって目を慣らしてみれば、それが自身の聞き及んだ白狼天狗の特徴と一致しないのに正邪は気付く。
「お前、寺に住み着いていた化け狸!」
その通り、と言わんばかりに身体と同じほどもある大きな尾を宙で左右に揺らしてから、化け狸――マミゾウは訂正を加えつつ応じる。
「儂はちょくちょく軒先を借りに行ってるだけで、別に住み着いとる訳じゃないがな。ときにあんさん、こんな所に来てしまって大丈夫だったのかな?」
「何の話だ」
当然心当たりはある、しかしマミゾウはそれを知らないはず。まともに取り合うつもりも無いと、脇を抜けて飛び去ろうとする正邪を、マミゾウが呼び止める。
「いや、例の黒白魔法使いがあんさんを探しとったんでな。逆さ城にも攻めてきた霧雨魔理沙じゃ、知っとるじゃろ?」
これは正邪にこそ寝耳に水だった。
「アイツが?」
一体どんな意図で、自分の行く先を知られたが故の行動か。それにしてもなぜわざわざ、自ら危険だと言った所に来るのか。時間と追っ手に追われた正邪には答えが導き出せない。
「まあまあ、ここが危険な場所だというのはよぉく分かったじゃろうて。そこでじゃ、このピンチを切り抜けるのにちょっとした策を授けてやろう」
するとマミゾウは、右手にひらり布を左手に小さな地蔵を取り出す。正邪は驚き、腰に提げた麻袋をまさぐる。いずれも自身の持ち物であるマジックアイテムなのに、それらがいつの間にか失せていた。小さな地蔵は名付けて『身代わり地蔵』、その名の通りに所有者へのダメージを皆無にするアイテムだ。
相手は化け狸、化かすのはお手の物。そんな妖怪に手元のアイテムを盗られた程度で驚くのは天邪鬼の名が廃ると、正邪は脂汗を流しながらも声音を落ち着かせる。
「どうやってギッたのかはどうでもいい、それがどうした」
「いや、これだけじゃが?」
これだけ、マミゾウは両方の手それぞれにアイテムを持っているだけ。それだけだった。
「察しが悪いのお。手が二つあるならアイテムも二つ扱えるじゃろ」
言われてみればその通り。
魔力の消費はアイテムに貯えられた分が主で、正邪が使用時に消費する妖力はそこまで大きくない。二つ同時でも扱えなくはない理屈だ、完璧とはいかないが。
「たかだかこの程度の事に気付かないなんて。くそっ、礼は言わないぞ」
「礼を言われたいが為にお前さんに親切にしてやってる訳じゃないからな。そんなもんはいらんよ。折角じゃから、あっちこっち引っかき回して貰えたら楽しいと思っただけじゃ。まっ、妖怪の山はちと逸りすぎだったかも知れんがの。そこまで生き急ぐなら、いっそあの世巡りをしてみるのもええじゃろう」
それも何かのヒントか。マミゾウの思惑がどこにあるのかは不明ながら、それはアドバイスにも思える。ただ旧地獄での件もあり、とてもそこに踏み出す切っ掛けにはし辛い。
一体何を考えてそんなに情報を寄越そうとするのか。その意図を問いただそうとした正邪に、最後のアドバイスがもたらされる。
「ほれ来たぞ。儂はここでおさらばするが、まあせいぜい頑張っとくれ」
追っ手を撒ききれた訳ではなかったのか。正邪が一瞬だけ来た方を向き、そちらから逃れようとまた正面を向くと、マミゾウの姿はそこには無かった。
流石は狢の総大将と言うべきか、椛が正邪を補足した時には、自身を少し大きめのヤマガラに化けさせ、既に木々の梢の中に消え去っていた。
椛もそれは認識していたが、今はそちらへの用は無い。
「けっ、まあいい、やってやる」
正邪が麻袋に手を突っ込んでみれば、マジックアイテムは元通り。そこから改めて二種のマジックアイテムを取り出す。選定に理由など無い、行き当たりばったり。
椛を背にしながら、逃げもせず空中で留まる正邪に、椛は脇差しほどの警棒を向ける。
「天邪鬼! 御山への侵入など狼藉の廉で、お前を捕縛する。神妙に縛に就け!」
正邪は乱杭歯をギチギチと鳴らしながら、
「はっ! お前がかよ、ワンコ! いいさ、とっととぶっちめてやるから掛かってこい。今度は負けやしない、負けるもんか!」
溜め息にも悲鳴にも思える不快な声で言い放つ。
椛の動きは、その啖呵を受けて僅かに後れを取った。
今度は。
今まさに敵と対峙しながらも、その言葉がいつを指すのかに考えが及び、椛は逡巡する。確かにかつて、天邪鬼とは戦った覚えもある。
ずっと古い話であるが、今この姿を取っているのも、年老いた山犬が天邪鬼に射殺された所から始まっている。そもそも千里眼――天眼通に非ずの浄天眼は、天邪鬼の如き勿怪を追随するため、天部におわす方より与えられた物。少なくとも転化転生したばかりであった頃の山犬にとっては、天邪鬼追捕こそ至上命題だったかも知れない。
正邪は意図せず生じた椛の隙を突き、飛び去りながら弾幕を展開。
意識を正邪に戻した椛は、咄嗟に背負っていた盾を構え、殆ど全身をそれに隠して第一波を凌ぐ。スペルを用いたでも妖術を用いたでもない気弾、貸与品の盾でも易く防げた。
「この、抵抗するのなら!」
気弾の第二波を防ぎながら正邪の前方に躍り出て、頭を押さえに掛かる。
椛は背側に佩いた大太刀を逆手に抜くと、風切り音を鳴らしながら手中で半回転。その刃に法力を乗せながらスペルを宣言。
牙符『咀嚼玩味』
刃は今の椛にとっての牙であり、唯一にして最大の護り。
扇状に弾幕を展開して正邪の進路を局限。周囲の大木が着弾に応じて激しく揺れ、穿たれる。その威力を正邪が目にするよりも先に、上下に光弾の壁が出現する。
空中に形作られたのは犬狼の腭。これも当然、不可能弾幕水準のスペル。椛が刃を一振りすると、それら弾幕の牙は正邪を噛み砕かんと閉じてゆく。
退くか進むか。正邪がいずれに向かうにしても、弾幕の口腔から逃れる必要がある。しかし手元に準備しているのは現状に適した『ひらり布』ではない。正邪は意を決して前進。にとりの時とは違い、運任せの突撃に賭けようと決心。その前に僅かな布石を打つ。
「大したモンだよ犬ころ! 人に飼われてのんびりしてた頃とは違うみたいだなぁ!」
そんな覚えは、確かにある。それも山犬にとっての“始め”であったからだ。ではこの天邪鬼は己が知るモノなのか。
天邪鬼には複数の形態があり、それぞれに伝承類話が無数に乗っている。そういった物の中に、犬が天邪鬼を退治する物があったかも知れない。
いや、そんな話には覚えが無い。それより己はなぜ今、そんな事を考える。
正邪自身には、訳の分からない話で混乱させる程度の意図しか無かった。しかし適当に打った布石は、彼女の想像の遙かに上をゆく結果をもたらした。
「ははっ! 所詮ワンコはワンコだな!」
椛の困惑に呼応して勢力を減じた弾幕をすり抜けながら、正邪は気を大きくして喚く。
椛はすぐに自分を取り戻し、弾幕の閉塞を早めようと妖力を込める。腭は得物を弄んでいたかのように、瞬く間に閉じた。
(墜としたか?)
残心を取り、光弾の群れに磨り潰された正邪の方を見る椛。ここで見逃して、またあらぬ方へ行かれてはかなわない。
見逃す心配だけはすぐに解消する。
「こん畜生が――」
光弾の壁から叫びながら現れた正邪に、今のスペルのダメージは無い。左手に携えた『身代わり地蔵』の効力により、ダメージを皆無なまでに減じていた。
椛の攻撃もこれで終わりではない。弾幕の腭を抜けて来た者は、白刃の衝撃で迎え撃つ。
「喰らえ!」
白刃が振るわれることにより発された衝撃を正面から圧し、進む正邪。その右手には蒔絵を施した小槌が握られている。
打ち出の小槌は既に取り上げられている。この小槌は紛い物に違いない、虚仮威しだ。
椛のその判断は、半分まで合っていた。失敗は、その小槌が先般正邪が旧地獄に持ち込み、本身の威力を見せつけるのに使用したレプリカではないのに気付かなかったこと。
椛が刃を戻した時には、正邪の姿は文字通りに目と鼻の先。そうであっても対応できるだけの力量を備えてこその白狼天狗。懐に入り込んだなら、柄で殴り、蹴り上げるだけ。
ただし椛はあえてそれをしない。
――分かってるね?
文の言いつけは十二分に理解している。始めから、捕らえる気も倒す気も無い。目的はあくまでも、これ以上目立つ行動をする前に追い返すだけ。
戦いながらも、椛の眼は先に新たな影を捉えていた。
ならばここはあえて受け、負けてやればいい。
妖怪の山という確固たる組織の中に在する椛は、己の勝敗よりも、課せられた役目を全うすることこそを――今それを下したのがその組織から少し外れた人物であるのを承知しながらも――至上と考えている。
刃を後ろに置き、盾を前に突き出す。正邪の次の一手は小槌の打撃に相違ないと、全身の動きから識別していた。
次の瞬間、振り下ろされたのは確かに打ち出の小槌だった。しかし椛には、その小槌の姿が山の神社が据えた御柱にも匹敵する強大さに見えていた。
いや、逆だ。椛が受けた衝撃が余りにも大きすぎたため、それまで見ていた小槌を巨大な神槌と、遡行して錯覚したのだった。
マジックアイテム『打ち出の小槌(レプリカ)』。それは形影として打ち出の小槌の力を招いたわけでなく、ただ強力な鈍器として機能していた。
思いの外強烈な衝撃に、油断していた椛は耐えきれず、背中から地面に叩き付けられた。
椛が目を覚ますと、そこには文とにとりの姿があった。
太陽は稜線に隠れたばかりで、周囲は明暗のあいまいな世界になっている。
そう時間は経っていないのを認識してから、椛は文に話しかける。
「すいません、不覚を取りました」
「あれ、わざと負けたんじゃなかったの?」
嫌味でなく文は、椛が堂に入った芝居をしたものだと思っていた。椛の方もその通りで、あの瞬間まではそれに徹しようとしていたのだ。
「はい、そのつもりでは当たっていたんですが。マジックアイテムのバリエーション、結構増えているみたいですね。打ち出の小槌を模した物で、この通りです」
十分に身構えていれば、軟着陸して負けたふりで済んだのに。油断したのは本当だった。
椛の心中にそれ以上は踏み入らず、文は尋ねる。
「……“それ”からは、例の魔力は感じ取れた?」
「分かりませんでした。あれを認識したのが突然だというのもあったので」
少なくともそれが、旧地獄へ持ち込まれた物と同一の器物でないのだけは判別できた。これだけは、二人とも揃って安心できた点だった。
「ところで天邪鬼は、黒白と合流を?」
「ええ、間に合ったみたい。今のところ目撃者は無し。ひとまず撃退には成功ね」
同時に大きく息を吐き出す二人に、とても心穏やかには見えないにとりが割り込む。
「ちょっとお二人さん。てか天狗様、あたしは口止めに同意しちゃいないんだけど」
「言ったでしょう。これは今後の幻想郷の如何に関わるかも知れない事態なんで協力して下さいと。私も当初は賛同しませんでしたが、よく考えてれば妥当だと分かりますから」
「天邪鬼の背景を探り、黒幕を見つけ出して叩き潰す? 知らないよ、そんなの」
にとりにしてみれば、幻想郷の如何などと言われても、非現実的な話でしかない。
幻想郷の内外を行き来するには、妖怪の山にあるという抜け穴か結界のほころびを抜けるか、その他の不正な手段を取るぐらいしか考えられない。
それらの手段を取れない者にとって幻想郷の存亡は自身と一蓮托生。にとりの身も直接関わる。そうであるからこそ、事が大きすぎて、そんなものは妖怪の山の上層部か博麗の巫女でなんとかしてくれとしか言えない。
しかし文は、その妖怪の山という組織への口止めも、にとりに提示していたのだ。
「だから納得できないんだよ。スペルに巻き込まれた件は、お互い様だけど」
言いながらも、にとりは甲斐甲斐しく椛の手当を進めている。にとりとは将棋仲間という程度に付き合いもある椛も、そうされながら真意を明かせないことに忸怩たる思いを抱く。
ここでにとりを抹殺して死人に口なし、という手は、先ほど見過ごせなかった時点で二人の選択肢には無い。文としては、彼女より先に正邪にアプローチできなかったという時点で、自身の失敗だと考えていた。
「分かりました、仕方ありませんね。ではせめて、私があなたに口止めをしたという事だけは、せめて黙っていて下さい」
にとりがチラと椛の方を向くと、椛も軽く頭を下げて拝む。
「はいはい、分かりましたよ。ついでにわざと天邪鬼とやらを逃がしたことも黙っててやる。でも奴がここに入り込んだ件は、然るべき筋から上申するからね」
「それは随意に」
文はにとりの誓約に、僅かな期待も抱かなかった。言葉通りに一部を伏せることすらも。
「やはり説得は駄目でしたね」
「あのシチュエーションじゃ、黙ってろって言うのが無理ね。私も焦ってやり過ぎたし。それに、にとり個人はどうか知らないけれど、種族としての河童には天邪鬼と因縁もあるからね。確執が魂に染みついている種族に一時とは言え[利敵行為をしろ]も難しいわ」
「因縁、ですか?」
河童の元の形態の一つに、術士に使役された藁人形だったという物がある。
藁人形と言っても、橋姫が貴船の杜に打ち付けていた物のように手の込んだ物ではなく、藁を纏めて手足を模した棒を通しただけ粗末な物。これが河童の元になったと言われ、数千ものそれを自在に使役したのが、壱岐の天邪鬼(あまんしゃぐめ)であるという話だ。
――もしそれらを何かに比定させたなら、それはまた別の悲劇の物語となろうか――
「まっ、今更何を言ったところで、出遅れた時点でアウトだったのよ。これからは、奴の件をどう落ち着けるかを考えるわ。なんとか人の目に触れないように進めたいけど……」
文は樹冠の向こう、夕闇の中に更に暗い影を認め、椛にもそうするよう促しながら降下。
視線の先には、ここで目に触れてはならない人物達が悠々と帰途を辿っていた。
正邪を導いて飛ぶ魔理沙は、森の中から鋭い妖力を叩き付けるモノを知覚していた。向けられた意思は「悠長に飛んでいないでとっとと帰れ」との忠告。
ただ存在は知覚されても、意図は魔理沙に伝わっていなかった。
「ったく、なんで行くなって言った所に行くかな」
これも悠長な様子で正邪に問いかける。天邪鬼にそんな事を言うだけ野暮というものだが、それでも口に出さずにはいられなかった。
「へっ。お前が行くなって言ったから、逆に行きたくなったんだよ」
納得したくもない、納得できる答え。
行けと言われれば行かないという話でもなく、結局正邪が幻想郷を巡る間、魔理沙の忠告を聞き入れない限り、いずれは辿り着いていただろう。
「本当にお前は、誰かさんにそっくりだよ」
「誰のことだ? 私そっくりなんて相当捻くれた奴だな」
「ああ、本当に嫌になるぐらいにな。ところで、私の忠告を無視してまでここまで来たんだ、何か成果はあったんだろうな」
「新しいマジックアイテムは無かった。今日は新しい潜伏先を探してたんだ」
「おいおい……」
こちらにいくらか企みがあるとは言っても、彼女にとっては平穏無事な宿であるはず。わざわざそこから出て、あえて危険地帯に乗り込むなどとは。魔理沙は天邪鬼というモノの扱いづらさを、つくづくと思い知らされる。
「もっとも、河童は出るわ鴉は出るわ犬ころに噛まれるわ、ろくな目に遭わなかった」
「そりゃそうだろう、生きていただけマシだと思え」
魔理沙は、正邪が言う鴉と犬ころが、文と椛である事を祈る。
彼女らならば事情を知っていると聞いている。問題は河童だが、妖怪の山では射命丸も比較的上位種とは聞いているため、常からつるんでいる椛も含めて彼女らだったのならどうにかするであろうと。
妖怪の山の方は、もう祈るより他ない。今は闇夜に紛れて正邪を連れ帰るのみ。
これら魔理沙の懸念の先は、正邪の追跡がおおっぴらなものになること。
これまではただ迷惑を振り撒きまくった妖怪という話だけで、各所で警戒していた者が迎撃、あるいは既に被害を被っていた者達が各個前進で襲い掛かっていただけだったが、妖怪の山は確固たるテリトリーを持つ上に、情報の発信能力がある。
そこで考えられる最悪の事態は、正邪の手配書の発行。
もしこの懸念が現実となれば、現在荷担している企みは、大きく後退するかご破算となる可能性も高い。
魔理沙の荷担する謀。それは先般の輝針城異変に係るもの。
――「天邪鬼の背後に黒幕の影あり」
そう言い出したのは、幻想郷の妖怪の賢者の一人である紫だった。そしてこれを知らされているのは、今のところごく一握りの人物に限られている。
直接異変解決に当たった霊夢と魔理沙、紅魔館のメイド長十六夜咲夜。輝針城異変に近しい時期にイリーガルな手段で外の世界から入り込んだため、まず容疑を向けられたマミゾウ。それに妖怪の山でも一応は話が通じると思われる文と、その協力者としての椛。
もしかしたら、咲夜からは主人であるレミリア・スカーレットに断りが入っているかも知れないが、紅魔館としては事が大きくならない限り静観するであろうと見込まれていた。
先の異変のもう一人の元凶、針妙丸自身は、正邪の口車に乗っただけであり、その背後に何か居るかも知れないなどとは思ってすらいなかった。――
魔理沙も紫のうさんくささは思い知っていても、今回の件については納得がいった。何より幻想郷の管理者然とした紫が、幻想郷の如何に係る話をするのは自然であったし、それに貧相な地力しか持たない小者妖怪を、妖怪の賢者とまで称される紫が執拗にいたぶる理由もあまり思い浮かばない。
紫の言うとおり、正邪の背後に幻想郷へ悪意を抱いた人物がいるのなら、これをどうにかしたいと思うのは、魔理沙の素直な心だった。
里の商売人の子として生まれ、しかし夜空の星に魅せられ魔法に傾倒し、家出してまで才能を磨く事を決心して、今に至っている魔理沙。家族や里の知人に未練があるとも無いとも口にはしないし、今の生活が快適かどうかなどとも語らない。しかし、それらを口にしないのは、彼ら彼女らを今も強く思っている事の裏返し。
(もし幻想郷にそんな奴が居るのなら――)
「でも、収穫はあったぞ」
不安と懸念にまみれた心の整理を進めていた魔理沙は、正邪からの語りかけに、胸中の動揺などおくびにも出さずに応じる。
「マジックアイテム以外の収穫が?」
「ああ、お前には関係ないけどな。これで少しは私も強くなった。化け狸様々だ」
マミゾウの動きに、魔理沙は首を傾げる。
彼女も紫と同じく、この度の企みの首謀者である。それがここでヒョコヒョコ出て来て、何か策を授けた。その思惑を魔理沙は推し量るが、嫌な方向にしか考えが向かない。
(単にマジックアイテム探索を助ける気か。それとももっと強力な奴らを宛がって、コイツが黒幕の所へ行くのを促す気か)
または、いくら化け狸とはいえ、天狗の目がある危険な場所で張っていたのを考えると、妖怪の山へ正邪が訪れた時点で、天狗の動きがどう転んでもいいように逃走に寄与する策を授けようとしたのか。
いくらでも可能性は考えられる。折を見て直接訪ねるまでは、考えるだけ無意味だろう。
「私に関係ないなら聞く意味も無いな。それはおいおい見せてくれ」
「ああ、いずれ見せてやるよ」
おおかた、また寝込みを襲う気であろう。何度撃退しても懲りないのだからしょうがない。これも天邪鬼のサガかと魔理沙は諦めている。あとは粛々とトラップマジックを張って安眠を確保するだけ。
「いずれじゃなくて、今見せてもらうことになりそうだ」
魔力感知術式を展開していた魔理沙は、自身を捉えようとしている何かの存在を知覚する。千里眼ほど精細ではないが、ただそれが向いているのを知るだけなら十分事足りる。
「正邪、私を撃ちまくれ。ただし本気ではやるな」
「急にどうしたんだ?」
「誰か来る、もう視られてるかも知れない。とりあえず私を襲っていた風に装え。危なくなったらちゃんと助けてやるから、さっき言った収穫でもってまずは一人で戦ってみろ」
正邪と仲良く飛んでいる場面を押さえられたら、魔理沙もしばらく身を隠さなくてはならなくなる。少なくとも紫の謀が終わるかして、事情が明らかにされるまでは。今の指示は、そういった事態に至らないように練っていた腹案の一つだった。
「あいあい、私としても寝床が無くなるのは都合が悪いしな」
魔理沙の表向きの意図は一応正邪に伝わっている。天邪鬼がその意図に素直に従うかは、また別の話だが。
正邪の応答を聞き、魔理沙はすぐに距離を取る。咄嗟後方からの全力射撃。
「お前! 全力でやるなって言っただろ!」
「ははは、迫真の演技だろ」
天邪鬼だからで何でも納得してはいられないが、魔理沙もここは我慢する。それに正邪の射撃自体は全力だが、避けた先への射撃の指向変更、彼女自身の飛行は単調かつ悠長。確かに“演技”ではあるようだ。
魔理沙も回避機動を繰り返す。遠目からなら魔理沙が追われてるように見えるだろう。
追跡者はまんまとそれに引っかかったが、
「待てー記事ネター! いや天邪鬼ー! 黒白なんてほっといて私の取材を受けろー!」
そう叫ぶ追っ手は、はたてだった。
「……天狗かよ、最悪だ」
たとえここで正邪が勝って逃げおおせても、妖怪の山が騒ぎ始めるのがほぼ確定した。
∴
普段のラフな装いを改めて正装に身を包み、幅三間もある薄闇の廊下を粛々と歩む文。
夜半から今まで、時間の概念が飛んでいる。今し方、晨朝(じんちょう)の鐘が遠くで鳴り響くのを聞き、ようやく刻限が知れた。
ここは西塔(さいとう)と称される区画の中核にある、八葉堂という名の伽藍。妖怪の山の行政機関である。早朝ではあっても、真昼の門前町の賑わいと真逆の威勢と威厳に満ちている。
そんな時間にこの様な場所に文が召喚されていた理由は当然、正邪の妖怪の山侵入と、それへの対応の顛末の説明の他に無い。
河童からの申告への対応にしては異常なまでに迅速に話が進むものだと、召喚を受けた当初は驚いていたが、あの後、はたてが文字通りの突撃取材を敢行したと聞いて納得した。
そのはたてと、先に対応に当たっていた椛、そしてにとりへの聴取は終わっている。(一応にとりは、口止めの件を言わないという約束は守ってくれたようだ)
侵入者排除は文の職責に係る話ではなく、妖怪の山のモノ全ての権利であり義務であるとも言える。それを見つけ次第追い払った事に関して責めがあったのではない。
ただしそこから先こそ、文の職責に係る話。
「呼ばれた時から嫌な予感はしてたけど、これはちょっとねぇ……」
やはりと言うべきか、先般の異変の元凶が妖怪の山へ忍び込んで来たのに対して、妖怪の山上層部が黙っている理由は無かった。
気の重さに背を丸め肩を落とした文の後ろから、しゃなりしゃなりとした足音が近づく。
「どうしたのかな? 一貫坊(いっかんぼう)」
一貫坊とは、かつての文の名乗り。その身の軽さから、修行していた時に与えられた僧坊の名がそれで、そのままそれを称したのだが、今はその名乗りを知る者、そう呼ぶ者は極めて限られている。(最も付き合いの古い者達ですら、今は射命丸あるいは文と呼ぶ)
話しかけてきたのは、紫衣(しえ)を纏い、優美な長髪を揺らした人物。線、特に肩の細さ、物腰の柔らかさから、容姿からは男とも女とも判別しがたい。そして今、文を呼び止めた声も、どちらかと言えば女性的である。
ただ、妖怪の山は護法の聖地。男性の立場の方が圧倒的に高いこの地で、女性が高位に在るはずもない。そう“彼”は妖怪の山の権力者の一人だ。
文は丸めていた背を伸ばしてから振り向き、礼拝して応じる。
「これは鞍馬(くらま)様。いえ、先ほどの天邪鬼手配の件、私の如きが差配してよいものかと」
この人物は鞍馬僧正坊(そうじょうぼう)。かつて鞍馬山を治めていた権現であり、その験力や見識、何より信仰上の実績などからして、天魔を除けば妖怪の山の事実上のトップと言える。
「何を言っておるのか、それがお前の勤めであろうが」
叱責の声を上げたのは鞍馬ではない。
文に存在すら認識させず、風の如き静けさを以て佇むのは、鞍馬とは全く対照的な剃り上げた頭に強ばった肩、普段からそうしている通りの胴丸を身につけた人物であった。
「飯綱(いづな)様。此度の件、反対に回った貴方様が、今度はこれをよく進めよと仰るのですか」
「天魔様の御前にて、我ら八葉の合議を以て下された決だ。一度これと決まった事を、後からとやかく言う筋は無い」
日本第三の天狗と祀られ、中世の武将からの信仰も厚かった大権現、飯綱三郎。自他に対して極めて厳格であるのが、その面にも現れている。
そう、鞍馬同様に彼も妖怪の山の最高意思決定機関『御八葉(おはちよう)』の一員であり、文の所属する『書陵課』の上級部署を束ねる『宗務総長』でもある。
――八葉とは、大日如来が座する蓮華の花弁の数。その花弁には、四菩薩と四如来の八尊が位置している。妖怪の山に比定される八ヶ岳の八峰、それに富士山頂の八神峰も八葉と称されるほど、この数字は妖怪の山の信仰に深く関わっている。
この地では、その中央に天魔を置き、八葉それぞれに権現が座しているのだ――
ちなみに鞍馬などは、その見た目とは裏腹に、荒事すら担当する実働機関である『検非違寮』や『執行部』などを直々に指揮している。
その様な最高位の八人の権現のうち、二人を前にしても、文はさして緊張していない。西塔での文の地位は末端に近いが、幻想郷でも相当に古い人物であるというのが、年功序列上等の組織の中で立場をかなり強く補強している。
組織上は頭を下げ、その命令には従うが、それはあくまで組織の中に限っての振る舞い。あえて高位を目指さないのも、フットワークが重くなるのを嫌うからだったりする。
何か起これば、その速度で誰よりも早く駆けつける。それが今の文。妖怪の山での地位など、安定した飯の種ぐらいにしか考えていない。
「はあ、私も飯綱様と同じ意見を述べたのですが、なぜ御八葉はこの度の件を公にしようとするのです? 御山へ侵入者があったなど喧伝すれば、却ってその名に疵を付けようというものだと思うのですが」
「くどい!」
さすがに強面の彼にピシャリと一喝されると、文も身をすぼめてしまう。
「まあまあ、飯綱殿。彼女の言う事ももっともですよ。ですが一貫坊、我々は天邪鬼の追討を公とすることで、御山へ害なす者への見せしめにしようと、そう決を下したのです」
もっともな話ではある。
正邪は既にあちこちの組織の勢力圏に入り込んでは、縄張りを荒らし回っている。今更、妖怪の山に入り込んだのを周囲に知られた所で恥にもならない。逆にここで幻想郷全体に檄を飛ばせば、妖怪の山という勢力が幻想郷でイニシアチブを握っている様にも見えよう。
「ふん、相変わらず射命丸には甘いのですな、鞍馬殿は。こやつなど精々、新聞作りの腕と人里に近しいことぐらいしか取り柄など無いのに」
ついでに誰よりも速く飛べるぐらいですかね、と文は茶化したくなる気持ちを抑えつつ「全く以て仰る通り」と頭を下げる。
「いえいえ、叶うなら執行部へと引き抜きたいぐらい優秀ですよ。頂けませんか?」
「残念ながら新聞作りの巧さというのが、情報の収集能力、発信力に直結するものですからな。書陵課も人材が不足しておりますので、已む無くこちらに置くしかないのです」
それは残念と、言葉通りに口惜しそうな貌で言う鞍馬。
飯綱の方はまた文の方を睨むと、改めて下命する。
「権令史(ごんのれいし)、射命丸。急ぎ天邪鬼の手配書を作成し、早々に天邪鬼追討の周知を行え!」
「はっ!」
ここで時間稼ぎなどしてもどうにもなるまい。こうなれば紫達と共に、実態解明を急ぐのみと、文はひとまず手元の仕事に集中する道を選んだ。
∴
妖怪の山の尋常ではない動きの早さは、魔理沙もすぐに思い知ることになった。
昼に人里に出でて、所用を済ませて帰ろうとする頃には、大通りをすれ違う人々の手にすら正邪の人相書きが渡っていたのだ。
道ばたに捨てられていたそれを拾い上げれば、そこには人相書きの他、これまでの悪行が子細に記されていた。ついでに、生死を問わず無力化すれば褒賞を出すなどとも。
人間が天邪鬼の手配書を受け取ったところで、ただ怖がるか自警団が備えを固めるだけにしかならない。故に、これは他の妖怪への流布が主体であろうとは、容易に想像できた。
(そりゃまぁ、こうなるよな)
先の「妖怪の山へ行くな」という忠告、実は文からのものであったが、こうも素早く言われた通りになるとはと、二重に驚く魔理沙。(ただし、この手配書が文当人の手による物だとは露程にも思っていない)
とりあえず今は、どこか別の隠れ家へ送り込むか。それともいっそ、正邪の背後関係を探る話をおおっぴらに進めるべきか。
前者の当ては無いでもない。後者であるが、誰が紫の言う黒幕か分からない以上、協力者が増えるほど証拠隠蔽のリスクが大きくなる。
採るべき手立ては前者かと、すぐに腹を決める。
その前に紫達と合流して相談をと博麗神社に行ってみるが、そちらでは針妙丸と霊夢が縁側で仲良くお茶をしている光景があるだけ。紫かマミゾウの行方を聞いたところで「知ったことではない」と塩を撒くかの如き対応。霊夢としては関わりたくないのが本音。
(霊夢の感働きがこれだと、紫の心配も杞憂かもなぁ……)
などと魔理沙は今更に思いもするが、彼女の勘が鈍ることもままあるため、それは頭から振り払って帰途に就く。
「おーい、帰ったぞー」
廊下のランタンに油を詰め直し、火を付けながら正邪を呼ぶ。返事は無い。
「どうした? 逃げたのかー」
手配書が回った今、ふらふらとほっつき歩かれては敵わない。魔理沙は少しばかり焦るが、警戒用の術式は出入りした者が無かったのを示している。
よく耳をそばだてれば、奥の方からは地響きに似た不快な音。正邪の居室に行ってみれば、正邪は大イビキをかいて寝ていた。
「しっかし、寝顔すら可愛くないってのは凄いな……」
乱杭歯の目立つ大口を開けてそうしているのを見て、年相応に可愛い物好き魔理沙はついついそれを口に出す。
「おい、起きろ」
「フガ?」
寝ぼけ眼で見上げてくる正邪に、魔理沙は手配書を突き付ける。
「ほら、お前が忠告を無視して妖怪の山に行った代償だ。これで満足か?」
写真から起こしたのであろう、特徴を強調して描かれた大写しの人相書き、その端に並べ立てられた悪行の数々を見て、正邪はクツクツと笑い出す。
「……ふふっ、面白いなぁ。こうだよ、こうじゃないと!」
つくづくこいつは天邪鬼だと、魔理沙は呆れかえる。
「言ってる場合か。これでウチで匿うのは難しくなった。近いうちに次のヤサに移すから、準備だけはしておけ」
「準備って言ったって、私にはこれだけしか無いけどな」
机の上に広げられたマジックアイテムに視線を向けて正邪は言う。それが彼女の全て。
ただそれだけ。思い返せばそう、寄る辺も無く暮らし、その末に「弱者が見捨てられない楽園を築く」などと嘯いただけのこと。
その真意はただの私利私欲であろう。そうではあっても、その身の上に同情する気持ちも魔理沙にはある。
「ああ、そうだったな。お前には、それしか無いんだよな」
正邪はその言葉に歯を鳴らすと、魔理沙の胸ぐらに手を伸ばす。魔理沙は彼女の動きに咄嗟に反応し、その腕を取ると、捻り上げながら布団に押し付けた。
「クソッ! 人間のガキが私を哀れむなよ!」
「ああ、悪かったよ。もう同情なんかしない。やっぱりお前は、よく似てる」
「だからそれ誰だよ!」
「私にさ」
拘束を解きながら答える魔理沙に、正邪は怪訝そうな貌を向ける。
「はあ? お前にだぁ?」
「ああ、そう感じるんだ。それは絶対同情とかじゃない。むしろお前なんかに似てるって言われても、これまでなら真っ平だと思ってただろうな」
「それはこっちの台詞だ!」
お互い根無し草のひねくれ者、だからではない。
戻ろうと思えば、魔理沙には親も知り合いも居る。誰かの寝首を掻こうとした試しなど無いし、嘘ばかりついている訳でもない。
「お前、ずっと反抗ばかりしてるけど、どこまでがお前の本心なんだ? 本当は誰にも逆らいたくなくて、平穏無事に過ごしたいんじゃないのか?」
やりたくないから、そうしてしまう。
なぜ天邪鬼がそういうサガを持って生まれたのかは分からないが、自分への危害も、実はそんな思いの裏返しなのではないかとも考えている。
別に正邪に好かれようが嫌われようがどうでもいい。ただそうした正邪の心情の解決が、自分の心情にも連なっているように思えたのだ。
(そう、素直じゃないんだよな)
ただそうするための存在に生まれたからと言ってしまえば、それまでの事でもある。
「はあ、私が穏やかに暮らしたいだぁ? 誰がそんなこと考えるかバーカ!」
正邪はそう叫ぶと、唾を吐きかけ、怯んだ魔理沙の脇をすり抜けてマジックアイテムを回収。そのまま出口へ向かって飛び出す。
「無駄だ! 私が術を解かなきゃ――」
『亡霊の送り提灯』with『天狗のトイカメラ』
提灯の効果で術を躱すと、一挙に速度を増し、そのまま外へ飛び出す。
魔理沙はその後を追って外に飛び出るが、正邪の姿は急速に沈んだ夕闇の向こうに消えていた。
∴
正邪はひたすら東へ飛んだ。
手配書が回ったなら、どこに行っても追跡の手が迫るであろう。ただ一箇所を除けば。
それに加えて頭の中に残っていたマミゾウの助言が、不意に思い出される。
「こういうのはなんて言ったかなぁ、虎口に飛び込んで虎児を得る、だっけ?」
その正否を答える者は無いが、次の潜伏先の当ては決まっていた。
辿り着いたのは博麗神社――の手前の杜の中。
そこでは地隙の陰になった風穴が口を開けている。
「またここに来るなんてなぁ。さて、何日持つかな」
あの世巡りをするならば、天上の冥界、白玉楼へ向かうか、妖怪の山から中有の道を抜けて三途の川へ至るか、普通ならそう考えるであろう。
しかし正邪が目指すのは、地獄の跡地。ここでもまた、天邪鬼のサガが出た。
だが正邪は、異変の前にここで盛大に事を起こしている。
まず旧地獄に至るまでに多く住まう土蜘蛛達こそ、正邪に積もる恨みを抱いていよう。幻想風穴という虎口に飛び込んで、そのまま噛み砕かれても文句の言えない立場だ。
「アイテムを使えば、行けるだろう」
そんな呟きも反響する風穴。その先には、巨大な縦穴が広がっていた。
旧地獄への降下は驚くほどすんなりといった。もちろんマジックアイテム頼みである。
「さて、ここからが問題かな」
まず縦坑からは距離を取りたい。しかし旧都を抜けて潜伏できそうな奥地へ向かうには、まず橋姫の在する橋を渡らなければならない。
正邪は橋守の姿が無い事を期待し、マジックアイテムを携えてそこまで進む。
姿を現す朱塗りの橋。そこに正邪はまぼろしを見る。
瘴気など含まない清々しい風が吹き渡り、橋の下には澄み渡った川の流れ。その水面が映す緑に顔を上げてみれば、そこには青々とした森が広がっている。
何者による幻惑かと、正邪はその光景を、己の五感一切を信じようとしない。そこに居る、一人の人物の姿以外。
「へへっ、早速かよ……」
目を向けた先には正邪が懸念した人物、欄干に寄りかかる一人の乙女の姿があった。
第4章 明けぬ夜を征く 一覧
感想をツイートする
ツイート