楽園の確率~Paradiseshift.第2章 失われたはし 失われたはし 第10話
所属カテゴリー: 楽園の確率~Paradiseshift.第2章 失われたはし
公開日:2017年05月01日 / 最終更新日:2017年05月01日
楽園の確率 ~ Paradise Shift. 第2章
失われたはし 第10話
「波斯国の姫であるが故、『はしひめ』か」(※1)
清明が語る橋姫の素性に、博雅が深く頷きながら言った。
「天竺よりもより西方の民――とは言うがな、この国が興る前には、そちらよりも人が渡って来たのかも知れぬのじゃ。火を焚き、鉄を鍛える者。あるいは田に水を引き、稲穂を育て、多くの民を従える者でもある。そも、大和の民とはなんぞや?」(※2)
「なんと難しい問いをする……」
良民とされない者を除けば、この問いは案外と簡単な物である。しかし博雅はそれが出来ず悩む。
「やはり、お前はよい男だ」
「いや、何の力も無いくせに、哀れむべきでない者にまで同情する、愚か者よ」
激しい雨風の中、牛車は洛中へ戻り、彼らは大内裏へと足を向けるのであった。
「そう、だから私は『波斯姫』」
二人の『はしひめ』の由縁を聞き、綱は呆然とする。覚悟していたつもりであったのに。
それが本当なら、目の前に居る橋姫もまた、大和の民どころかヒトですらない。
「私達は、上代にこの国に連れてこられた。ある物のために、一族ごと」(※3)
数百年も前、ただの少年の綱にとっては、気の遠くなるような昔の話。それを波斯姫――橋姫は、体験してきたのだ。
「上代……」
「この国の巫女王が大陸に、新羅に攻め寄せた時、ある豪族が遣わされたの」
橋姫が言うのは、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の后、神功皇后(じんぐうこうごう)の頃に行われた新羅(しらぎ)征伐(※4)の事であろうか。若いながらも、武家として確固たる家を持つ綱であればこそ、これを知っていた。
「それはもう、記紀にうたわれる頃の話ではないか……」(※5)
ヒトか妖かより、己の生きるよりずっと旧い世の中を生きた者であるという事実に、綱は橋姫との間に恐ろしい隔たりを覚える。それは時間としてより、距離として感じられた。
すぐ側に居るのに、千里も彼方に在る者であるかのように。
天の瓶が割れたかの如き豪雨を掻き分け、清明と博雅は、沓を水に浸しながら歩む。
目指すは内裏の北に位置する大蔵省、主計寮である。
「清明よ! 前に言っていた信仰とは、葛城(かつらぎ)氏に係るものか!」
「そうじゃ! 新羅征伐の折り、波斯人を日の本に連れて来たのが、葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)! それを遣わした神功皇后の母もまた葛城氏、葛城高額媛(かずらきのたかぬかひめ)」
「その葛城氏の神格、一言主(ひとことぬし)を祖神として、南都に奉じたのが、今の賀茂氏で――」
「貴布禰の社は、これも賀茂氏が祀る賀茂川から連なる、水神の系譜じゃ!」
「信仰は民、民は信仰。私達は葛城襲津彦の、葛城氏の手によって、我が神と共にこちらに渡って来たの。そして私は、主神を奉る巫(こうなぎ)」
綱の意識の中で遙かに遠くに居た橋姫は、いつの間にかすぐ側まで歩み寄っていた。これは橋姫から懸命に近づいたのだ。心の中の万里の道を駆けて。
橋姫が真に、万里よりもなお遠い道を辿って来たのを知った綱は、それを受け止める。
「よく話してくれた……ならば俺はどうすればよい、御許のために」
ヒトではなかったかも知れない、だが妖し勿怪ではない。いずれにせよ橋姫は、それを赤心で話してくれたのだ。それだけで綱は、何かが救われた気がした。
これは、己の始めから課せられていた運命やも知れぬ。
今の綱には、主君や父兄へ果たすべき忠孝よりも、強い使命感が満ちていた。己のみが、橋姫を助けられるのであろうと。
「綱、私にはその言葉だけで嬉しい。でも叶うなら、このまま洛中へ」
「もとより承知だ。して、その先で何を?」
橋姫はまた、微笑みを返す。
気付けば二時にも及んだ野分は嘘のように止み、空は澄み渡っている。だが太陽は南よりもだいぶ西へ傾いていた。
二人は駆け出す、己が使命を果たしに。
誰もが野分を、それに連れられた雷を畏れ、戸板を閉じて「桑原」と唱えながら引き籠もったまま、歩む者などいない大蔵省の南庭。三人の男の姿だけがそこにある。
清明と博雅、それに賀茂保憲である。
「保憲殿、如何なる由で、左京大夫様に呪詛などを」
「否、博雅様。保憲様が真に狙ったのは、私でありましょう」
これには博雅が驚きを呈するが、いずれの言葉にも、保憲は黙したままである。
「清明、そんな事があろうか。この方は、お前の兄弟子殿ではないか」
「……鬼女橋姫は、おれの名を知っていた。呪詛をかける相手じゃ、当然であろう」
四条通に現れた、彼岸への、まほろばの橋での事である。
「しかしお前の名は、朱雀門のお方や、先の羅城門のお方にも知られる程じゃ」
「あの方達は、封じられたモノではない。逆に橋姫は、長らく封じられておった」
博雅にはもう、反駁の意思は無い。清明がその事実に向き合おうとしているのに、それを阻む理由など、もはや無いのである。
「堀河殿の庇護を受ける代わりに、かの方の肉親でありながら政敵でもある、左京大夫様への呪詛を承った。貴方は、それに加えて私への呪詛を重ねられたのだ」
やおら向けられた保憲の瞳には、微かに緑色が差し込んでいる。
日は傾きつつあっても、月の光はまだ無いのに、である。
「妬ましや、あな、妬ましや――」
ぎょろりと、緑の目が清明の方を向く。
「何を仰る。其許(そこもと)は官人として順調に歩んで来たであろうに。清明の何を妬むのじゃ!」
「民草も、帝や臣でさえも、陰陽師として大成したお前を讃える。何故じゃ! 我こそは賀茂氏の長者、賀茂保憲。鉄を携え、帝と並び歩んだ、葛城山の一族の裔ぞ!」
「いえ、貴方様はお父上の、優れたる臣であった忠行様の、跡を継いだお方――」
「だからこそ、妬ましいのじゃ!」
保憲は出世より何より、あくまでも陰陽師としての大成を志していたのだ。
もはや、清明が何を言っても聞くまい。だが、
「私には分かります!」
博雅が、胸を張って叫ぶ。
「源姓を賜り、左中将を賜った其許が、何をのたまう!」
「だからこそ、分かるのじゃ! おれは皇籍より外された、ただの雅楽師よ。臣籍に下った者がどの様に過ごすか、分からぬ保憲殿でもあるまい」
かつて皇族にあった者。そこから離れれば、ただの人より窮屈な存在である。
某かの後ろ盾無しでは、生きることすら辛い。望んで野に下る者もいるであろうが、大抵は違う。
綱や頼光らの様に、武家として身を立てられる者もいよう。しかし、それも一握り。
「うぬ……」
「おれは、ただの雅楽師じゃ。笛を奏で、弦を弾き続けたとて、終には何も残らぬ」
博雅の赤心を、清明が継ぐ。
「ですが保憲様には、残すものがありましょうぞ」
保憲を含めた彼ら一族が、陰陽術を体系化し、ただの官人以上の功績を残したのは、民草こそ知らない。しかし清明は、誰よりもそれを知っている。
また清明と共に陰陽寮に在する保憲の子も、何かを残せる逸材であるのも。
「うぬ……」
過ぎたるほどの先がある。
保憲の中に満ちていた緑色の心は、にわかに色を失ってゆく。
「されどおれは、いくら己の身の上を顧みても、誰かを妬ましいなどとは、思わぬ」
そう、また博雅は言った。
博雅は自然(じねん)のまま音を奏でる。音は虚空に融け、残らぬ。彼はそれを是とする男である。
「うむ……」
保憲は天を見上げ、膝を着く。その目には、晴天の斜陽が映り込んでいた。
清明と兼家への呪詛、鬼女の調査を阻んだ件。
正気を取り戻した保憲は、一切をつまびらかに語る。
「始めにあったは、決して、お前への妬みなどでは無かったのだ……」
貴布禰の社にて怪異あり。
本来であれば、清明にも知らされたであろうそれはしかし、まず、今の賀茂氏の当主である保憲に伝えられたのだ。
「おれは、これぞ己の為すことと……思い上がりであった。それもこれも、お前の話で分かった。あれこそ鞍馬山の罠であったか」
保憲はそこで、封じられていたはずの、鬼女の力に当てられたのである。
それが彼の心の片隅にあった、陰陽師としての嫉妬を膨れあがらせた。
鞍馬山は、この心すら見通していたのだ。
保憲は鬼女を使役したつもりでいて、彼女にも鞍馬山にも、利用されていたのだ。
「彼らは、力を持った陰陽師を、除こうと考えたのでしょう。まずは私を。それが叶わなければ、呪詛を返された保憲様を。私が、この度の件を放っておけば、いずれは、保憲様の身に害が及びました。暗にこれを語った天狗も、それは知っていたはず」
今以て、あの護法鬼神と称した天狗が、助言を与えた意図は分からない。
「おれよりお前の方が、ずっと優れた陰陽師じゃ。いずれかであるなら、お前よりおれが倒れた方が、朝廷にとって傷が浅く済む」
自嘲も混じる保憲の言葉で、清明は気付く。
「――否、鞍馬山の企みとは、陰陽寮に変わって、朝廷に明確に食い込むことであったかと。しかし天狗の言う通りにしていたなら、いずれもが力を失う道程となったのでは」
「損得勘定と見ればよいのか――朝廷がお前という多大な損を出し、鞍馬山が朝廷への影響力という得をする所、朝廷も鞍馬山も、一つずつ損をする羽目になっていたか……」
ここで博雅は不思議に思う。
保憲が後に言った、多大ではない「朝廷の損」とは、呪詛返しを受ける保憲自身。だが、
「保憲殿、清明。鞍馬山が被るはずであった損とは、何であろうか?」
清明と保憲が頷き合い、清明の方からこれに答える。
「失われるのは『はし』じゃ。この暗澹(あんたん)たる世に、人は、彼岸、来世への期待と、浄土へ至ることを渇望しておる。そこに至るための道が一つ、消えるのじゃ」
博雅も気付いた。何が起ころうとしていたかを。
「そうか、お前が鬼女を「倒さぬ」と誓ったはそういう事か! 保憲殿が鬼女橋姫に弑(しい)されれば、陰陽師は、はしひめの真実を知らぬお前は全力を以て、退治せざるを得なかった。もし鬼女を倒さば、『橋姫』は一人となる。彼岸へ至る、三つの途の一つが切れる!」
仏法の徒の一角である鞍馬山のみならず、本邦の仏法僧すべてにとってそれは、僅かなりと信仰を落ち込ませる一因となる。
「そしておれは、清明が倒れたところで、はしひめに操られたまま。よしんば正気に戻ったとて、封じるに留めた……」
かつて賀茂氏の父祖が、はしひめを倒さず封じたのと同じく、彼女の素性と役割を知っていればこそ、そうせざるを得なかったであろう。
「保憲様。はしひめは、私が全霊を賭し、封じてご覧に入れます。保憲様は堀河殿の警護に当たって頂けませぬか?」
兼通もまた、呪詛返しを被るべき者の一人である。
保憲は深く頷き、それを受け入れる。
「清明、もう日が傾いてきた。早く堀川沿いへ」
鬼女が現れる前に。二人の男は、果たすべき役目を負い、急ぐ。
∴
堀川を下る橋姫と綱はようやく洛中に辿り着き、日が暮れてもなお、南へと走り続ける。
「橋姫、どこまで行けばよいのだ」
疲れなど見せず、綱が問う。彼に手を引かれる橋姫は、息せき切らせながら答える。
「四条まで。私たち二人で、四条に至れば、自ずと、あの娘は現れます」
限界に近いのを察した綱は、速度を緩めて橋姫に並ぶ。
そこに駆け寄る足音。
前に橋姫を襲った賊かと柄に手を掛けて振り向く綱の前に、過ぎるほどに見覚えのある顔が、過ぎるほど間近に迫っていた。
「綱! よう無事で戻った!」
「頼光様。数々の不義の責め、いくらでもお受けします。ですが今は、お目こぼしを!」
「お前が俺の前から姿を消したには、何か理由があったのであろう。聞かせてくれ!」
何も言わず姿を消した二人を頼光は、喜ばしげな顔で迎えた。彼は綱を信じたのだ。
頼光もまた、己が主を信じる。
「分かったのです、頼光様! 橋姫が誰と会おうとしていたのか」
「なんと!」
「あの時、橋姫は兼家様をお守りになり、清明様の元へ赴くつもりであったのです」
これまでの事、これからの事、橋姫から聞かされた事を全て、頼光に語る。無論、橋姫がヒトでないことも、包み隠さずに。
「波斯国の神の、巫女……いや、信じようぞ。むしろ御許が我らの前に現れたは、必然であったのやも知れぬ」
頼光の家も綱の家も、奉じるのは八幡大菩薩。かの神は、外来の神すらもその懐に秘めた神である。その中には、橋姫の祀る神も居たかも知れない。
「頼光様……」
己とさほど歳も違わぬのに、なんという器の大きさであろうか。綱はただ、頭を垂れる。
「一条戻り橋の浮浪者らにお前達を見かけたと聞いて追いかけてみれば、もうこんな所だ。足の速さに驚いたぞ。これならば、四条にもすぐに辿り着こう!」
「あの方達は無事だったのですね。良かった……」
昼間の野分の後、轟々と流れる堀川の流れを見て、彼らのことも気に掛けていた橋姫は、心からの安堵の表情を浮かべる。
そうして二人の若武者に連れられた橋姫は、ついに四条まで行き着くのであった。
堀川の流れはますます速い。野分の雨を集めた山が、今になっておびただしい水を吐き出しているからだ。
しかし闇夜の中ではその様も僅かにしか見えず、それが却って恐れを生み出す。
「こんな流れでは、鬼女の生み出した橋すら、流されてしまいそうだな……」
耳の側で鳴るかの如き轟音に、頼光は虚勢を張る。事実、水かさは河川敷を飲み込み、彼らの足下にまで迫るほどに増していた。
その虚勢は、これより現れる敵を恐れまいぞという、決意でもある。その兆しである、幽世(かくりょ)の橋が目の前に顕れては、尚更に。
「綱、抜かるなよ。橋姫、我らは御許を、どうすればよい?」
彼が「はっ」と短く発した後、橋姫も問いに答える。
「この橋は、顕界にて行き着くべき端を失った橋。私があちら側へ渡ることでこの橋は顕界に行き着く先を得ます。さすれば、隠形(おに)たるあの娘は、私に従うしかなくなる」
「では俺達は、御許を守ってあちらへ渡ればよいのだな?」
これは橋姫がいればこそ為せる業(わざ)。もし橋姫を伴わずにこの橋を渡れば、これは彼岸に行き着くのと同じ意味となる。それも生きながらに。
綱は橋姫を信じ、橋姫を信じる綱を頼光は信じ、三人は各々、一歩、また一歩と歩む。
その行く手から、突如男の叫び声が届く。
「清明! 大事ないか?!」
博雅が、清明を案じる声である。
彼らは、綱たちよりも先にここへ着き、既に鬼女『橋姫』と対峙していたのだ。
「博雅、逃げよ……」
呻くような声、清明が博雅を案じた物である。
希代の陰陽師と、古の鬼女の戦いは、既に決していた。清明は方術の限りを尽くし、式神、天将月将の力を最大限に借りて戦ったが、それすら届かなかったのだ。
「何を言う、お前を残してゆけるか!」
「倒すだけなら、できる。封じるのは、倒すより難い。おれこそ思い上がっていた……」
「お前がこの世に、取り返しの付かぬ疵など刻むものか。命を賭しても封じるつもりか」
清明にはまだ策があったが、それを博雅はあっさりと看破してしまった。
「ここは退こうぞ。お前を失ってはそれこそ、取り返しがつかぬ!」
清明らの企図を知らぬ頼光と綱は、ただ彼が倒されたとだけ思い、戦慄する。彼でも叶わぬ敵に、己ら如き若輩が敵うものなのかと。
そこへ、更なる畏怖を乗せた声が浴びせられる。
「妬ましい。互いに思う友を連れたお前らが、妬ましい。ここは選別の橋、お前達は揃って、奈落へ落ちよ!」
ゆらり、ゆらりと、緑眼が宙空で揺れている。
「貴女にも、いるはずじゃ。互いに、思いやりを向けるべき、友が……」
清明は立ち上がり、退かず、博雅の前に出ると、おぼつかぬ足取りで、反閇(へんばい)を踏む。
「――南斗、北斗、三台、玉女。左ガ青龍ハ万兵ヲ避ケ、右ガ白虎ハ不祥ヲ避ケ、前ガ朱雀ハ口舌ヲ避ケ、後ガ玄武ハ万鬼ヲ避クル」
――急々如律令
五行を表す桔梗の印が、鬼女を取り囲む。彼女を封じ込める、結界であった。
「清明!」
「無駄じゃ……」
ただの妖なら、身じろぎ一つ出来ぬはず。なのに彼女は、歩みを緩めた程度である。
ここは鬼女の領域。彼の全力を賭しても、これが精一杯なのだ。
「お前等も、妬ましい。友を連れ、良人を連れ――私には、何も無い! 名すら無い!」
鬼女の緑眼は、清明の後ろへ視線を突き刺す。その先には、橋姫の姿がある。
鉄輪を逆さに被いた緑眼の魔物、まさしく鬼女たる有り様。
「うん。やっと、会えたね……」
「なぜ、なぜお前だけが、友を、良人を連れている」
結界の端に触れ、なお前に進もうとする鬼女に向かい、橋姫も歩み出す。
橋姫を守ろうと綱が、頼光が前に出ようとするが、何故か指一本も動かすことが出来ない。ここは橋姫の領域でもある。今度は、彼らを止める結界を拵えたのだ。
「待たれよ、パルスィ(波斯姫)!」
清明が叫ぶ。これは、彼すらも押しとどめる力であった。
「ありがとう、綱」
何を言うのか。言葉を発することすらままならぬ綱は、これから起こる事を想像し、言いしれぬ恐怖に襲われる。
橋姫の手元で白刃が煌めく。それは綱の携えていた太刀、髭切であった。
清明ですら敵わぬ鬼女に、太刀を構えたところで敵おうものか。綱は橋姫を止めようと足掻くが、やはり動くことは叶わない。頼光も同じく、ただ成り行きを見守るだけ。
見れば橋姫の周りには、怪火が浮かんでいる。庵で綱と橋姫を助けた物であった。
「もう私達は、主神の元へ帰れない――」
鬼女の頭の上で鬼の角の如く屹立する鉄輪の脚それぞれに、怪火が明かりを灯す。
その明かりは、鬼女の顔に丹を塗った様な赤色に染める。
(金気を御す火気、もしや……!)
それは、遙か西方よりもたらされた、神火であった。
灯った神火は鉄輪を虚空に溶かして鬼女の力を奪い、彼女を清明の結界に押さえ込んだ。
「これからは、ともに参りましょう――」
結末は一瞬であった。
鬼女の身には、髭切が深々と突き立てられた。
綱達が戒めから解かれた時、『はしひめ』は一人となっていた。
緑眼に金髪。装いは鬼女の纏っていた、見知らぬ異国の物。だがその優しげな面だけは、綱が守ろうとした橋姫のものであった。
「橋姫、どうなってしまったのだ……」
ふらふらと歩み寄ろうとする綱を、頼光が、清明が引き止める。
「なりません。この橋はもはや、失われます」
「それに水かさも増している。このままでは川が溢れるぞ!」
二人を振り切って進もうとする綱に、橋姫が微笑む。
「妬むことを知らない貴方たちが、本当に妬ましい。さようなら……」
橋姫は本当に、この世の者ではなくなってしまったのだ。
それを悟った綱は、滂沱(ぼうだ)と涙しながら、背を向けるのであった。
∵
「クワァ……」
延々と続いた話に、鴉は飽きるよりも、ただただ呆気にとられていた。
「刀にまつわる者達の話は、これで終いだ。しかしもう少しだけ続きもあってな――源頼光が、橋姫を貶めた葛城氏の祖神一言主や、鞍馬山の背後に在った叡山の一党を討とうとしたり、渡辺綱が羅城門の鬼に、仙術を以て橋姫を呼び戻すように迫ったり、云々と」
それはまた今度聞きたいと、心の中での出来事とはいえ目まぐるしい体験をした鴉は、身振り羽振りで辞退する。
しかし、と鴉は思う。橋姫は綱を、綱は橋姫を好いていた様に感じた。
ヒトが妖を、妖がヒトを、恋するなどあり得るのか。否、あれは橋姫が、鬼女の嫉妬を己に向けるための策だったのかも知れない。
そうだ、きっとそうなのだ。
ひとり鴉が納得していると、坊主が、それならばという体で言い出す。
「話をここまでにして帰るなら、すぐに飛んだ方がよいのではないか? 信濃(しなの)は遠いぞ」
鴉の生地であり、常の在所は信濃国である。ここ熊野からは相当な距離がある。
「クワァ、ガッガッ!」
その言葉に、鴉は「しからば」と暇乞いし、飛び立った。
鴉は陽光を背に飛び、眼下に巨神の足跡が如き淡海(あわうみ)を見てすぐ、丑寅へ向きを変える。
天竜川を遡って信濃に至ろうとする、数えきれぬほど辿った、鴉が好む道程である。
視界が途切れるほどの彼方には、本邦最高峰である芙蓉(ふよう)の峰。
(己も橋姫の様に、偽りでも、ヒトを好きになる事があるのだろうか。いや無いな)
つらつらと考えながら、これからも数えきれぬほど飛ぶであろう空を、鴉は征く。
平安の世が終わり、この国に、一つの変革をもたらす刻まで。
第10話注釈
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1 波斯国:ペルシャ。現在のイランの古名
※2 天竺:現在のインドの古名
※3 上代:日本の有史以来、飛鳥時代から奈良時代を指す。文脈により、神話時代も含められる。
※4 新羅征伐:三韓征伐とも。新羅は現南北朝鮮にまたがる、主に日本海側の地域
※5 記紀:記紀神話、古事記と日本書紀の総称
蛇足:
パルスィ:ペルシャ人という意で固有名詞と考えず、故にパルさんは名無しの巫女さんとしました
三途川の橋:平安時代末期に消えた思想で、本話はそれとゾロアスター教の橋を習合させました
パルさん達の主神:アフラ・マズダ(ゾロアスター教)という事でよろしくお願いします
山蛇:蛇はゾロアスター教で邪悪な存在とのことなので。山夫ときのえもそんな感じです
呪:文字としての記述も憚るべきなのですが、安易に口にするのは絶対に控えて下さい(真言も)
清明&博雅:本話を省みると、東方二次と言うより『陰陽師』(夢枕貘)の二次創作ですね……
髭切:本稿脱稿現在、膝丸は順調に育ってますが兄者は依然として来てません(おのれ検非違使)
鴉の行き先:
ここ http://thatz-chicken.cocolog-nifty.com/novel/historicaltrilogy/subpage_konohana_01.html と
ここ http://thatz-chicken.cocolog-nifty.com/novel/historicaltrilogy/subpage_shinonome.html へ
失われたはし 第10話
「波斯国の姫であるが故、『はしひめ』か」(※1)
清明が語る橋姫の素性に、博雅が深く頷きながら言った。
「天竺よりもより西方の民――とは言うがな、この国が興る前には、そちらよりも人が渡って来たのかも知れぬのじゃ。火を焚き、鉄を鍛える者。あるいは田に水を引き、稲穂を育て、多くの民を従える者でもある。そも、大和の民とはなんぞや?」(※2)
「なんと難しい問いをする……」
良民とされない者を除けば、この問いは案外と簡単な物である。しかし博雅はそれが出来ず悩む。
「やはり、お前はよい男だ」
「いや、何の力も無いくせに、哀れむべきでない者にまで同情する、愚か者よ」
激しい雨風の中、牛車は洛中へ戻り、彼らは大内裏へと足を向けるのであった。
「そう、だから私は『波斯姫』」
二人の『はしひめ』の由縁を聞き、綱は呆然とする。覚悟していたつもりであったのに。
それが本当なら、目の前に居る橋姫もまた、大和の民どころかヒトですらない。
「私達は、上代にこの国に連れてこられた。ある物のために、一族ごと」(※3)
数百年も前、ただの少年の綱にとっては、気の遠くなるような昔の話。それを波斯姫――橋姫は、体験してきたのだ。
「上代……」
「この国の巫女王が大陸に、新羅に攻め寄せた時、ある豪族が遣わされたの」
橋姫が言うのは、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の后、神功皇后(じんぐうこうごう)の頃に行われた新羅(しらぎ)征伐(※4)の事であろうか。若いながらも、武家として確固たる家を持つ綱であればこそ、これを知っていた。
「それはもう、記紀にうたわれる頃の話ではないか……」(※5)
ヒトか妖かより、己の生きるよりずっと旧い世の中を生きた者であるという事実に、綱は橋姫との間に恐ろしい隔たりを覚える。それは時間としてより、距離として感じられた。
すぐ側に居るのに、千里も彼方に在る者であるかのように。
天の瓶が割れたかの如き豪雨を掻き分け、清明と博雅は、沓を水に浸しながら歩む。
目指すは内裏の北に位置する大蔵省、主計寮である。
「清明よ! 前に言っていた信仰とは、葛城(かつらぎ)氏に係るものか!」
「そうじゃ! 新羅征伐の折り、波斯人を日の本に連れて来たのが、葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)! それを遣わした神功皇后の母もまた葛城氏、葛城高額媛(かずらきのたかぬかひめ)」
「その葛城氏の神格、一言主(ひとことぬし)を祖神として、南都に奉じたのが、今の賀茂氏で――」
「貴布禰の社は、これも賀茂氏が祀る賀茂川から連なる、水神の系譜じゃ!」
「信仰は民、民は信仰。私達は葛城襲津彦の、葛城氏の手によって、我が神と共にこちらに渡って来たの。そして私は、主神を奉る巫(こうなぎ)」
綱の意識の中で遙かに遠くに居た橋姫は、いつの間にかすぐ側まで歩み寄っていた。これは橋姫から懸命に近づいたのだ。心の中の万里の道を駆けて。
橋姫が真に、万里よりもなお遠い道を辿って来たのを知った綱は、それを受け止める。
「よく話してくれた……ならば俺はどうすればよい、御許のために」
ヒトではなかったかも知れない、だが妖し勿怪ではない。いずれにせよ橋姫は、それを赤心で話してくれたのだ。それだけで綱は、何かが救われた気がした。
これは、己の始めから課せられていた運命やも知れぬ。
今の綱には、主君や父兄へ果たすべき忠孝よりも、強い使命感が満ちていた。己のみが、橋姫を助けられるのであろうと。
「綱、私にはその言葉だけで嬉しい。でも叶うなら、このまま洛中へ」
「もとより承知だ。して、その先で何を?」
橋姫はまた、微笑みを返す。
気付けば二時にも及んだ野分は嘘のように止み、空は澄み渡っている。だが太陽は南よりもだいぶ西へ傾いていた。
二人は駆け出す、己が使命を果たしに。
誰もが野分を、それに連れられた雷を畏れ、戸板を閉じて「桑原」と唱えながら引き籠もったまま、歩む者などいない大蔵省の南庭。三人の男の姿だけがそこにある。
清明と博雅、それに賀茂保憲である。
「保憲殿、如何なる由で、左京大夫様に呪詛などを」
「否、博雅様。保憲様が真に狙ったのは、私でありましょう」
これには博雅が驚きを呈するが、いずれの言葉にも、保憲は黙したままである。
「清明、そんな事があろうか。この方は、お前の兄弟子殿ではないか」
「……鬼女橋姫は、おれの名を知っていた。呪詛をかける相手じゃ、当然であろう」
四条通に現れた、彼岸への、まほろばの橋での事である。
「しかしお前の名は、朱雀門のお方や、先の羅城門のお方にも知られる程じゃ」
「あの方達は、封じられたモノではない。逆に橋姫は、長らく封じられておった」
博雅にはもう、反駁の意思は無い。清明がその事実に向き合おうとしているのに、それを阻む理由など、もはや無いのである。
「堀河殿の庇護を受ける代わりに、かの方の肉親でありながら政敵でもある、左京大夫様への呪詛を承った。貴方は、それに加えて私への呪詛を重ねられたのだ」
やおら向けられた保憲の瞳には、微かに緑色が差し込んでいる。
日は傾きつつあっても、月の光はまだ無いのに、である。
「妬ましや、あな、妬ましや――」
ぎょろりと、緑の目が清明の方を向く。
「何を仰る。其許(そこもと)は官人として順調に歩んで来たであろうに。清明の何を妬むのじゃ!」
「民草も、帝や臣でさえも、陰陽師として大成したお前を讃える。何故じゃ! 我こそは賀茂氏の長者、賀茂保憲。鉄を携え、帝と並び歩んだ、葛城山の一族の裔ぞ!」
「いえ、貴方様はお父上の、優れたる臣であった忠行様の、跡を継いだお方――」
「だからこそ、妬ましいのじゃ!」
保憲は出世より何より、あくまでも陰陽師としての大成を志していたのだ。
もはや、清明が何を言っても聞くまい。だが、
「私には分かります!」
博雅が、胸を張って叫ぶ。
「源姓を賜り、左中将を賜った其許が、何をのたまう!」
「だからこそ、分かるのじゃ! おれは皇籍より外された、ただの雅楽師よ。臣籍に下った者がどの様に過ごすか、分からぬ保憲殿でもあるまい」
かつて皇族にあった者。そこから離れれば、ただの人より窮屈な存在である。
某かの後ろ盾無しでは、生きることすら辛い。望んで野に下る者もいるであろうが、大抵は違う。
綱や頼光らの様に、武家として身を立てられる者もいよう。しかし、それも一握り。
「うぬ……」
「おれは、ただの雅楽師じゃ。笛を奏で、弦を弾き続けたとて、終には何も残らぬ」
博雅の赤心を、清明が継ぐ。
「ですが保憲様には、残すものがありましょうぞ」
保憲を含めた彼ら一族が、陰陽術を体系化し、ただの官人以上の功績を残したのは、民草こそ知らない。しかし清明は、誰よりもそれを知っている。
また清明と共に陰陽寮に在する保憲の子も、何かを残せる逸材であるのも。
「うぬ……」
過ぎたるほどの先がある。
保憲の中に満ちていた緑色の心は、にわかに色を失ってゆく。
「されどおれは、いくら己の身の上を顧みても、誰かを妬ましいなどとは、思わぬ」
そう、また博雅は言った。
博雅は自然(じねん)のまま音を奏でる。音は虚空に融け、残らぬ。彼はそれを是とする男である。
「うむ……」
保憲は天を見上げ、膝を着く。その目には、晴天の斜陽が映り込んでいた。
清明と兼家への呪詛、鬼女の調査を阻んだ件。
正気を取り戻した保憲は、一切をつまびらかに語る。
「始めにあったは、決して、お前への妬みなどでは無かったのだ……」
貴布禰の社にて怪異あり。
本来であれば、清明にも知らされたであろうそれはしかし、まず、今の賀茂氏の当主である保憲に伝えられたのだ。
「おれは、これぞ己の為すことと……思い上がりであった。それもこれも、お前の話で分かった。あれこそ鞍馬山の罠であったか」
保憲はそこで、封じられていたはずの、鬼女の力に当てられたのである。
それが彼の心の片隅にあった、陰陽師としての嫉妬を膨れあがらせた。
鞍馬山は、この心すら見通していたのだ。
保憲は鬼女を使役したつもりでいて、彼女にも鞍馬山にも、利用されていたのだ。
「彼らは、力を持った陰陽師を、除こうと考えたのでしょう。まずは私を。それが叶わなければ、呪詛を返された保憲様を。私が、この度の件を放っておけば、いずれは、保憲様の身に害が及びました。暗にこれを語った天狗も、それは知っていたはず」
今以て、あの護法鬼神と称した天狗が、助言を与えた意図は分からない。
「おれよりお前の方が、ずっと優れた陰陽師じゃ。いずれかであるなら、お前よりおれが倒れた方が、朝廷にとって傷が浅く済む」
自嘲も混じる保憲の言葉で、清明は気付く。
「――否、鞍馬山の企みとは、陰陽寮に変わって、朝廷に明確に食い込むことであったかと。しかし天狗の言う通りにしていたなら、いずれもが力を失う道程となったのでは」
「損得勘定と見ればよいのか――朝廷がお前という多大な損を出し、鞍馬山が朝廷への影響力という得をする所、朝廷も鞍馬山も、一つずつ損をする羽目になっていたか……」
ここで博雅は不思議に思う。
保憲が後に言った、多大ではない「朝廷の損」とは、呪詛返しを受ける保憲自身。だが、
「保憲殿、清明。鞍馬山が被るはずであった損とは、何であろうか?」
清明と保憲が頷き合い、清明の方からこれに答える。
「失われるのは『はし』じゃ。この暗澹(あんたん)たる世に、人は、彼岸、来世への期待と、浄土へ至ることを渇望しておる。そこに至るための道が一つ、消えるのじゃ」
博雅も気付いた。何が起ころうとしていたかを。
「そうか、お前が鬼女を「倒さぬ」と誓ったはそういう事か! 保憲殿が鬼女橋姫に弑(しい)されれば、陰陽師は、はしひめの真実を知らぬお前は全力を以て、退治せざるを得なかった。もし鬼女を倒さば、『橋姫』は一人となる。彼岸へ至る、三つの途の一つが切れる!」
仏法の徒の一角である鞍馬山のみならず、本邦の仏法僧すべてにとってそれは、僅かなりと信仰を落ち込ませる一因となる。
「そしておれは、清明が倒れたところで、はしひめに操られたまま。よしんば正気に戻ったとて、封じるに留めた……」
かつて賀茂氏の父祖が、はしひめを倒さず封じたのと同じく、彼女の素性と役割を知っていればこそ、そうせざるを得なかったであろう。
「保憲様。はしひめは、私が全霊を賭し、封じてご覧に入れます。保憲様は堀河殿の警護に当たって頂けませぬか?」
兼通もまた、呪詛返しを被るべき者の一人である。
保憲は深く頷き、それを受け入れる。
「清明、もう日が傾いてきた。早く堀川沿いへ」
鬼女が現れる前に。二人の男は、果たすべき役目を負い、急ぐ。
∴
堀川を下る橋姫と綱はようやく洛中に辿り着き、日が暮れてもなお、南へと走り続ける。
「橋姫、どこまで行けばよいのだ」
疲れなど見せず、綱が問う。彼に手を引かれる橋姫は、息せき切らせながら答える。
「四条まで。私たち二人で、四条に至れば、自ずと、あの娘は現れます」
限界に近いのを察した綱は、速度を緩めて橋姫に並ぶ。
そこに駆け寄る足音。
前に橋姫を襲った賊かと柄に手を掛けて振り向く綱の前に、過ぎるほどに見覚えのある顔が、過ぎるほど間近に迫っていた。
「綱! よう無事で戻った!」
「頼光様。数々の不義の責め、いくらでもお受けします。ですが今は、お目こぼしを!」
「お前が俺の前から姿を消したには、何か理由があったのであろう。聞かせてくれ!」
何も言わず姿を消した二人を頼光は、喜ばしげな顔で迎えた。彼は綱を信じたのだ。
頼光もまた、己が主を信じる。
「分かったのです、頼光様! 橋姫が誰と会おうとしていたのか」
「なんと!」
「あの時、橋姫は兼家様をお守りになり、清明様の元へ赴くつもりであったのです」
これまでの事、これからの事、橋姫から聞かされた事を全て、頼光に語る。無論、橋姫がヒトでないことも、包み隠さずに。
「波斯国の神の、巫女……いや、信じようぞ。むしろ御許が我らの前に現れたは、必然であったのやも知れぬ」
頼光の家も綱の家も、奉じるのは八幡大菩薩。かの神は、外来の神すらもその懐に秘めた神である。その中には、橋姫の祀る神も居たかも知れない。
「頼光様……」
己とさほど歳も違わぬのに、なんという器の大きさであろうか。綱はただ、頭を垂れる。
「一条戻り橋の浮浪者らにお前達を見かけたと聞いて追いかけてみれば、もうこんな所だ。足の速さに驚いたぞ。これならば、四条にもすぐに辿り着こう!」
「あの方達は無事だったのですね。良かった……」
昼間の野分の後、轟々と流れる堀川の流れを見て、彼らのことも気に掛けていた橋姫は、心からの安堵の表情を浮かべる。
そうして二人の若武者に連れられた橋姫は、ついに四条まで行き着くのであった。
堀川の流れはますます速い。野分の雨を集めた山が、今になっておびただしい水を吐き出しているからだ。
しかし闇夜の中ではその様も僅かにしか見えず、それが却って恐れを生み出す。
「こんな流れでは、鬼女の生み出した橋すら、流されてしまいそうだな……」
耳の側で鳴るかの如き轟音に、頼光は虚勢を張る。事実、水かさは河川敷を飲み込み、彼らの足下にまで迫るほどに増していた。
その虚勢は、これより現れる敵を恐れまいぞという、決意でもある。その兆しである、幽世(かくりょ)の橋が目の前に顕れては、尚更に。
「綱、抜かるなよ。橋姫、我らは御許を、どうすればよい?」
彼が「はっ」と短く発した後、橋姫も問いに答える。
「この橋は、顕界にて行き着くべき端を失った橋。私があちら側へ渡ることでこの橋は顕界に行き着く先を得ます。さすれば、隠形(おに)たるあの娘は、私に従うしかなくなる」
「では俺達は、御許を守ってあちらへ渡ればよいのだな?」
これは橋姫がいればこそ為せる業(わざ)。もし橋姫を伴わずにこの橋を渡れば、これは彼岸に行き着くのと同じ意味となる。それも生きながらに。
綱は橋姫を信じ、橋姫を信じる綱を頼光は信じ、三人は各々、一歩、また一歩と歩む。
その行く手から、突如男の叫び声が届く。
「清明! 大事ないか?!」
博雅が、清明を案じる声である。
彼らは、綱たちよりも先にここへ着き、既に鬼女『橋姫』と対峙していたのだ。
「博雅、逃げよ……」
呻くような声、清明が博雅を案じた物である。
希代の陰陽師と、古の鬼女の戦いは、既に決していた。清明は方術の限りを尽くし、式神、天将月将の力を最大限に借りて戦ったが、それすら届かなかったのだ。
「何を言う、お前を残してゆけるか!」
「倒すだけなら、できる。封じるのは、倒すより難い。おれこそ思い上がっていた……」
「お前がこの世に、取り返しの付かぬ疵など刻むものか。命を賭しても封じるつもりか」
清明にはまだ策があったが、それを博雅はあっさりと看破してしまった。
「ここは退こうぞ。お前を失ってはそれこそ、取り返しがつかぬ!」
清明らの企図を知らぬ頼光と綱は、ただ彼が倒されたとだけ思い、戦慄する。彼でも叶わぬ敵に、己ら如き若輩が敵うものなのかと。
そこへ、更なる畏怖を乗せた声が浴びせられる。
「妬ましい。互いに思う友を連れたお前らが、妬ましい。ここは選別の橋、お前達は揃って、奈落へ落ちよ!」
ゆらり、ゆらりと、緑眼が宙空で揺れている。
「貴女にも、いるはずじゃ。互いに、思いやりを向けるべき、友が……」
清明は立ち上がり、退かず、博雅の前に出ると、おぼつかぬ足取りで、反閇(へんばい)を踏む。
「――南斗、北斗、三台、玉女。左ガ青龍ハ万兵ヲ避ケ、右ガ白虎ハ不祥ヲ避ケ、前ガ朱雀ハ口舌ヲ避ケ、後ガ玄武ハ万鬼ヲ避クル」
――急々如律令
五行を表す桔梗の印が、鬼女を取り囲む。彼女を封じ込める、結界であった。
「清明!」
「無駄じゃ……」
ただの妖なら、身じろぎ一つ出来ぬはず。なのに彼女は、歩みを緩めた程度である。
ここは鬼女の領域。彼の全力を賭しても、これが精一杯なのだ。
「お前等も、妬ましい。友を連れ、良人を連れ――私には、何も無い! 名すら無い!」
鬼女の緑眼は、清明の後ろへ視線を突き刺す。その先には、橋姫の姿がある。
鉄輪を逆さに被いた緑眼の魔物、まさしく鬼女たる有り様。
「うん。やっと、会えたね……」
「なぜ、なぜお前だけが、友を、良人を連れている」
結界の端に触れ、なお前に進もうとする鬼女に向かい、橋姫も歩み出す。
橋姫を守ろうと綱が、頼光が前に出ようとするが、何故か指一本も動かすことが出来ない。ここは橋姫の領域でもある。今度は、彼らを止める結界を拵えたのだ。
「待たれよ、パルスィ(波斯姫)!」
清明が叫ぶ。これは、彼すらも押しとどめる力であった。
「ありがとう、綱」
何を言うのか。言葉を発することすらままならぬ綱は、これから起こる事を想像し、言いしれぬ恐怖に襲われる。
橋姫の手元で白刃が煌めく。それは綱の携えていた太刀、髭切であった。
清明ですら敵わぬ鬼女に、太刀を構えたところで敵おうものか。綱は橋姫を止めようと足掻くが、やはり動くことは叶わない。頼光も同じく、ただ成り行きを見守るだけ。
見れば橋姫の周りには、怪火が浮かんでいる。庵で綱と橋姫を助けた物であった。
「もう私達は、主神の元へ帰れない――」
鬼女の頭の上で鬼の角の如く屹立する鉄輪の脚それぞれに、怪火が明かりを灯す。
その明かりは、鬼女の顔に丹を塗った様な赤色に染める。
(金気を御す火気、もしや……!)
それは、遙か西方よりもたらされた、神火であった。
灯った神火は鉄輪を虚空に溶かして鬼女の力を奪い、彼女を清明の結界に押さえ込んだ。
「これからは、ともに参りましょう――」
結末は一瞬であった。
鬼女の身には、髭切が深々と突き立てられた。
綱達が戒めから解かれた時、『はしひめ』は一人となっていた。
緑眼に金髪。装いは鬼女の纏っていた、見知らぬ異国の物。だがその優しげな面だけは、綱が守ろうとした橋姫のものであった。
「橋姫、どうなってしまったのだ……」
ふらふらと歩み寄ろうとする綱を、頼光が、清明が引き止める。
「なりません。この橋はもはや、失われます」
「それに水かさも増している。このままでは川が溢れるぞ!」
二人を振り切って進もうとする綱に、橋姫が微笑む。
「妬むことを知らない貴方たちが、本当に妬ましい。さようなら……」
橋姫は本当に、この世の者ではなくなってしまったのだ。
それを悟った綱は、滂沱(ぼうだ)と涙しながら、背を向けるのであった。
∵
「クワァ……」
延々と続いた話に、鴉は飽きるよりも、ただただ呆気にとられていた。
「刀にまつわる者達の話は、これで終いだ。しかしもう少しだけ続きもあってな――源頼光が、橋姫を貶めた葛城氏の祖神一言主や、鞍馬山の背後に在った叡山の一党を討とうとしたり、渡辺綱が羅城門の鬼に、仙術を以て橋姫を呼び戻すように迫ったり、云々と」
それはまた今度聞きたいと、心の中での出来事とはいえ目まぐるしい体験をした鴉は、身振り羽振りで辞退する。
しかし、と鴉は思う。橋姫は綱を、綱は橋姫を好いていた様に感じた。
ヒトが妖を、妖がヒトを、恋するなどあり得るのか。否、あれは橋姫が、鬼女の嫉妬を己に向けるための策だったのかも知れない。
そうだ、きっとそうなのだ。
ひとり鴉が納得していると、坊主が、それならばという体で言い出す。
「話をここまでにして帰るなら、すぐに飛んだ方がよいのではないか? 信濃(しなの)は遠いぞ」
鴉の生地であり、常の在所は信濃国である。ここ熊野からは相当な距離がある。
「クワァ、ガッガッ!」
その言葉に、鴉は「しからば」と暇乞いし、飛び立った。
鴉は陽光を背に飛び、眼下に巨神の足跡が如き淡海(あわうみ)を見てすぐ、丑寅へ向きを変える。
天竜川を遡って信濃に至ろうとする、数えきれぬほど辿った、鴉が好む道程である。
視界が途切れるほどの彼方には、本邦最高峰である芙蓉(ふよう)の峰。
(己も橋姫の様に、偽りでも、ヒトを好きになる事があるのだろうか。いや無いな)
つらつらと考えながら、これからも数えきれぬほど飛ぶであろう空を、鴉は征く。
平安の世が終わり、この国に、一つの変革をもたらす刻まで。
第10話注釈
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※1 波斯国:ペルシャ。現在のイランの古名
※2 天竺:現在のインドの古名
※3 上代:日本の有史以来、飛鳥時代から奈良時代を指す。文脈により、神話時代も含められる。
※4 新羅征伐:三韓征伐とも。新羅は現南北朝鮮にまたがる、主に日本海側の地域
※5 記紀:記紀神話、古事記と日本書紀の総称
蛇足:
パルスィ:ペルシャ人という意で固有名詞と考えず、故にパルさんは名無しの巫女さんとしました
三途川の橋:平安時代末期に消えた思想で、本話はそれとゾロアスター教の橋を習合させました
パルさん達の主神:アフラ・マズダ(ゾロアスター教)という事でよろしくお願いします
山蛇:蛇はゾロアスター教で邪悪な存在とのことなので。山夫ときのえもそんな感じです
呪:文字としての記述も憚るべきなのですが、安易に口にするのは絶対に控えて下さい(真言も)
清明&博雅:本話を省みると、東方二次と言うより『陰陽師』(夢枕貘)の二次創作ですね……
髭切:本稿脱稿現在、膝丸は順調に育ってますが兄者は依然として来てません(おのれ検非違使)
鴉の行き先:
ここ http://thatz-chicken.cocolog-nifty.com/novel/historicaltrilogy/subpage_konohana_01.html と
ここ http://thatz-chicken.cocolog-nifty.com/novel/historicaltrilogy/subpage_shinonome.html へ
第2章 失われたはし 一覧
感想をツイートする
ツイート








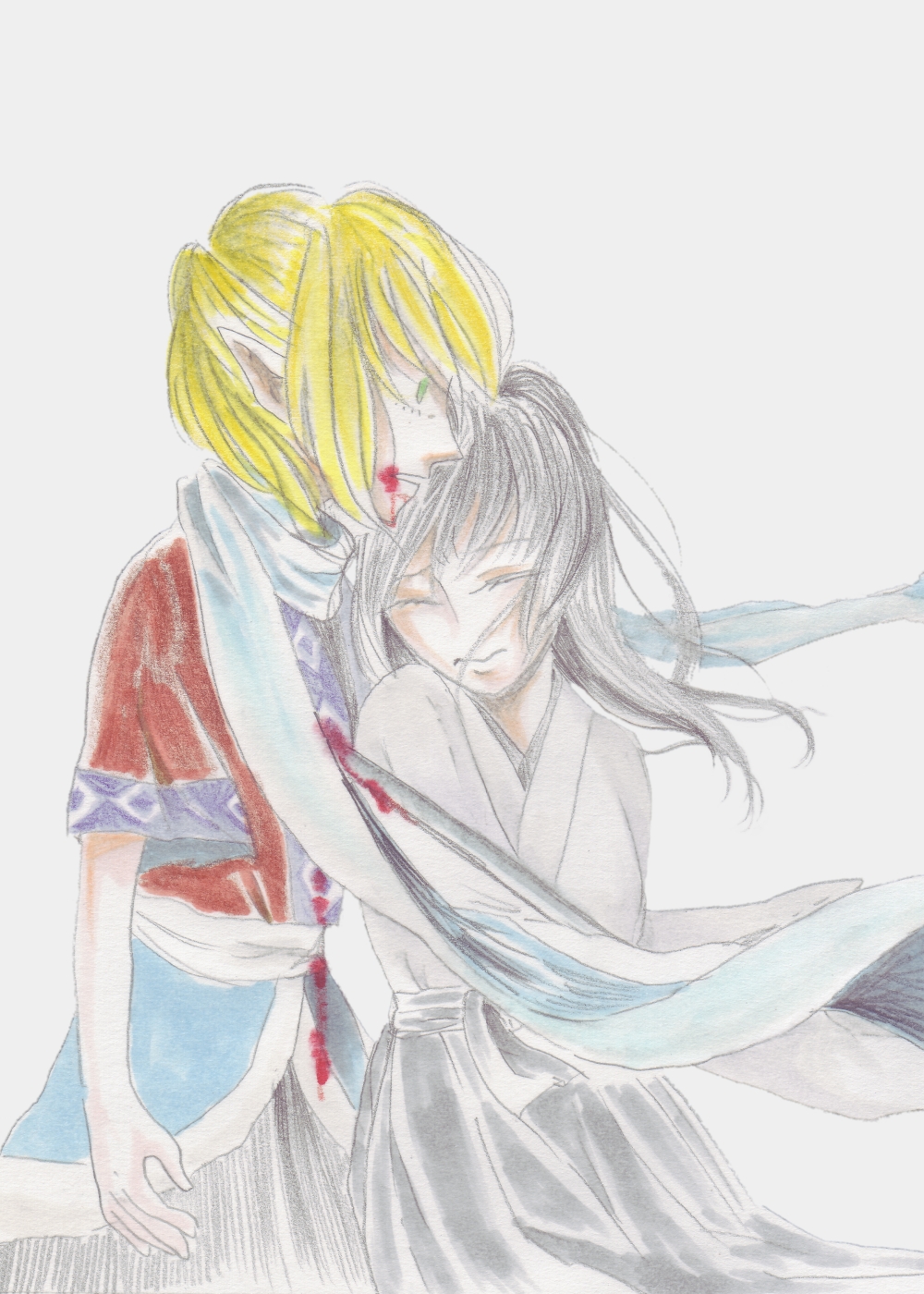



おもしろかったです!
この鴉は射命丸かな?